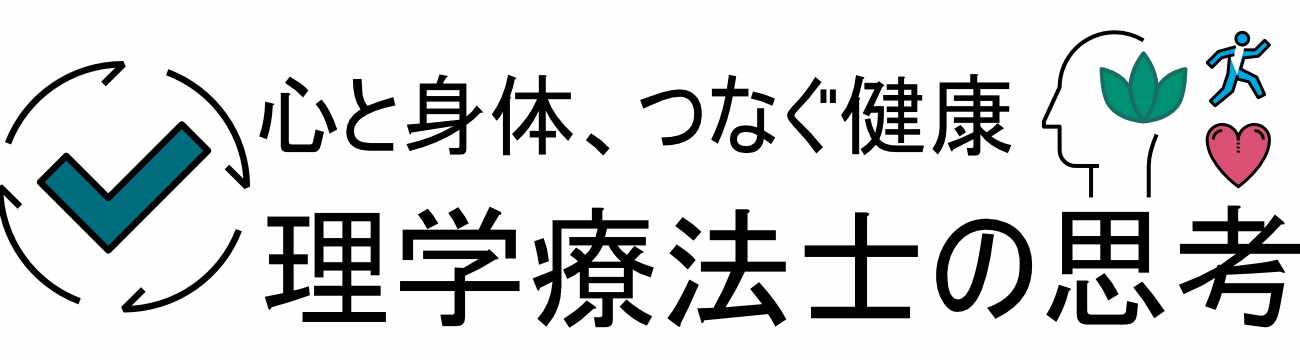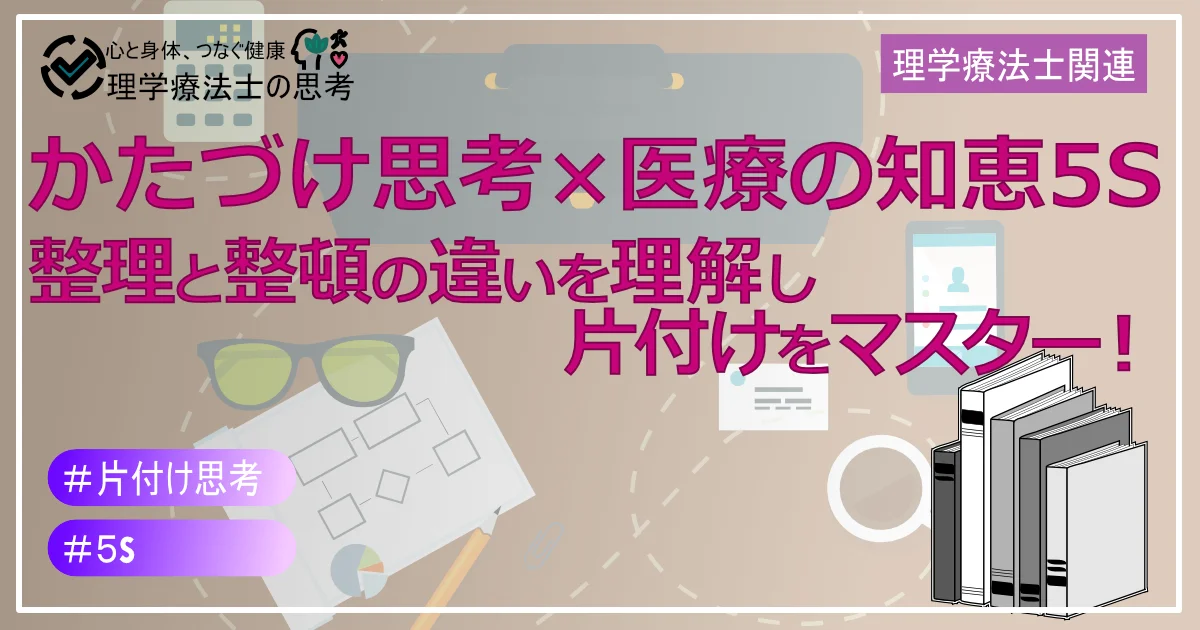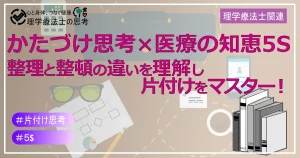「部屋がなかなか片付かない…」
「頭の中がごちゃごちゃして集中できない…」
そんな悩みを抱えていませんか?
片付けは、単に見た目をきれいにするだけでなく、私たちの思考や行動、さらには安全性にも深く関わっています。
今回は、ベストセラー『かたづけ思考』で提唱されている「整理」と「整頓」の違い、特にその中核となる「分ける」作業に着目し、その本質を掘り下げます。
さらに、医療や製造業の現場で徹底されている「5S」(整理・整頓・清掃・清潔・躾)の考え方を取り入れることで、より実践的で効果的な片付け術を身につけていきましょう。
この記事は、以下のような方におすすめです。
- 整理・整頓の具体的な方法を知りたい
- 片付けの基本をしっかり学びたい
- 「かたづけ思考」をより深く理解したい
- 医療現場の知恵「5S」に興味がある
なぜ片付けに「5S」が役立つのか?医療現場の知恵
まず、今回の記事で参考にする「5S」について簡単にご紹介します。
5Sとは、主に職場環境の改善や維持のために用いられるスローガンで、以下の5つの要素の頭文字をとったものです。
- 整理 (Seiri): 要るものと要らないものを分け、要らないものを捨てること。
- 整頓 (Seiton): 要るものを使いやすいように置き場を決めて、分かりやすく表示すること。
- 清掃 (Seiso): 身の回りのものや職場をきれいに掃除すること。
- 清潔 (Seiketsu): 整理・整頓・清掃の状態を維持すること。
- 躾 (Shitsuke): 決められたルールや手順を正しく守る習慣をつけること。
特に医療現場では、5Sの徹底が医療安全の確保、業務効率の向上、ミスの防止に直結するため、非常に重要視されています。
この「安全」や「効率」という視点は、私たちの日常生活や仕事の片付けにも大いに役立ちます。
片付けの第一歩:「整理」における「分ける」=分別
『かたづけ思考』によれば、片付けは「整理」→「整頓」の順に進めるのが基本です。
そして「整理」は、「出す→分ける→減らす→しまう」の4ステップで構成されます。
この整理段階での「分ける」は、「分別(ぶんべつ)」と呼ばれます。
ポイント:不要なものを取り除く(捨てる・手放す)ことを前提に分ける
文字通り、「分けて」「分かれる」こと。
つまり、今あるモノやコトの中から、要らないもの・やらないことを明確に見つけ出し、区別する作業です。
- 「モノ」の分別:
- 目の前にあるものを「要るもの」と「要らないもの」に分けます。
- 5Sの視点: 単に好き嫌いやまだ使えるかだけでなく、「本当に必要か?」「安全に使えるか?(壊れかけなど)」「保管スペースを圧迫していないか?」といった、より客観的な基準で判断します。医療現場で不要な物品や期限切れの薬剤を処分するように、リスク管理の視点も重要です。
- 「コト」(思考やタスク)の分別:
- 頭の中にある「やることリスト」や「悩み事」を、「本当にやること・考えるべきこと」と「やらないこと・考えないこと」に分けます。
- 5Sの視点: 「やらないこと」を決めることで、取り組むべきタスクに集中でき、効率が上がります。これは、医療現場で不要な作業手順をなくし、コア業務に集中する考え方と同じです。
整理における「分別」は、まず対象を絞り込み、身軽になるための重要なステップです。
片付けの第二段階:「整頓」における「分ける」=分類
整理によって要るものだけが残ったら、次のステップは「整頓」です。
整頓は、「分ける→配置する→収納する」の3ステップで進みます。
この整頓段階での「分ける」は、「分類(ぶんるい)」と呼ばれます。
残したものを使いやすくする(残す・活用する)ことを前提に分ける
分別を経て残った「要るもの」や「やること」を、共通点や関連性、使用頻度などに基づいてグループ分けし、分かりやすく整理する作業です。
- 「モノ」の分類:
- 残ったモノを、種類、用途、使う場所、使う人などでグループ分けします。
- 5Sの視点: ここで重要なのが、5Sの整頓の考え方、つまり「誰にでも分かりやすく、すぐに取り出せるように配置・表示すること」です。グループ分けしたら、引き出しやファイルに分かりやすい名前(ラベリング)をつけましょう。医療現場では、誤使用を防ぎ、誰でも迅速に必要なものを取り出せるよう、定位置管理と明確な表示が不可欠です。『かたづけ思考』でNGとされる「その他」という分類名は、目的が曖昧でブラックボックス化しやすいため、5Sの「見える化」「標準化」の観点からも避けるべきです。
- 「コト」(タスクや情報)の分類:
- 整理(分別)で「やること」を決めたタスクを、「いつやるか」「どこでやるか」「どのくらいの時間がかかるか」といった基準で分け、スケジュールに落とし込みます。プロジェクトごとにタスクを分類したり、緊急度と重要度で分類したりするのも有効です。
- 5Sの視点: タスクを分類しスケジュール化することで、計画的に実行でき、抜け漏れを防ぎます。これは、作業手順を明確にし、効率的に業務を進める5Sの考え方と共通します。
整頓における「分類」は、必要な時に必要なモノや情報にスムーズにアクセスするためのステップです。
まとめ:分別と分類を理解し、5Sの視点で片付けをレベルアップ!
今回は、「かたづけ思考」における整理の「分別」と整頓の「分類」の違いを、医療現場の知恵「5S」の視点を交えて掘り下げました。
- 整理の「分別」: 不要なものを取り除く(捨てる前提)。安全・効率の観点も加えて判断。
- 整頓の「分類」: 必要なものを使いやすくする(残す・活用する前提)。誰でも分かるように、定位置・定表示を意識する。
この二つの「分ける」の違いを意識し、片付けのステップ(整理→整頓)を正しく踏むことで、モノだけでなく、頭の中(コト)も驚くほどスッキリするはずです。
ごちゃごちゃした状態は、探し物による時間のロスだけでなく、集中力の低下や、場合によっては事故のリスクにもつながります。5Sの「整理」「整頓」を意識することは、単にきれいにするだけでなく、「安全」で「効率的」な環境を手に入れることでもあるのです。
さらに、整理・整頓された状態を維持するための「清掃」「清潔」、そしてそれを習慣化する「躾」へと繋げていくことで、片付けの効果は持続します。
まずは、身の回りの小さなスペースから、「分別」と「分類」を意識して片付けを始めてみませんか? きっと、思考もクリアになり、より快適で生産的な毎日を送るための一歩となるはずです。一緒に片付けができる人を目指しましょう!