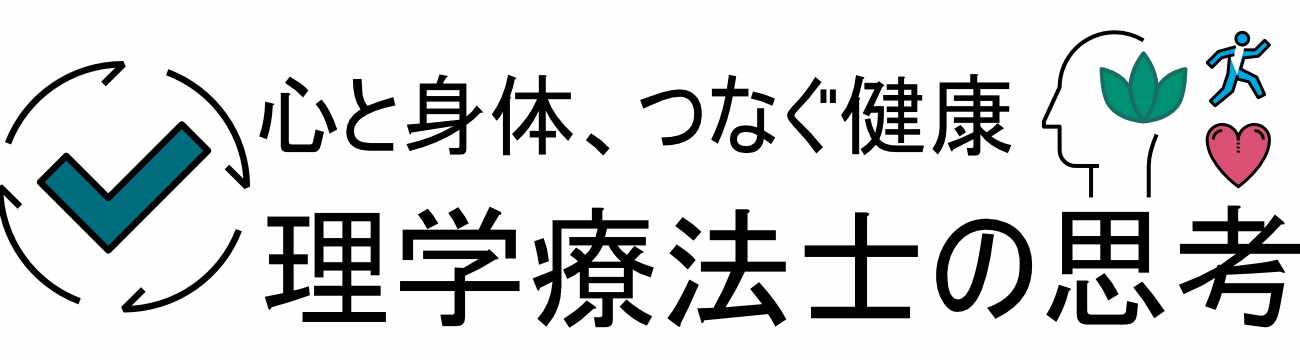こんばんは。
今日は一日休みでしたが、結局家から出ずに、読書や勉強に時間を使っていました。特に、近々開催予定の院内勉強会(疼痛がテーマ)の準備を進めていて、あっという間に時間が過ぎてしまいました。
その準備の中で、特に時間をかけて調べていたのが「下行性疼痛抑制系(かこうせいとうつうよくせいけい)」という、私たちの体が持つ痛みを抑える仕組みについてです。今回は、この勉強を通して学んだこと、考えたことを整理してみたいと思います。
臨床でのギモン:「痛みの反応」はなぜ人それぞれ?
理学療法士として日々患者さんと接していると、「痛みの感じ方や、アプローチへの反応は本当に人それぞれだな」と感じる場面が多くありませんか?
- ちょっとした介入や、特に痛みを意識していないアプローチで、驚くほど痛みが軽減する方
- 逆に、しっかりと評価し、原因と考えられる部位にアプローチしても、なかなか痛みが変わらない方
- 全く同じような症状に見えても、介入への反応が全く異なるケース
こうした経験は、理学療法士なら誰しもが持っているのではないでしょうか。この「反応の違い」は、疼痛治療の難しさであり、同時に私たちの腕の見せ所、そして探求しがいのある面白い分野でもあると感じています。患者さんの「楽になった!」という笑顔を引き出すために、私たち理学療法士は、痛みのメカニズムに関する知識を常にアップデートし、臨床に活かしていく必要があると強く感じます。
(今回の院内勉強会では、この辺りの最新知見から具体的なアプローチまでを、15分という短い時間でどこまで伝えられるか…というのが私の課題です!)
体が持つブレーキ役:「下行性疼痛抑制系」とは?
今回学んだ中で、この「痛みの反応の違い」を理解する上で非常に重要だと感じたのが、「下行性疼痛抑制系」という脳の働きです。
これは、簡単に言うと、私たちの脳が持っている「痛みを抑える(ブレーキをかける)システム」のことです。
基本的な仕組み(今回学んだ範囲での理解):
- 痛みなどの感覚情報は、末梢の神経から脊髄を通って脳へと伝わります(上行性)。
- 同時に、脳の中の特定の部位(特に中脳中心灰白質:PAGなどが重要とのこと)が活性化されると、そこから脊髄に向かって痛みを抑える信号が送られます(下行性)。
- この下行性の信号が、脊髄の後角という場所で、脳へ痛みを伝えようとする神経細胞の活動を抑制します。
- 結果として、脳へ伝わる痛みの信号量が減少し、痛みが和らぐ、と考えられているようです。
つまり、私たちが臨床で行う徒手療法(マッサージやモビライゼーションなど)や温熱療法といった介入が痛みを和らげる効果の一部は、これらの刺激が感覚受容器を介して脳に伝わり、この下行性疼痛抑制系を活性化させることで生じている可能性がある、ということになります。
(※別の講習会では、徒手療法によって結合組織の状態が変化し、動きやすさが改善すること自体も痛みの軽減に繋がる、という話も聞きました。痛みの改善には、神経系の働きだけでなく、組織自体の変化や運動制御(腹圧など)の改善といった多面的な視点が必要だと改めて感じます。)
脳に器質的な問題がない患者さんでは、こうした元々備わっている痛みの抑制システムが比較的働きやすく、介入による痛みの軽減効果も現れやすいのかもしれません。
なぜ慢性痛では効きにくい? 下行性疼痛抑制系の機能低下
一方で、臨床ではなかなか痛みが改善しない、特に慢性的な痛みを抱える患者さんもいらっしゃいます。なぜ、そのような方々では痛みの軽減効果が得られにくいのでしょうか?
今回学んだ資料によると、慢性疼痛患者さんでは、この下行性疼痛抑制系の働き自体が弱まっている(ブレーキが効きにくくなっている)可能性があるとのことです。
その背景として、以下のような点が指摘されていました。
- 脳の変化: 慢性的な痛みによって、脳の特定の部位(特に前頭前野など)に萎縮や灰白質の減少といった構造的な変化が生じることがある。
- 抑制機能の減弱: 下行性疼痛抑制系の機能低下や、DNIC(広汎性侵害抑制調節)と呼ばれる、体の他の部位への刺激によって痛みが和らぐ仕組みの働きが悪くなっている。
- 情動・報酬系の影響: 不安や抑うつといった情動の問題が、脳の報酬系(中脳辺縁系ドパミンシステムなど)の活動を低下させ、それが結果的に下行性疼痛抑制系の働きを弱めてしまう。
つまり、慢性疼痛の患者さんでは、単に痛みの信号が強いだけでなく、痛みを抑えるための脳のシステム自体がうまく機能しなくなっている可能性がある、というわけです。これは、介入効果が出にくい理由を考える上で、非常に重要な視点だと感じました。
痛みが取れにくい患者さんへのアプローチのヒント
では、下行性疼痛抑制系の働きが弱まっている可能性のある患者さんに対して、私たちはどのようなアプローチを考えられるでしょうか?
今回学んだ中でのヒントとしては、以下の2点が挙げられていました。
- 「快」刺激の活用:
- 意外かもしれませんが、「心地よい」と感じる刺激が痛みを和らげることがあるようです。例えば、好きな音楽を聴いたり、好きな写真を見たりすることでも痛みが軽減したという研究もあるとのこと。
- 臨床場面では、患者さんが不快に感じないような優しい触れ方を心がけたり、リラックスできる環境を整えたりすることが、間接的に痛みの抑制に繋がる可能性があるかもしれません。
- 運動療法(特に痛みのない部位へのアプローチ):
- 慢性的な痛みがある部位を直接動かすのが難しい場合でも、痛みがない他の部位を動かす運動療法が、結果的に痛みを和らげる効果を持つことがあるとのことでした。
- これは私自身も臨床で経験したことがありますが、「なぜ関係ない場所の運動で痛みが楽になるんだろう?」と不思議に思っていました。もしかすると、運動によって脳の様々な部位が活性化され、結果的に弱っていた下行性疼痛抑制系が賦活される、といったメカニズムが関わっているのかもしれません。(この辺りはもっと詳しく勉強したいです!)
まとめ:痛みの理解を深め、より良いアプローチへ
今回、「下行性疼痛抑制系」という視点から痛みのメカニズムを学んだことで、日々の臨床で感じていた「なぜ痛みの反応は人それぞれ違うのか?」という疑問に対して、一つの大きなヒントを得られたように思います。
特に、慢性的な痛みを抱える患者さんに対しては、単に痛む部位へのアプローチだけでなく、脳の機能(痛みを抑えるシステム)にも目を向け、快刺激や運動療法といったアプローチを検討することの重要性を再認識しました。
まだまだ勉強不足な点は多いですが、こうした知識を深め、実際の介入に結びつけていくことで、少しでも多くの患者さんの痛みを和らげ、笑顔を引き出せるような理学療法士になりたい。そう強く思いました。(まずは明日の勉強会、頑張ります!)