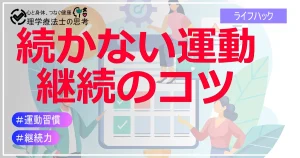はじめに:「運動しなきゃ…」と思いつつ、今日もソファから動けなかったあなたへ
「最近、明らかに運動不足で、体がなまっているのを感じる…」
「健康のために何か始めたいけれど、仕事が忙しくて時間も気力もない…」
「かつてはマラソンやジム通いをしていたのに、いつの間にか遠のいてしまった…」
このような悩みを抱えている方は、決して少なくないでしょう。
2018年当時、私自身もまさにその一人でした。
フルマラソンの大会を控えながらも、日々の忙しさの中で練習時間が確保できず、焦りを感じていました。
そんな時、ある医師でありながらトップレベルのアマチュアサイクリストでもある方の本を読み、その時間術と練習法に感銘を受けると同時に、自分の考え方を見直す大きなきっかけを得ました。
この記事では、当時の私の気づきと試行錯誤の経験を元に、特定のスポーツに限らず、忙しい現代人が運動習慣を身につけ、心身のコンディションを整えるための普遍的な3つのステップについて、2025年の視点から具体的にお伝えします。
ステップ1:「いきなり完璧」を目指さない – エリートの真似から学ぶべきこと
当時、私が読んだ本には、その医師の方の驚くべき一日が紹介されていました。
- 4時半起床・朝食
- 5時~7時:室内でのトレーニング
- その後、通勤、仕事、家族との団らんを経て、22時就寝
このようなストイックなスケジュールを見て、「すごい!」と感心すると同時に、「自分には到底真似できない…」と感じるのが正直なところでしょう。
また、その本では「強い人は月間1500~2000km走る」といった、トップレベルの練習量が紹介されていました。
ここで陥りがちなのが、「このくらいやらないと意味がないんだ」という完璧主義の罠です。
高すぎる目標は、行動へのハードルを上げ、「どうせできないなら、やらない方がマシ」という思考に繋がり、結局何も始められないという最悪の結果を招きます。
私たちが学ぶべきは、彼らの練習量やスケジュールそのものではなく、それを可能にしている「習慣化の仕組み」と「思考法」です。
まずは、「自分には自分のペースがある」と認め、いきなり完璧を目指さないことから始めましょう。
ステップ2:焦らず「土台」を作ることに集中する – LSDの考え方を応用する
ロードバイクの世界には「LSD(Long Slow Distance)」というトレーニング方法があります。
これは、文字通り「ゆっくり、長く」走ることで、毛細血管を発達させ、脂質代謝能力を高め、持久力の「土台(地足)」を作ることを目的とした練習です。
この「まずは高強度ではなく、低強度で継続できる土台を作る」という考え方は、あらゆる運動習慣の確立に応用できます。
- ウォーキングやジョギングなら: スピードを気にせず、おしゃべりできるくらいのペースで、心地よく感じられる時間歩いたり走ったりする。
- 筋力トレーニングなら: 重い重量を追い求めるのではなく、正しいフォームを意識しながら、軽い負荷で丁寧に行う。
- ヨガやストレッチなら: 無理にポーズを深めようとせず、自分の体の伸びを感じられる範囲で、呼吸を止めずに行う。
運動を始めたばかりの時期や、ブランクがある場合、最も重要なのは「高強度なトレーニングで自分を追い込む」ことではなく、「低強度でも良いから、継続して行うことで、運動を生活の一部として体に馴染ませる」ことです。
この土台作りを丁寧に行うことで、ケガのリスクを減らし、運動を楽しいと感じる心を育み、長期的な習慣化へと繋がっていきます。
ステップ3:「始める」ハードルを極限まで下げる – 続けられる環境をデザインする
運動を継続する上で、意外なほど大きな障壁となるのが、「運動を始めるまでの一手間」です。
- 「ウェアに着替えるのが面倒…」
- 「ジムに行くまでが遠い…」
- 「ロードバイクを外に出すのが億劫…」
これらの小さな「面倒くさい」が積み重なり、やる気を削いでしまいます。
そこで、「始めよう」と思ってから実際に行動に移すまでのハードルを、物理的・心理的に極限まで下げる工夫が重要になります。
- 環境を整える:
- ウェアや道具は前日に準備: 朝ランニングするなら、枕元にウェア一式を置いておく。
- 室内トレーニング環境の活用: 2018年当時の私が活用しようとしていたローラー台(室内で自転車を漕げる器具)のように、天候に左右されず、自宅ですぐに始められる環境を整える(エアロバイク、ヨガマット、トレーニングチューブなど)。
- 動線を工夫する: 帰宅したら必ず通る場所にトレーニングウェアを置いておくなど、自然と意識が向くようにする。
- 時間を確保する:
- 短時間でもOKと割り切る: 「30分やらなきゃ」ではなく、「まずは5分でもいいからやってみる」とハードルを下げる。
- スケジュールに組み込む: 他の予定と同じように、カレンダーに「運動」の時間をブロックしてしまう。
- 記録をつけて可視化する:
- 2019年の私も「距離を記録するようにする」と決意しましたが、走行距離や時間、実施した日などをアプリや手帳に記録することで、自分の頑張りが見える化され、モチベーション維持に繋がります。
考察:運動と栄養はセットで考える – 体が変われば心も変わる
2018年の記事の最後に、「運動と栄養は一緒に考えないとだめですね」とメモのように書いていましたが、これは非常に重要な視点です。
どんなに運動を頑張っても、食事がおろそかでは、体は十分に回復せず、疲労が蓄積し、パフォーマンスも向上しません。
特に、朝食を抜いたり、極端に食事量を減らしたりすると、体はエネルギー不足に陥り、かえって筋肉を分解してしまうこともあります。
まずは、「バランスの取れた食事を3食しっかり摂る」という基本を大切にしましょう。
運動という「アクセル」と、栄養・休養という「ブレーキ・メンテナンス」の両輪が揃って初めて、体は良い方向へと進み始めます。
まとめ:小さな一歩の積み重ねが、未来の自分を創る
かつて運動不足と焦りを感じていた私が、一冊の本から学んだこと。
それは、エリートの真似をすることではなく、その背後にある普遍的な原則を、自分のできる範囲で、自分に合った形で実践することの重要性でした。
- いきなり完璧を目指さず、小さな目標から始める。
- 強度よりも継続を重視し、まずは運動の「土台」を作る。
- 「始めるのが面倒」という障壁を、工夫して取り除く。
この3つのステップを意識するだけで、「運動しなきゃ」というプレッシャーは、「今日もちょっとやってみるか」という気軽な気持ちに変わっていくはずです。
そして、その小さな積み重ねが、気づいた時には大きな変化となり、より健康的で活力に満ちた毎日をもたらしてくれるでしょう。