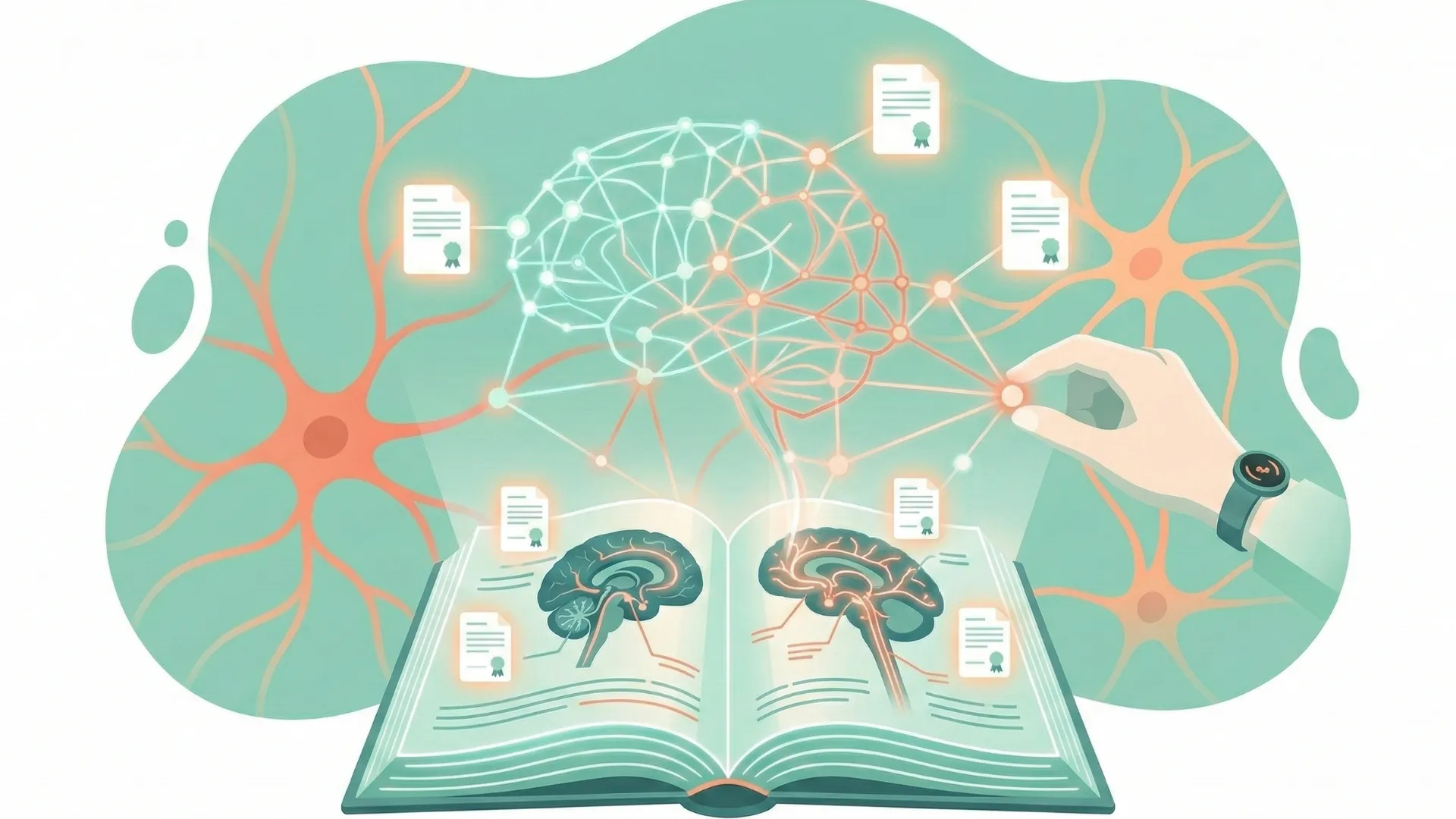「日々の業務に追われて、勉強する時間がない…」 「勉強したはずの知識が、臨床でうまく使えない…」
新人理学療法士さんや学生さんの中には、そんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。学校で膨大な知識を学び、国家試験を乗り越えても、臨床の現場では新たな壁にぶつかりますよね。
実は私も、かつては同じ悩みを抱える理学療法士の一人でした。日曜出勤でヘトヘトになった日、家に帰ってからも勉強しなきゃと焦るものの、なかなか机に向かう気力が起きない。そんな時、ふと「勉強は机の上でするもの、というのは思い込みかもしれない」と考えたのです。
それから私は、料理をしながら、ロードバイクのローラーを漕ぎながら、頭の中でその日に学んだ治療法について反芻する、いわゆる「ながら勉強」を始めました。
この記事では、そんな私の経験も踏まえ、日々の隙間時間を「臨床思考を深めるトレーニング」に変えるための具体的な方法と、その一例として私が学んだ「BiNI理論」の考え方について、理学療法士の新人さん、学生さんにも分かりやすく解説していきます。
この記事を読めば、あなたも明日からの臨床が少し違って見えるかもしれません。
臨床で結果を出すための「統合的」な視点とは?
理学療法士として患者さんを良くしていくためには、解剖学、運動学、生理学といった個別の知識はもちろん重要です。しかし、それらの知識をただ暗記しているだけでは、目の前の患者さんが抱える複雑な問題は解決できません。
Point(結論): 臨床で本当に大切なのは、断片的な知識を繋ぎ合わせ、一人の人間をシステムとして捉える「統合的な思考」です。
Reason(理由): なぜなら、人の身体は、様々な要素が相互に影響し合って機能しているからです。例えば、足首の硬さが膝や股関節、ひいては体幹の動きにまで影響を及ぼすように、身体は一つのパーツの集合体ではなく、すべてが連動した一つのシステムとして成り立っています。
Example(具体例): 私が学んでいる「BiNI理論」も、まさにこの統合的な視点を重視するアプローチの一つです。
日本で提唱されたBiNI Approachは、力学的な法則性の中で、身体がどのように自己組織化していくかを考えるアプローチです。その結果、感覚入力を用いて協調的な運動を再生成することを目指します。
用語解説:BiNI理論(インテグレイティブオーガナイゼーション:統合的自己組織化) 非常に難しく聞こえますが、簡単に言うと「私たちの身体は、重力や床からの力といった外部からの情報(感覚入力)を受け取り、それを脳や神経が処理して、最適な動き(運動出力)を無意識のうちに作り出している」という考え方です。
この理論では、単に筋力をつけたり、関節の可動域を広げたりするだけでなく、「どうすればより良い感覚を身体に入力できるか」という点を非常に重要視します。
Point(結論の再提示): このように、一つの理論を例にとっても、身体を多角的に、そして統合的に捉える視点が、臨床での問題解決の糸口になることが分かります。
【論文解説でわかったこと】BiNI理論から学ぶ臨床思考の3つのヒント
元の記事で私がメモしていた「BiNI理論」「原理原則」「オシレーションの効果」。これらは一見するとバラバラの知識に見えます。しかし、これらを統合的な視点で繋ぎ合わせることで、臨床で使える「思考の武器」になります。ここでは、その思考プロセスを3つのヒントとして解説します。
ヒント1:身体を「システム」として捉える – なぜアライメントが重要なのか?
新人や学生時代、「アライメントを評価しなさい」と口酸っぱく言われた経験はありませんか?なぜ、あれほどまでにアライメントが重要なのでしょうか。
BiNI理論の原理原則の一つに、「アライメントや組織の硬度も感覚情報を変化させるため重要である」というものがあります。
感覚入力の「質」が変わる
これは、骨や関節の配列(アライメント)が崩れていると、身体が受け取る感覚情報の「質」が変わってしまう、ということを意味します。例えば、猫背で頭が前方に出ている姿勢を考えてみましょう。
- 重力に対する身体の応答が変わる: 頭の重さを支えるために、首や背中の筋肉は常に過剰な緊張を強いられます。これは「頑張りすぎ」という感覚情報を脳に送り続けることになります。
- 足裏からの感覚が変わる: 重心がつま先側に偏るため、足裏の接地感も変化します。本来感じるべき踵からの安定した感覚入力が減少し、不安定な感覚情報が脳に送られます。
このような質の悪い感覚情報が入力され続けると、脳はそれを「普通の状態」だと勘違いしてしまい、結果として非効率な運動パターンが定着してしまうのです。
治療効果の持続性に関わる
さらに、「硬度が高い結合組織の性質を変化させると治療効果の持続性を高める」とも言われています。
アライメント不良は、特定の筋肉や筋膜、靭帯といった結合組織に持続的なストレスをかけ、それらを硬くしてしまいます。この「硬さ」自体も、異常な感覚情報として脳に入力されます。
いくらマッサージやストレッチで一時的に筋肉をほぐしても、根本的なアライメントが改善されなければ、結合組織はまたすぐに硬くなってしまいます。だからこそ、アライメントを評価し、その根本原因にアプローチして組織の硬さを変化させることが、治療効果を持続させる上で不可欠なのです。
ヒント2:オシレーションを「目的志向」で使う – ただ揺らすだけからの脱却
次に、私が学んだ「オシレーション」の効果について考えてみましょう。オシレーションとは、身体をリズミカルに揺らす手技のことです。
元のメモには、効果として以下の4点が書かれていました。
- リラックス効果、血流改善、筋緊張緩和
- 関節液の対流、結合組織の硬度低下
- 摩擦熱による層間の滑り、結合組織の硬度低下
- 良好な感覚入力、腹内側系の活性化
これらの知識をただ暗記するだけでは、「なんとなく身体に良さそう」で終わってしまいます。大切なのは、「どの効果を狙って」「目の前の患者さんにどう使うのか」という目的志向の思考です。
効果を臨床場面と結びつける
例えば、全身がガチガチに緊張している患者さんがいるとします。この方に対して、あなたはどの効果を一番に狙いますか?
まずは①のリラックス効果や筋緊張緩和を狙うのが定石でしょう。交感神経の興奮を抑え、まずは安心して身体を預けてもらうことが治療の第一歩になります。
次に、特定の関節の動きが悪い場合。例えば股関節の詰まり感があるなら、②の関節液の対流や結合組織の硬度低下を狙います。股関節周辺をターゲットに、少し周波数を変えながら揺らすことで、関節包や周辺の筋膜にアプローチできるかもしれません。
さらに、寝返りや起き上がりといった基本的な動作の改善を目指すなら、④の良好な感覚入力や腹内側系の活性化を狙います。足部から左右交互にリズミカルな揺れを加えることで、歩行に近い感覚を脳に入力し、体幹の安定性に関わる神経系(腹内側系)を賦活することができる、と仮説を立てられます。
ヒント3:「ながら勉強」を「臨床思考トレーニング」に変える技術
さて、冒頭でお話しした「ながら勉強」に話を戻しましょう。忙しい毎日の中で、この時間をいかにして質の高い学びに変えるか。その鍵は「知識をネットワーク化する」ことです。
元の記事で私はこう書いていました。
脳内のネットワークを生成し、情報と情報をリンクし、不足情報を補いリンクすることでネットワークを構築していきます。このリンクを強固なものにすることで、臨床で役立つし、何より試験ですぐに知識を引き出せると思います。
これはまさに、断片的な知識を統合的な思考へと昇華させるプロセスです。
ステップ1:今日の臨床での「なぜ?」を持ち帰る
まずは、その日の臨床で感じた小さな疑問や、「うまくいった/いかなかった」経験を一つだけ持ち帰りましょう。
- 「なぜ、Aさんの起き上がりはスムーズなのに、Bさんはあんなに大変そうなんだろう?」
- 「今日試したアプローチで、なぜ腰の痛みが少し楽になったんだろう?」
この「なぜ?」が、思考トレーニングの出発点になります。
ステップ2:隙間時間で知識をインプット&リンクさせる
通勤中の電車の中、料理をしながら、お風呂に入りながら。そんな隙間時間に、持ち帰った「なぜ?」について考えます。
例えば、「Bさんの起き上がりが大変なのはなぜ?」という疑問。
- (知識の想起)「起き上がりには、体幹の回旋と屈曲が必要だよな…」
- (情報とのリンク)「Bさんは体幹がガチガチに固まっていた。オシレーションのリラックス効果が使えるかもしれない。」
- (新たな疑問/不足情報)「そもそも、なぜBさんの体幹は固いんだ?アライメントはどうなってる?普段どんな姿勢で過ごしているんだろう?」
- (知識のリンク)「アライメントが崩れて、特定の筋肉が常に緊張してるからかも。それが悪い感覚入力になって、さらに動きにくくなってる悪循環?」
このように、一つの疑問から、手持ちの知識(アライメント、オシレーション、感覚入力など)を次々に連想し、繋ぎ合わせていきます。分からなければ、その場でスマホで調べるのも良いでしょう。
ステップ3:簡単な言葉でアウトプットする
最後に、考えたことを簡単な言葉でアウトプットします。これは、頭の中のネットワークを強固にするために非常に重要です。
- メモに書き出す: 「Bさんの起き上がり困難→体幹の固さ→アライメント不良による持続的な筋緊張?→明日は座位アライメントをチェックしてみよう」
- 声に出して説明してみる(独り言): 「つまり、Bさんの問題は、ただの筋力低下じゃなくて、姿勢の崩れからくる悪い感覚入力が、動きそのものを邪魔してるってことか…」
この「インプット→リンク→アウトプット」のサイクルを繰り返すことで、「ながら時間」は単なる知識の確認ではなく、臨床に直結する思考力を鍛えるための貴重なトレーニング時間へと変わるのです。
【明日からの臨床で試せる!】思考の第一歩
理論や方法を知っても、行動に移さなければ何も変わりません。最後に、この記事を読んでくださったあなたが、明日からすぐに試せるアクションプランを提案します。
アクション1:担当患者さん一人の「感覚入力」を意識して観察する
まずは、担当している患者さんの中から一人だけを選んでみてください。そして、その方の身体に「今、どんな感覚が入力されているか」を意識して観察してみましょう。
- 座っている時の坐骨: 左右均等に体重が乗っていますか?それともどちらかに偏っていますか?
- 立っている時の足の裏: 踵とつま先、どちらに重心がありますか?足の指は地面を掴めているでしょうか?
- ベッドに寝ている時の身体の接地感: 背中や骨盤は、ベッドにリラックスして沈んでいますか?それともどこか浮いている感じがしますか?
普段何気なく見ているアライメントを、「感覚入力の入り口」という視点で捉え直すだけで、新たな気づきがあるはずです。
アクション2:「なぜ?」を一つだけメモして帰る
業務が終わったら、今日の臨床で感じた「なぜ?」を一つだけ、メモ帳やスマートフォンのメモアプリに書き出してみましょう。どんなに些細なことでも構いません。
「なぜ、この方はいつも右側に寄りかかって座るんだろう?」 「なぜ、歩くときに腕を全く振らないんだろう?」
この小さな疑問が、あなたの臨床思考を深めるための最高の燃料になります。そして、帰り道や家での隙間時間に、その「なぜ?」について少しだけ考えてみてください。答えが出なくても構いません。考えること自体がトレーニングなのです。
まとめ
今回は、新人理学療法士・学生さんに向けて、「ながら勉強」を「臨床思考トレーニング」に変えるためのヒントを、BiNI理論を例にご紹介しました。
- 臨床では、知識を繋ぎ合わせる「統合的な思考」が重要。
- アライメントや組織の硬さは、身体に入る「感覚情報の質」を左右し、治療効果の持続性にも関わる。
- オシレーションなどの手技は、複数の効果を理解し、「目的」を持って使うことで質が高まる。
- 日々の「なぜ?」を持ち帰り、「インプット→リンク→アウトプット」のサイクルを回すことで、隙間時間が最高の学習時間になる。
臨床に出てすぐは、覚えることも多く、目の前の業務に追われてしまいがちです。しかし、そんな中でもほんの少し視点を変え、日々の臨床と学習を結びつける意識を持つだけで、成長のスピードは格段に上がります。
この記事が、あなたの臨床の一助となれば幸いです。
参考文献
この記事を作成するにあたり、BiNI Approachの考え方を参考にしました。より深く学びたい方は、関連書籍や公式サイトをご参照ください。
健康・医学関連情報の注意喚起
本記事は、理学療法における学習法と臨床思考に関する情報提供を目的としたものであり、特定の医学的アドバイスを提供するものではありません。 特定の疾患などの診断や治療については、必ず医療従事者にご相談ください。