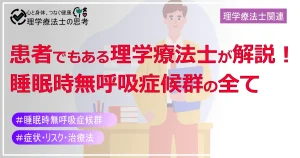はじめに:「いびきが大きいだけ」では済まされない?睡眠時無呼吸症候群の真実
皆さん、こんにちは。理学療法士のPTケイです。
「夜、いびきがうるさいって言われるんだよね…」 「昼間にどうしようもなく眠くなることがある…」
こんな経験はありませんか? もしかしたら、それは単なる疲れや体質ではなく、「睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome: SAS)」のサインかもしれません。
睡眠時無呼吸症候群は、文字通り睡眠中に呼吸が止まったり、浅くなったりすることを繰り返す病気です。
この状態が続くと、体への酸素供給が不足し、日中の活動だけでなく、全身の健康に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
私自身、睡眠時無呼吸症候群であり、マウスピースをつけて寝ています。今回は、理学療法士の視点も交えながら、睡眠時無呼吸症候群の症状、リスク、診断、治療法、そして私たち理学療法士がどのように関わることができるのかについて、詳しく解説していきます。
1. 睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは? 基本的な知識をおさらい
睡眠時無呼吸症候群は、睡眠1時間あたりに10秒以上の呼吸停止(無呼吸)や呼吸の著しい低下(低呼吸)が5回以上見られる状態を指します。
この無呼吸・低呼吸により、血液中の酸素濃度が低下し、睡眠の質が著しく悪化します。
SASの主なタイプ:
- 閉塞性睡眠時無呼吸症候群 (Obstructive Sleep Apnea: OSA): 最も一般的なタイプで、喉の奥(上気道)が物理的に狭くなったり塞がったりすることで起こります。肥満による首周りの脂肪沈着、扁桃肥大、舌根沈下、顎が小さいことなどが原因となります。
- 中枢性睡眠時無呼吸症候群 (Central Sleep Apnea: CSA): 脳の呼吸中枢の異常により、呼吸指令そのものが出なくなるタイプです。心不全や脳血管障害などが原因となることがあります。
- 混合性睡眠時無呼吸症候群: 閉塞性と中枢性の両方の特徴を持つタイプです。
2. もしかしてSAS?見逃せない主な症状
SASの症状は多岐にわたりますが、代表的なものとしては以下のようなものが挙げられます。
- 大きないびきと無呼吸: 家族やパートナーから指摘されることが多い代表的な症状です。いびきが突然止まり、しばらくして大きな呼吸と共に再開するような場合は要注意です。
- 日中の過度な眠気: 睡眠の質が著しく低下するため、日中に強い眠気を感じ、仕事や学業、運転などに支障をきたすことがあります。
- 起床時の頭痛・倦怠感: 睡眠中の低酸素状態や睡眠不足により、朝起きた時に頭痛やスッキリしない感じ、体が重いといった症状が出ることがあります。
- 集中力・記憶力の低下: 慢性的な睡眠不足と低酸素状態は、脳機能に影響を与え、日中の集中力や記憶力の低下を招きます。
- 夜間頻尿: 睡眠中の無呼吸は、利尿ホルモンの分泌異常を引き起こし、夜中に何度もトイレに起きる原因となることがあります。
- その他: 性欲減退、抑うつ気分、イライラ感、寝汗なども見られることがあります。
私も当てはまる症状が多いですが、マウスピースの治療を行っている今でも、日中の過度な眠気と夜間頻尿(今は1回くらいですが以前は0回だったので気になる)は生活の質に影響が大きく、自己管理の難しさを実感しています。
3. SASを放置するリスク:全身に及ぶ深刻な影響
SASを治療せずに放置すると、様々な健康問題を引き起こすリスクが高まります。
- 高血圧: 睡眠中の低酸素状態や交感神経の亢進により、血圧が上昇しやすくなります。SASは高血圧の独立した危険因子とされています。
- 心血管疾患: 心房細動、不整脈、狭心症、心筋梗塞、心不全などのリスクを高めます。睡眠中の無呼吸は心臓に大きな負担をかけるためです。
- 脳血管障害: 脳梗塞や脳出血のリスクを高めることが知られています。
- 2型糖尿病: インスリン抵抗性(インスリンの効きが悪くなる状態)を増悪させ、糖尿病の発症や悪化に関与します。
- 認知機能障害・認知症: 長期的な低酸素状態や睡眠の質の低下は、認知機能の低下を招き、将来的には認知症のリスクを高める可能性も指摘されています。
- 精神疾患: うつ病や不安障害との関連も報告されています。睡眠障害自体が精神状態に影響を与えることに加え、SASによる日中のQOL低下も要因と考えられます。
- 交通事故のリスク増加: 日中の強い眠気により、居眠り運転による交通事故のリスクが大幅に高まります。
これらの合併症は、生命に関わる重大なものも含まれており、SASの早期発見・早期治療の重要性を示しています。
4. SASの診断:まずは専門医へ相談を
SASが疑われる場合、まずは睡眠専門医や呼吸器内科、耳鼻咽喉科などを受診しましょう。
- 問診・診察: 症状や生活習慣、既往歴などを詳しく聴取し、喉や鼻の状態を診察します。
- 簡易検査(スクリーニング検査): 自宅で指先にセンサーを装着して睡眠中の酸素飽和度や脈拍を測定したり、鼻にカニューラを装着して呼吸の状態を記録したりする検査です。これにより、SASの可能性を評価します。
- 終夜睡眠ポリグラフ検査 (PSG検査): SAS診断のゴールドスタンダードです。通常、1泊入院して行われ、脳波、眼球運動、筋電図、心電図、呼吸状態(鼻・口の気流、胸腹部の動き)、血液中の酸素飽和度、いびきの音などを詳細に記録します。この検査により、無呼吸・低呼吸の回数や種類、睡眠の深さや質などを正確に評価できます。
5. SASの治療法:ライフスタイル改善から専門治療まで
SASの治療法は、重症度や原因、患者さんの状態に応じて選択されます。
- 生活習慣の改善:
- 減量: 肥満はOSAの最大の原因の一つであり、減量することで気道の閉塞が改善し、SASが軽快することがあります。理学療法士も運動指導や食事に関するアドバイスで関与できます。
- 禁煙: 喫煙は上気道の炎症を引き起こし、SASを悪化させる可能性があります。
- アルコール制限: 特に就寝前の飲酒は、筋弛緩作用により上気道を狭窄させやすく、無呼吸を悪化させます。
- 睡眠衛生の改善: 規則正しい睡眠時間、適切な寝具の選択、寝室環境の整備なども重要です。
- 体位療法: 横向きで寝ることで、舌根沈下を防ぎ、いびきや無呼吸を軽減できる場合があります。抱き枕や専用のベストなどが用いられることもあります。
- CPAP療法 (Continuous Positive Airway Pressure:経鼻的持続陽圧呼吸療法):
- 中等症から重症のOSAに対する第一選択治療です。
- 寝ている間に鼻に装着したマスクから空気を送り込み、上気道に陽圧をかけることで、気道の閉塞を防ぎます。
- 適切に使用すれば、いびきや無呼吸が劇的に改善し、日中の眠気や合併症のリスクも軽減されます。
- 理学療法士は、CPAP導入後の患者さんに対して、マスクのフィッティング調整のアドバイスや、CPAP使用下での呼吸リハビリテーション(必要な場合)などに関わることがあります。
- 口腔内装置(マウスピース):
- 軽症から中等症のOSAや、CPAP療法が適応とならない、あるいは継続困難な場合に用いられます。
- 下顎を前方に移動させることで、気道を広げる効果があります。歯科医によって作製されます。
- 外科的治療:
- 扁桃肥大、アデノイド、鼻中隔弯曲症、大きな口蓋垂など、明らかな解剖学的な異常が原因で気道狭窄が起きている場合に検討されることがあります。
- 例:口蓋垂軟口蓋咽頭形成術(UPPP)、レーザー口蓋垂軟口蓋形成術(LAUP)、鼻中隔矯正術など。
- ただし、手術の適応は慎重に判断され、効果や合併症のリスクも考慮する必要があります。手術療法の有効性に関するエビデンスの質と量は、他の治療法と比較してまだ十分とは言えない側面もあります。
6. 私の体験談と「痩せていてもSASになる」という事実
実は、この記事を書いている私自身も、かつて睡眠時無呼吸症候群と診断された経験があります。当時、私は特に太っているわけではなく、むしろ痩せ型でした。「SAS=太っている人の病気」という先入観があったため、診断された時は非常に驚きました。
しかし、日中の耐え難い眠気や集中力の低下に悩まされ、専門医を受診した結果、SASと診断されました。私の場合は、顎が比較的小さいことが一因ではないかとのことでした。診断後はマウスピース療法を開始し、症状は劇的に改善しました。
この経験から、「体型に関わらず、誰でもSASになる可能性がある」ということを身をもって知りました。顎の形態、扁桃腺の大きさ、鼻の通り具合など、様々な要因がSASの発症に関与します。
7. 理学療法士としてSASにどう関わるか?
理学療法士は、SASの直接的な治療を行うわけではありませんが、以下のような点で患者さんをサポートできる可能性があります。
- リスク因子の評価と生活習慣指導: 肥満、不良姿勢、呼吸パターンなどを評価し、運動療法や呼吸訓練、姿勢矯正、体重管理のためのアドバイスを行います。
- CPAP療法や口腔内装置の適応支援: マスクのフィッティングや装着感に関する相談、装置使用に伴う身体的な不快感の軽減、呼吸パターンの最適化などを支援します。
- 合併症の予防と管理: 高血圧や心疾患、糖尿病などの合併症を持つ患者さんに対して、それぞれの疾患に応じた運動療法や生活指導を行います。
- 呼吸リハビリテーション: 呼吸筋の強化や効率的な呼吸パターンの獲得を促すことで、睡眠中の呼吸状態の改善に寄与できる可能性があります(特に特定の病態において)。
- 患者教育と啓発: SASに関する正しい知識を提供し、早期受診や治療継続の重要性を啓発します。
まとめ:気になる症状があれば、まずは専門医へ相談を
睡眠時無呼吸症候群は、単なる「いびき」や「眠気」の問題ではなく、放置すると全身の健康に深刻な影響を及ぼす可能性のある疾患です。しかし、幸いなことに、適切な診断と治療によって、その症状は大きく改善し、合併症のリスクを軽減することができます。
「もしかして自分も…?」と感じる症状があれば、決して自己判断せず、まずは専門の医療機関を受診し、相談することをお勧めします。そして、私たち理学療法士も、患者さんのQOL向上と健康維持のために、多角的な視点からサポートできることがあるということを、心に留めておきたいと思います。