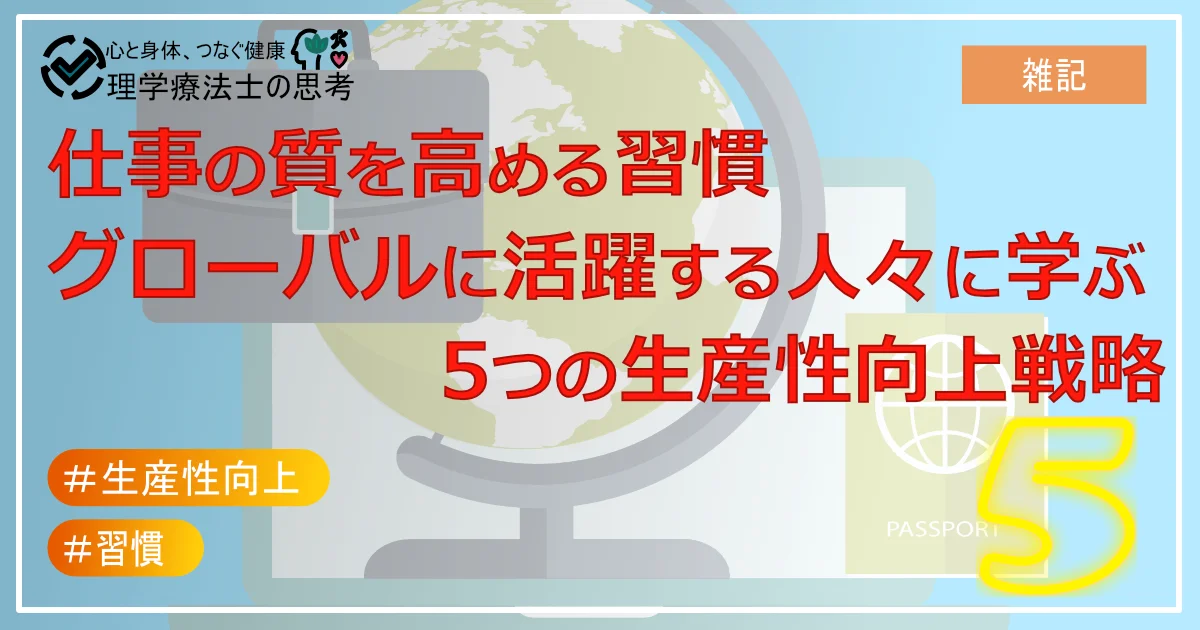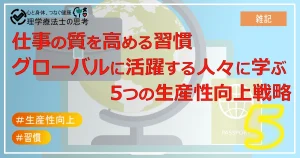はじめに:なぜ今、「質の高い仕事の習慣」に学ぶのか?
日々の業務に追われ、なかなか自分の時間や学びの時間を確保できない…そんな悩みを抱えている方は少なくないでしょう。2018年、私はあるビジネス誌の記事をきっかけに、「グローバルに活躍する人々は、どのように時間とタスクを管理し、高い生産性を維持しているのか?」というテーマに関心を持ち、自身の働き方を見直す機会を得ました。
あれから数年が経過し、働き方も多様化しましたが、高い成果を出し続ける人々に共通する普遍的な習慣や考え方は、依然として私たちにとって大きなヒントを与えてくれます。この記事では、当時注目した「グローバルに活躍する人々の5つの習慣」を、現在の視点からアップデートし、日々の仕事や生活の質を高めるための具体的な戦略として掘り下げていきます。
グローバルエリートに学ぶ5つの生産性向上戦略
1. 睡眠:最高のパフォーマンスを引き出すための最重要戦略
- 当時のポイント:「7時間以上確保せよ!」
- 6時間未満の睡眠は、日中のパフォーマンスに深刻な影響を与える。理学療法士のような対人援助職においては、コミュニケーションの質を保つためにも睡眠は不可欠。
- 現在の視点と深掘り:
- 睡眠の質への注目: 単に時間を確保するだけでなく、睡眠の質(深い睡眠、レム睡眠のサイクル)を高めることの重要性がより強調されています。寝る前のカフェイン摂取を避ける、寝室の環境を整える(温度、湿度、光、音)、規則正しい就寝・起床時間を心がけるなどが挙げられます。
- 睡眠負債の概念: 日々のわずかな睡眠不足が蓄積し、心身の不調やパフォーマンス低下を招く「睡眠負債」。これを意識し、週末の寝だめではなく、日々の睡眠時間を安定させることが重要です。
- 日中の仮眠の活用: 午後の眠気対策として、15~20分程度の短い仮眠(パワーナップ)が、集中力回復に効果的であるという研究も増えています。
2. タスク管理:思考を整理し、行動を促す「書き出す」力
- 当時のポイント:「仕事内容はメモに書き出す」
- PC・スマホのみでのTODO管理は不十分。手書きで書き出すことが大切。
- 現在の視点と深掘り:
- デジタルとアナログのハイブリッド活用: デジタルツール(タスク管理アプリ、カレンダーアプリ)の利便性と、手書きの思考整理効果を組み合わせるのが現代的です。例えば、大きなプロジェクトやアイデア出しは手書きで、日々の細かなタスク管理はデジタルで、といった使い分けが考えられます。
- 「書き出す」ことの認知科学的メリット: 手を動かして書く行為は、脳を活性化させ、記憶の定着や思考の整理を助けると言われています(ジャーナリング効果)。頭の中のモヤモヤを書き出すことで、客観的にタスクを把握し、優先順位をつけやすくなります。
- GTD(Getting Things Done)メソッドの応用: 頭の中にある「気になること」を全て信頼できるシステム(手帳やアプリ)に書き出し、脳のメモリを解放して目の前のタスクに集中するというGTDの考え方は、今も有効です。
3. 時間管理:パーキンソンの法則に打ち勝つ「制限時間」の効果
- 当時のポイント:「仕事に制限時間を設けよ」
- 人は与えられた時間いっぱいに仕事を伸ばす傾向がある(パーキンソンの法則)。残業を避けるため、タスクに優先順位をつけ、制限時間を設けて取り組む。
- 現在の視点と深掘り:
- タイムブロッキングの実践: 1日や週のスケジュールを時間帯で区切り、各ブロックに特定のタスクを割り当てる手法。これにより、「いつ、何をやるか」が明確になり、集中しやすくなります。
- ポモドーロ・テクニックの活用: 例えば「25分作業+5分休憩」を1セットとし、これを繰り返すことで集中力を持続させ、疲労を軽減します。
- 「重要だが緊急ではない」タスクへの時間投資: 緊急性の高い業務に追われがちですが、長期的な目標達成や自己成長に繋がる「重要だが緊急ではない」タスク(例:新しいスキルの学習、人脈作り、健康増進活動)にも意識的に時間を割り当てることが、将来の生産性を高めます。
4. 情報収集:成長を止めないための継続的インプット
- 当時のポイント:「常にインプットを怠らず読書を!」
- 高年収と読書量は比例する傾向。グローバルエリートの多くは月2冊以上読書。
- 現在の視点と深掘り:
- 読書習慣の多様化: 紙の書籍だけでなく、電子書籍、オーディオブックなど、ライフスタイルに合わせてインプット手段を選べるようになりました。通勤時間や家事をしながらの「ながら聴き」も有効です。
- 質の高い情報源の選択: インターネット上には情報が溢れていますが、その質は玉石混交です。信頼できるニュースサイト、業界の専門誌、質の高い論文、専門家のブログやポッドキャストなど、自分にとって価値のある情報源を見極める能力が重要です。
- インプットとアウトプットのサイクル: 読書や情報収集で得た知識を、誰かに話したり、文章にまとめたり、実践したりすることで、より深く理解し、記憶に定着させることができます。
5. 時間帯別得意分野の把握:自分のバイオリズムを活かす
- 当時のポイント:「午前・午後で仕事内容を変えよ!」
- 自分にとって集中しやすい時間帯や向いている仕事がある。大変な仕事は午前中に集中して行う方が効率的。
- 現在の視点と深掘り:
- クロノタイプの理解と活用: 人には朝型、夜型といった「クロノタイプ」があり、最も生産性が高まる時間帯が異なります。自分のクロノタイプを把握し、集中力が必要なタスク(分析、企画、文章作成など)や、逆に創造性が求められるタスク、単純作業などを適切な時間帯に配置することで、効率を最大化できます。
- エネルギーマネジメントの視点: 時間だけでなく、自分自身のエネルギーレベル(肉体的、精神的、感情的)を意識し、高いエネルギーレベルの時間帯に最も重要なタスクを割り当てるという考え方です。適度な休憩や気分転換もエネルギー維持には不可欠です。
- 「残業で頑張る」からの脱却: 困難な仕事や集中力を要する仕事を夜遅くまで持ち越すのは、効率も質も低下しがちです。日中の生産性を高め、定時で質の高い仕事を終えることを目指す方が、長期的には持続可能です。
考察:これらの習慣がもたらす「好循環」
これらの習慣は、単に個々のタスクを効率化するだけでなく、「仕事の質と効率の向上 → 自己投資の時間の創出 → さらなるスキルアップとパフォーマンス向上」という好循環を生み出すためのものです。
仕事の準備や段取りに時間をかけることは、一見遠回りに見えるかもしれません。しかし、それによって日中の業務がスムーズに進み、結果として残業が減り、自己啓発や健康維持、家族との時間など、より本質的な活動に時間を充てられるようになります。この好循環こそが、継続的に高い成果を出し続ける秘訣なのではないでしょうか。
まとめ:普遍的な仕事の習慣を日常に取り入れ、自己成長を加速させる
今回挙げた5つの習慣は、特別な才能や環境がなくても、意識と工夫次第で誰でも取り入れることができるものです。
- 質の高い睡眠を確保する
- タスクを書き出して整理する
- 仕事に制限時間を設けて集中する
- 継続的に読書や情報収集を行う
- 自分のパフォーマンスが高い時間帯を把握し活用する
これらの習慣を一つでも多く実践することで、日々の仕事の効率が上がり、時間に追われる感覚から解放され、より充実した毎日を送るための一歩となるはずです。2018年当時の私も、これらの習慣を意識することで、X線画像の読影や専門知識の学習、そしてこのブログを書くための時間を少しずつ確保できるようになりました。
皆さんも、ぜひこれらの仕事術を参考に、ご自身の働き方を見直し、自己成長を加速させてみてはいかがでしょうか。