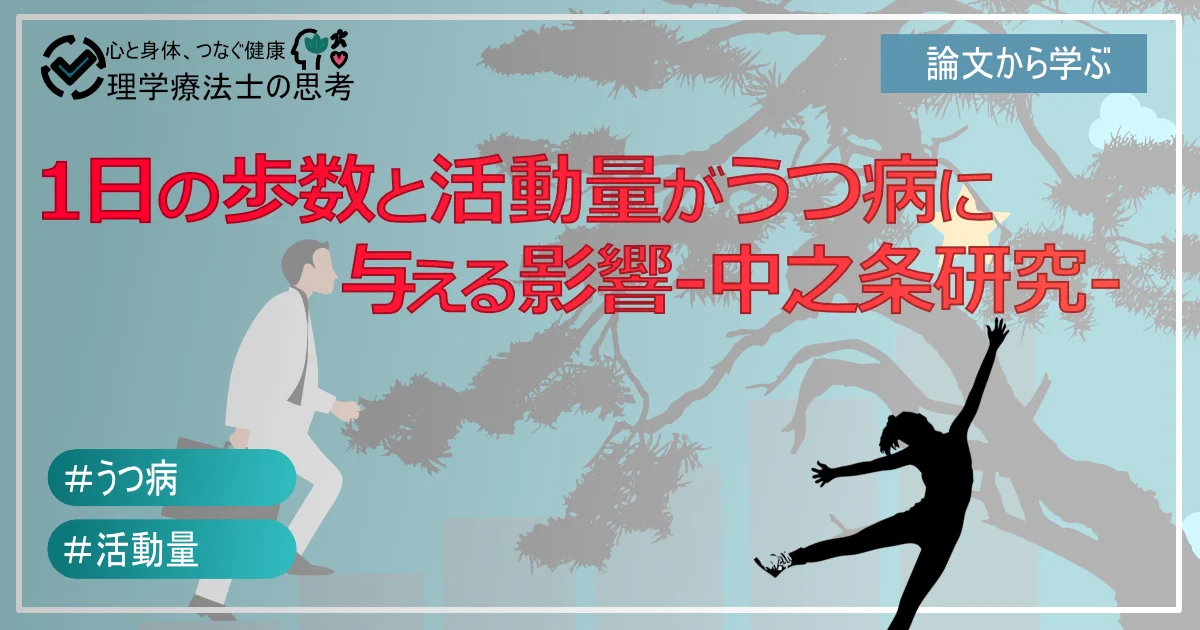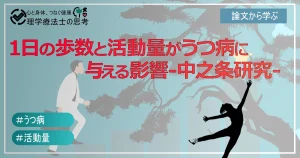皆さん、こんにちは!PTケイです。
年齢を重ねるとともに、「最近、気分が沈みがち…」「何をするにも億劫…」と感じることが増えていませんか?もしかしたら、それは「年のせい」だけではなく、「運動不足」が関係しているかもしれません。
近年の研究で、運動不足とうつ病には深いつながりがあることがわかってきています。今回は、そんな「運動不足」と「うつ病」の関係について、これまでの研究でわかっていることと、最新の研究で新たにわかったことを、どこよりも詳しく解説していきます!
運動とうつ病の関係:これまでの研究でわかっていること
実は、運動とうつ病の関係については、これまでにもたくさんの研究が行われてきました。

- 身体活動とうつ病は逆の関係!: 多くの研究で、身体活動量が多い人ほど、うつ病になりにくいことが示されています。ただし、身体活動の測定方法(自己申告アンケート、歩数計、加速度計など)や、研究デザイン(横断研究、縦断研究など)は様々です。
- 運動はうつ病の治療にも効果あり!: ウォーキングやジョギングなどの運動は、うつ病の症状を軽くする効果があることがわかっています。
- 客観的な測定はまだ少ない: 身体活動とメンタルヘルスに関する研究は増えていますが、身体活動を客観的に測定し、うつ病との関連を長期間にわたって追跡した研究は、まだ少ないのが現状です。
つまり、運動不足を解消し、積極的に体を動かすことが、うつ病の予防や改善につながる可能性があると考えられてきたのです。
ちょっと復習:運動不足がうつ病のリスクを高める
2024年 ステファニー・ルー氏らの研究グループは、中高年者を対象に、身体活動および座位時間の軌跡とうつ病との長期的な関連を調査しました。
この研究では、オーストラリアの約1200人の中高年者を対象に、
- 約11年間にわたって、3回、身体活動量、座っている時間、うつ病の症状を調査
- 時間の経過とともに、これらの要素がどのように変化するか(軌跡)を分析
という方法で、運動不足とうつ病の関係をより詳しく調べました。
研究でわかったこと:運動不足はうつ病のリスクを高め、座りすぎは…?
この最新研究から、
- 身体活動量が増えると、うつ病の症状が改善する傾向がある
- 具体的には、身体活動量の増加の軌跡(時間の経過とともに身体活動量が増えていくパターン)が、うつ病症状の減少の軌跡(時間の経過とともにうつ病症状が減っていくパターン)と関連していました。つまり、積極的に体を動かす習慣を身につけ、それを維持することで、うつ病の症状が改善する可能性があるということです。
- 座っている時間の変化は、うつ病の症状の変化とは関係がない
- この研究では、座っている時間が増えたり減ったりすることと、うつ病の症状が変化することとの間には、明確な関連は見られませんでした。つまり、座っている時間が増えたからといって、必ずしもうつ病の症状が悪化するわけではない、ということです。
- ただし、過去の研究では「長時間の座位」が、身体活動量とは関係なく、うつ病のリスクを高める可能性も指摘されているため、この点については今後も注意して研究結果を見ていく必要があります。今回の研究では、「座っている時間の変化」に着目しているため、「ずっと座りっぱなし」の生活がどう影響するかは、別の研究で調べる必要があります。
つまり、これまでの研究結果を裏付けるように、運動不足を解消し、積極的に体を動かすことが、うつ病の予防や改善につながる可能性が改めて示されたのです。
今回の研究紹介:日本人高齢者でも同様の結果が!
ここで、2021年に発表された、稲田修司氏らによる日本人高齢者を対象とした研究についても触れておきましょう。これは、中之条研究といい非常に有名です。

この研究では、65歳から85歳の男女191人を対象に、
- 加速度計という機器を腰につけてもらい、1日の歩数と中強度以上の運動時間(MVPA)を客観的に測定しました。
- MVPAとは、早歩きや、それ以上の強度の運動(3METs以上)のこと。息がはずみ、汗をかく程度の運動を指します。
- このデータを、5年間、毎年記録し続けました。
- 軌跡分析という特別な分析方法を用いて、5年間の歩数とMVPAの変化パターンを、いくつかのグループに分類しました。
- 1日の歩数:6つのグループに分類
- 例:ずっと歩数が多いグループ、徐々に歩数が減るグループ、ずっと歩数が少ないグループなど
- 中強度以上の運動時間(MVPA):5つのグループに分類
- 例:ずっと運動時間が多いグループ、徐々に運動時間が減るグループ、ずっと運動時間が少ないグループなど
- 1日の歩数:6つのグループに分類
- 5年後の調査で、うつ病の症状を評価するアンケート(HADS-D)を実施し、各グループのうつ状態を比較しました。
その結果、
- 中強度以上の運動時間(MVPA)が少ないグループは、5年後の調査でうつ状態になりやすいことがわかりました。
- 特に、
- 最初からMVPAが少なく、5年間ずっと少ないままだったグループ(表のグループ1)
- 最初は中程度のMVPAを保っていたけれど、途中で減ってしまったグループ(表に記載なし) で、うつ状態になりやすい傾向が顕著でした。
- 特に、
- 1日の歩数が少ないグループも、うつ状態との関連が見られました。
これらの結果から、日本人高齢者においても、
- 中強度以上の運動(MVPA)を継続すること
- 日々の歩数を増やすこと
の両方が、心の健康を維持するために重要である可能性が示唆されます。
ただし、この研究では年齢の影響も考慮する必要があり、今後のさらなる研究が待たれます。
今日からできる!運動不足解消のためのヒント
「運動が大切」なのはわかったけど、何から始めればいいの?
そんな方のために、今回は運動不足解消のためのヒントをいくつかご紹介します!
まずは日常生活を見直してみましょう!
- 「ちょこっと運動」を意識する:
- 「エスカレーターやエレベーターではなく、なるべく階段を使う」
- 「テレビを見ながら足踏みをする」
- 「いつもより少し遠回りして歩く」
- 「家事の合間にストレッチをする」 など、日常生活の中で少しでも体を動かす工夫をしてみましょう。
- 座りっぱなしの時間を減らす:
- 「30分に1回は立ち上がる」
- 「テレビを見ながらストレッチをする」
- 「スタンディングデスクを使う」 など、座りっぱなしの時間を減らす工夫をしてみましょう。
慣れてきたら、運動の習慣化にチャレンジ!
- ウォーキングから始める:
- ウォーキングは、手軽に始められる運動の代表格です。
- 最初は短い時間から始めて、徐々に時間や距離を延ばしていきましょう。
- 歩数計やアプリを使って、毎日の歩数を記録するのもモチベーションアップにつながります。
- 好きな運動を見つける:
- ジョギング、水泳、ヨガ、ダンス、サイクリング、筋トレ…など、運動の種類はたくさんあります。
- 「楽しい!」と思える運動を見つけて、継続することが大切です。
- 地域のスポーツクラブやサークルに参加してみるのも良いでしょう。
- 無理は禁物!:
- 体調が悪い時や、気分が乗らない時は、無理せず休みましょう。
- 運動中に痛みを感じたら、すぐに中止しましょう。
まとめ:運動で、心も体も健やかに!
今回の最新研究、そして過去の研究結果から、運動不足を解消することが、うつ病の予防や改善に非常に大きな効果を持つ可能性が示されています。
「最近、ちょっと気分が落ち込みがち…」 「運動不足が気になる…」
そんな方は、ぜひ今日から、体を動かす習慣を始めてみてください。
運動で、心も体も健やかな毎日を目指しましょう!
健康・医学関連情報の注意喚起:
本記事は、うつ病と身体活動に関する一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の医学的アドバイスを提供するものではありません。 うつ病の診断や治療については、必ず医療従事者にご相談ください。