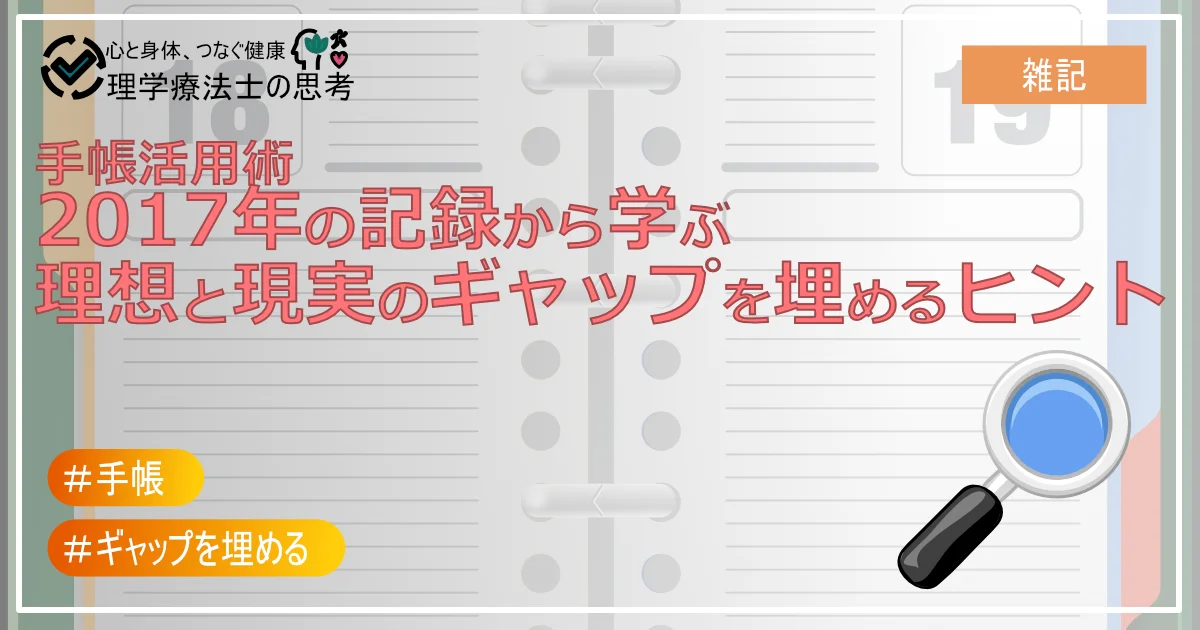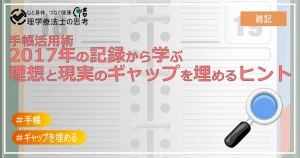メリークリスマス。年の瀬が迫るこの時期は、新しい年に向けて手帳を新調したり、使い方を見直したりする方も多いのではないでしょうか。
ふと、2017年のクリスマスに書いた手帳に関する記事を読み返してみました。当時は新しい手帳(ジブン手帳)を使い始めて9日目。バーティカル式の24時間軸の使いやすさや、予定の可視化に手応えを感じつつも、計画通りにいかない現実、特に睡眠時間や勉強時間の確保に苦労していた様子が記録されていました。
この記事では、当時の私の試行錯誤を振り返りながら、手帳を単なるスケジュール管理ツールとしてだけでなく、自己理解を深め、理想の習慣を築くための「実験ノート」として活用するためのヒントを探ります。
1. 「見える化」が生む気づき:バーティカル手帳の威力
当時の私が感じていた「書き込みスペースの多さ」「一週間の流れの把握しやすさ」は、バーティカル式手帳の大きな利点です。24時間軸で自分の行動を記録していくと、予定だけでなく、実際に何にどれだけ時間を使っているかが克明になります。
- 時間のブラックボックスを発見: 「特にやる予定のないことで時間をつぶしてしまう」という当時の悩みは、多くの人に共通するのではないでしょうか。記録することで、こうした無意識の「浪費時間」が可視化され、改善の第一歩となります。
- 生活リズムのパターン認識: 忘年会シーズンで夜型に移行しがちだった当時の私のように、自分の生活リズムがどのような要因(イベント、気分、体調など)で変動するのか、そのパターンが見えてきます。理想(朝型)と現実(夜型への移行しやすさ)のギャップを客観的に把握できます。
- 振り返りによる学び: 記録は、未来の計画のためだけでなく、過去の行動とその結果を分析するための貴重なデータとなります。「なぜ予定通りいかなかったのか?」「何がうまくいったのか?」を問いかけることで、より現実的で効果的な計画へと繋げられます。
2. 計画倒れは「データ」である:理想と現実の調整法
「割と予定通りいかないことが多いですね。これは予想通りです。」当時の私のこの一文は、計画と実行の間にギャップがあることへのある種の諦めと、それでも計画を立てる意義を感じている複雑な心境を表しています。
計画通りにいかないことは、失敗ではありません。それは「今の自分にとっては、この計画は負荷が高すぎた」「予期せぬ出来事へのバッファーが足りなかった」といった貴重なフィードバックです。
- 睡眠時間のコントロール: 「早く寝て起きる時間を固定する方が有意義」という理想と、「朝になるとモチベーションが下がる」現実。このギャップに対して、「血圧の問題?」「受動的な行動?」と原因を探ろうとしています。手帳の記録と体調・気分のメモを組み合わせることで、自分なりの最適な睡眠パターンや、それを妨げる要因(例:寝る前のスマホ時間、カフェイン摂取)への対策が見えてきます。
- 「受動的な行動」への対策: なぜ意図しない行動で時間を使ってしまうのか?手帳に「やりたいことリスト」や「暇な時にやることリスト」を書いておき、受動的な時間に陥りそうになったらそれを見る、という仕組みを作るのも有効です。
3. タスクの分解と時間ブロック:勉強と運動から学ぶ実行のコツ
当時の記録では、勉強と運動の計画実行において対照的な結果が見られました。
- 勉強(複雑なタスク)の課題: 「インプット→パワーポイント→ブログ」という流れが1日では負担が大きく、実行に移せない。これは、タスクが大きすぎ、成果が見えにくいことが原因と考えられます。
- 対策: 当時の私が思いついていた「ポモドーロテクニック(例:25分集中して5分休憩)などで時間と内容を区切り、その中でできる範囲でアウトプットする」という方法は非常に有効です。大きな目標を、具体的な行動レベル(例:「〇〇の文献を1つ読む」「スライドを3枚作る」)まで分解し、短い時間枠で実行可能な形にすることが重要です。
- 運動(習慣化したいタスク)の成功: 「あらかじめ予定をブロックし、時間を確保しておいたため、スムーズに行動に移せた。」これは「いつ、何をするか」を事前に決定し、他の予定と同様に扱うことの有効性を示しています。
- 対策: 勉強や早起きなど、習慣化したい他の行動についても、「いつ(特定の時間)」「どこで(特定の場所)」「何を(具体的な行動)」を明確に予定に組み込む(時間ブロック)ことで、実行のハードルを下げることができます。「考える時間」を減らし、「実行する」モードにスムーズに移行しやすくなります。
4. システムに委ね、実行に集中する (GTD的思考)
「自分が今やるべきことをNOZBEと手帳というシステムに預け、実行していくだけ。」これはGTD(Getting Things Done)の考え方にも通じます。頭の中にある「やること」「気になること」をすべて信頼できるシステム(手帳、アプリなど)に書き出し、整理することで、脳のメモリを解放し、目の前のタスクに集中できるようにします。
- 計画疲れを防ぐ: 完璧な計画を立てることに時間を使いすぎるのではなく、まずはシステムにタスクを移し、優先順位に従って着手する。計画は実行しながら修正していく、という柔軟な姿勢が大切です。
- 習慣化への道: システムを参照し、実行するというサイクルを繰り返すことで、徐々に行動が自動化され、習慣として定着していきます。
まとめ:手帳は自己成長の羅針盤
2017年の私の手帳との格闘は、多くの人が経験するであろう時間管理や目標達成の難しさを映し出しています。しかし、その試行錯誤の記録自体が、自己理解を深め、より良い習慣を築くための羅針盤となり得ます。
手帳を単なる予定帳としてだけでなく、
- 自分の時間の使い方やパターンを「見える化」するツール
- 計画と現実のギャップから学ぶ「実験ノート」
- 目標達成のための具体的な行動を促す「実行プランナー」
- 頭の中を整理し、行動に集中するための「外部脳システム」
として活用してみてはいかがでしょうか。当時の私がそうであったように、試行錯誤を繰り返しながら、自分に合った手帳との付き合い方を見つけていくプロセスそのものが、自己成長の糧となるはずです。
この記事が、皆さんの手帳活用と目標達成の一助となれば幸いです。