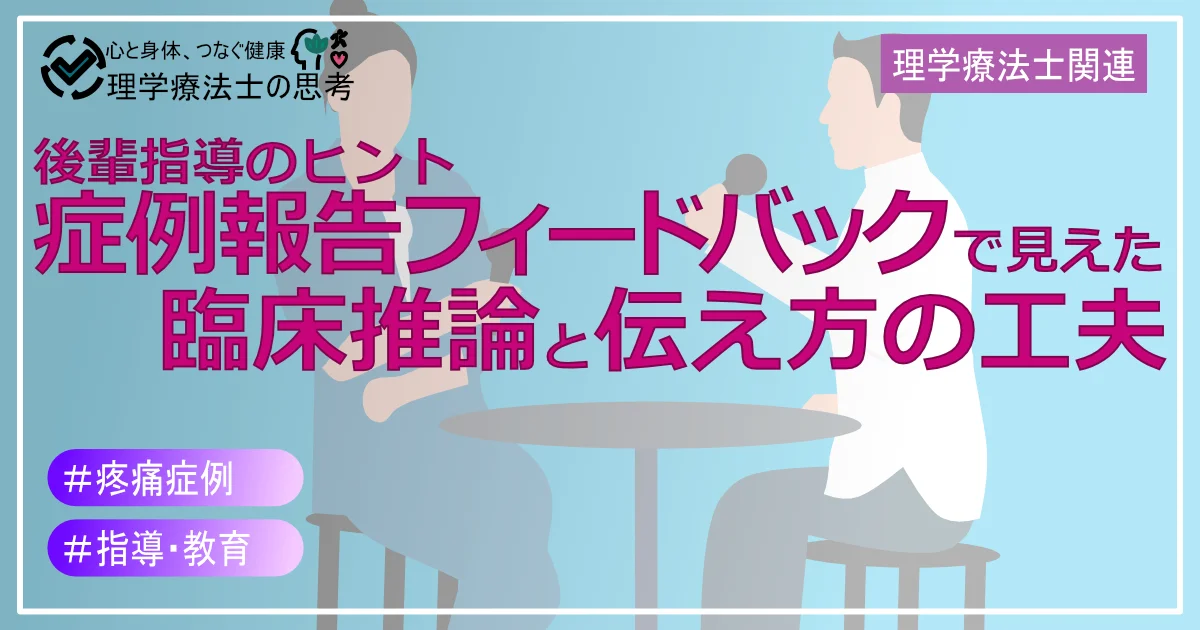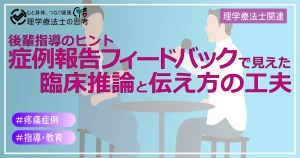こんばんは。PTケイです。
今日も一日お疲れ様でした。帰りは少し遅くなってしまいましたが、明日が休みだと思うと、心に余裕が生まれますね。(明日の予定も考えつつ…まずは今日の振り返りを!)
さて、今日は後輩の症例報告(PT勉強会用)に対するフィードバックを行いました。昨日フィードバックしたスタッフとは別の方で、これで担当している2人分の初回フィードバックが終わったことになります。
一度に複数名の指導を行うのは、時間的にも精神的にも負荷がかかりますが、今回は事前に後輩がある程度考察を進め、発表のイメージを持ってくれていたため、修正内容の検討自体は比較的スムーズに進みました。その分、より深いレベルでの考察や、効果的な伝え方について考える時間を持つことができたように感じます。
今回は、そのフィードバックのプロセスと、特に「疼痛のアセスメント(評価と解釈)」について、具体的な事例を通して考えたこと、指導で工夫した点を共有したいと思います。後輩指導や症例検討に関わる皆さんの、何かのヒントになれば幸いです。
ケーススタディ:大腿骨転子部骨折後の膝痛、どう考える?
今回フィードバックを行ったのは、大腿骨転子部骨折の患者さんの症例報告でした。
この症例は、手術前に約2週間、直達牽引(骨に直接ピンを刺して引っ張る治療)を受けていたという背景があります。(当初は手術ができない可能性もあったためですが、最終的に手術可能となったケースです。)
術後、リハビリを進める中で、患側(左)の膝関節に著しい屈曲制限が見られ、さらに膝関節の遠位外側から膝蓋骨(お皿)の上あたりにかけて痛みを訴えられていました。
この「膝の痛み」に対して、後輩はどのように考え、アプローチしたのか? そして、私はどのようにフィードバックを行ったのか? そのプロセスを、疼痛の原因として考えられる要因を整理しながら見ていきましょう。
後輩と共に、この膝痛の原因として考えられる主な要因を以下のように整理しました。
- 不動期間による結合組織の伸張性低下:
- 手術前の約2週間の直達牽引、そして術後の安静期間により、膝関節周囲の筋肉、靭帯、関節包といった結合組織が動かされない状態が続きました。これにより、組織の柔軟性が失われ、伸張性が低下。膝を曲げようとした際に、硬くなった組織が引き伸ばされて痛みが生じている可能性が考えられます。
- 不動期間による痛みの感受性増大(中枢感作の可能性):
- 長期間の不動や持続する痛みは、単に組織を硬くするだけでなく、痛みを感じる神経系の感度を高めてしまう(感作)可能性があります。特に、痛みの信号を脳に伝える神経回路が過敏になり、通常では痛みを感じないような刺激(例:軽く触れる、少し動かす)に対しても痛みを感じやすくなっている状態(中枢感作)も考慮に入れる必要があります。
- 代償的なアライメントと筋の過負荷:
- 元々、この患者さんには膝が外側に曲がる変形(膝外反OA)があったことに加え、大腿骨転子部骨折の影響で股関節を外側に捻る動き(外旋)が制限されていました。これをかばうように、無意識のうちに股関節が内側に捻れた状態(内旋位)で動作を行う傾向が見られました。この代償的なアライメント(姿勢・動き)によって、太ももの外側の筋肉(大腿筋膜張筋など)に過剰な負担(overuse)がかかり、筋肉が硬くなり、痛みを引き起こしている可能性も考えられます。
- アライメント異常によるメカニカルストレス:
- 膝外反という元々のアライメント異常がある状態で、歩行などの荷重がかかると、膝関節の外側に過剰な力学的ストレス(メカニカルストレス)が集中しやすくなります。これが直接的な痛みの原因となっている可能性も否定できません。
このように、一つの「膝の痛み」という現象に対しても、複数の要因が複雑に絡み合っている可能性を考え、多角的に評価・解釈していくことが重要になります。
指導のジレンマと工夫:「教える」と「引き出す」のバランス
これらの要因についてアセスメントを進める中で、指導者として難しさを感じたのは、「どこまで具体的に教えるか」と「本人の思考をどこまで引き出すか」のバランスです。
- 教えすぎの弊害: あまりに私が修正を加えすぎてしまうと、それはもう「私の発表」になってしまい、後輩自身の学びや達成感が薄れてしまいます。
- 引き出すことの重要性: 本人の言葉で考え、考察し、表現するプロセスこそが、最も成長に繋がるはずです。
しかし、今回はまだ考察が浅い部分も見受けられたため、ある程度の方向性を示す必要も感じました。そこで、以下のような点を意識してフィードバックを行いました。
- 思考の「型」を示す: 上記の①~④のような視点(組織の問題、神経系の問題、アライメント・代償動作の問題、力学的ストレスの問題)を提示し、多角的に原因を探るための「考え方の枠組み」を示すようにしました。
- アウトプットの機会を作る: 一方的に説明するだけでなく、「今の説明を聞いて、〇〇さんはどう考えますか?」「この部分を、ご自身の言葉で説明してみてください」といった形で、途中で本人にアウトプットしてもらう場面を意図的に作りました。
- 次のアクションを明確にする: フィードバック内容をただ聞くだけでなく、「今の話を元に、ご自身でスライドのこの部分を修正してみてください」「この点について、もう少し調べてみましょう」と、具体的な次のアクションに繋がるように促し、メモを取ってもらうようにしました。
指導とは本当に難しいものですが、画一的な方法があるわけではなく、相手の理解度や状況、そして伝えたい内容に合わせて、様々なアプローチ(引き出し)を使い分けていく経験そのものが、指導者としての成長に繋がるのだと改めて感じました。知識はもちろん重要ですが、その知識を相手に合わせて応用し、効果的に伝える「技術」は、やはり経験を通して磨かれていくものなのでしょう。
まとめ:構造化された思考と、相手に合わせた指導を
今回は、症例報告のフィードバックを通して、疼痛のアセスメントにおける多角的な視点の重要性と、後輩指導における「教える」と「引き出す」のバランスの難しさ、そしてその工夫について考えてみました。
複雑な臨床問題を解決するためには、情報を整理し、構造化して考える力(臨床推論能力)が不可欠です。そして、その力を後輩に伝えていくためには、一方的な知識伝達ではなく、相手の思考を促し、自ら気づきを得られるような関わり方を工夫していく必要があるのだと思います。
これからも、一つ一つの指導の機会を大切にし、自分自身も学び続けながら、より良い関わり方ができるよう努めていきたいと思います。