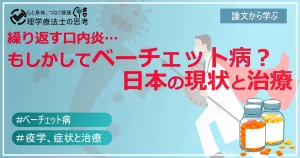「また口内炎ができた…」「目の充血が治らない…」 そんな繰り返す症状に、悩まされていませんか? もしかしたら、それは「ベーチェット病」という病気のサインかもしれません。
日本では約2万人の方が罹患していると言われるベーチェット病ですが、近年、その症状の現れ方が変わってきていることが指摘されています。
私自身、ベーチェット病と診断されていますが、ベーチェット病という病気は複雑で、どういう疾患なのか理解が難しかったので、知識を整理するために論文を読みました。
今回は、2019年に発表された論文をもとに、ベーチェット病とはどんな病気なのか、日本の現状はどうなっているのか、そして最新の治療法について、詳しく解説していきます。
研究紹介
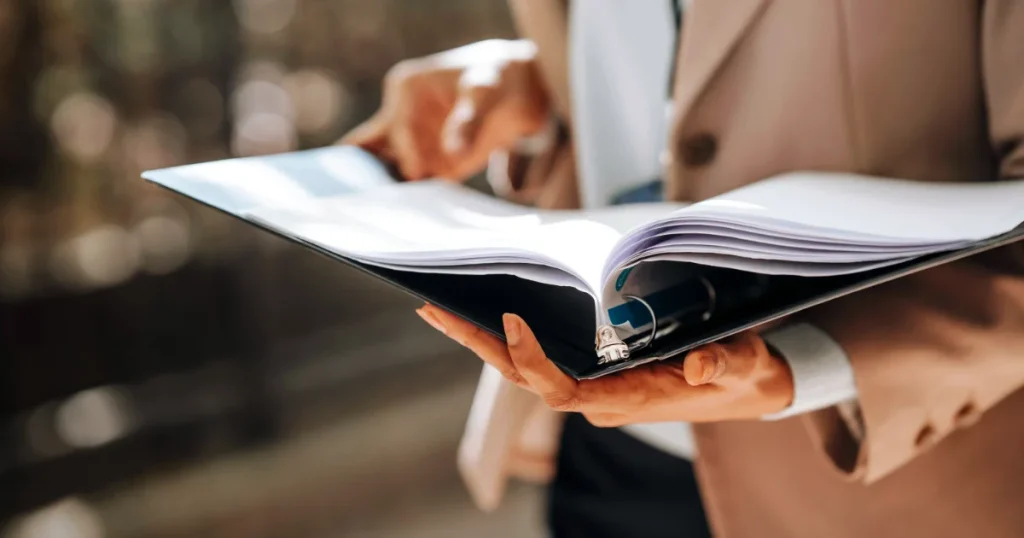
2019年、日本のキリノ ヨウヘイ氏とナカジマ ヒデアキ氏は、日本におけるベーチェット病(BD)の臨床的・遺伝的側面についてのレビュー論文を発表しました。その結果、過去20年間で日本人BD患者の表現型が変化しており(完全型・HLA-B51陽性患者の減少、腸管型の増加)、この変化は未解明の環境要因に関連する可能性があり、また、抗TNF-α抗体による治療は有効であるものの、特に特殊型BDに対するエビデンスは限定的であることなどを報告しました。
- レビュー論文:過去の研究をまとめて分析した論文のこと。
- 表現型:病気の症状の現れ方のこと。
- HLA-B51:ベーチェット病の発症に関わる遺伝子の型のひとつ。
- 抗TNF-α抗体:炎症を引き起こす物質の働きを抑える薬。
ベーチェット病ってどんな病気?~多彩な症状とその診断~
ベーチェット病は、全身の様々な場所に、繰り返し炎症が起こる原因不明の病気です。 まるで体のあちこちに火事が起こるようなイメージかもしれません。
日本では、厚生労働省が定める診断基準に基づいて診断されます。
診断の手がかりとなる主な症状は以下の4つです。
- 口腔粘膜の再発性アフタ性潰瘍: ほとんどの患者さんで見られる、最も特徴的な症状です。痛みを伴う口内炎が、繰り返しできます。
- 皮膚症状:
- 結節性紅斑(けっせつせいこうはん)様皮疹:主にすねにできる、痛みを伴う赤いしこり。
- 毛嚢炎(もうのうえん)様皮疹:ニキビのようなできもの。
- 皮下の血栓性静脈炎:皮膚の下の静脈に血栓ができ、赤く腫れる。
- 眼症状:
- ぶどう膜炎:目の内部(ぶどう膜)に炎症が起こり、視力低下やかすみ目、目の痛みなどを引き起こす。重症化すると失明に至ることも。
- 網膜血管炎など、目の様々な部分に炎症が起こりうる。
- 外陰部潰瘍: 性器やその周りに、口内炎のような潰瘍ができる。
これらの主な症状のうち、3つ以上が現れるか、特定の組み合わせが見られるとベーチェット病と診断されます。
さらに、ベーチェット病では、以下のような副症状が現れることもあります。
- 関節炎: 膝や足首などの関節が腫れて痛む。
- 精巣上体炎(副睾丸炎): 男性の精巣の隣にある臓器に炎症が起こり、腫れて痛む。
- 血管病変: 動脈や静脈に炎症が起こり、動脈瘤(血管のこぶ)や血栓(血の塊)ができることがある。
- 神経症状(神経ベーチェット病): 脳や脊髄に炎症が起こり、頭痛、発熱、麻痺、意識障害などを引き起こす。
- 消化器症状(腸管ベーチェット病): 腸に潰瘍ができ、腹痛、下痢、下血などを引き起こす。
これらの血管、神経、消化器系の症状は「特殊型」と呼ばれ、重症化しやすい傾向があります。
ベーチェット病診断の難しさ
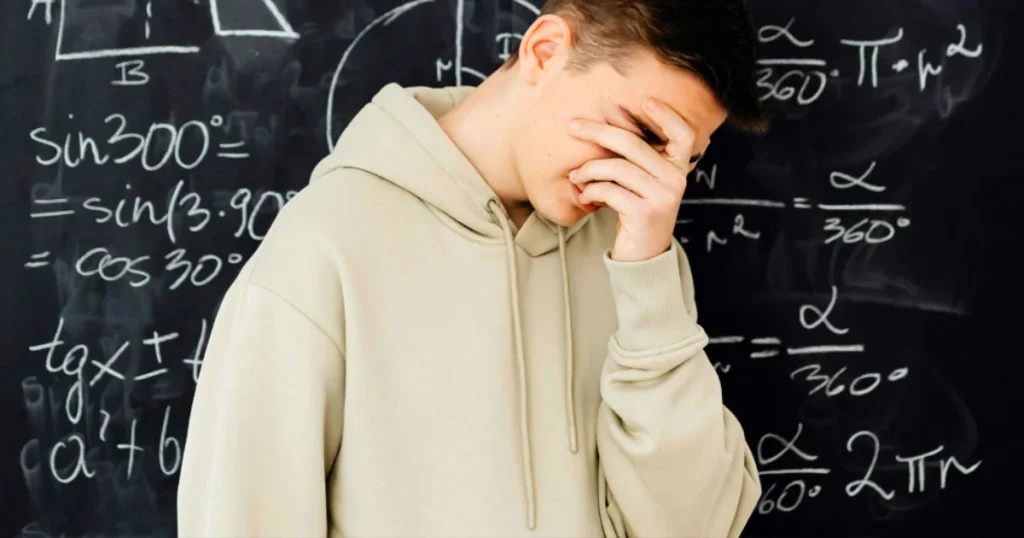
ベーチェット病の診断が難しい理由の一つは、これらの症状が一度に現れるとは限らないことです。 口内炎が何年も前からあった人が、後になって目の症状や腸の症状を発症する、というケースも少なくありません。 また、症状が一時的に良くなったり(寛解)、悪くなったり(再燃)を繰り返すのも特徴です。
日本のベーチェット病、どう変わってきてる?~疫学と症状の変化~
ベーチェット病は、トルコなど、かつてシルクロードが通っていた地域に多い病気として知られています。
日本では、10万人あたり約16人の方が罹患しており、厚生労働省の統計(2014年)によると、約2万人の方が医療費助成を受けています。
男女差は全体的にはありませんが、症状別に見ると、関節炎や陰部潰瘍は女性に、目の症状や神経症状は男性に多い傾向があります。
近年、日本のベーチェット病には、症状の現れ方(表現型)に変化が見られています。
- 主要な症状が全て揃う「完全型」や、特定の遺伝子(HLA-B51)を持つ患者さんの割合が減少。
- 一方で、腸に症状が出る「腸管型」の患者さんの割合が増加。
この変化の原因はまだはっきりしていませんが、日本への移民流入は少ないことから、遺伝的な変化よりも、食生活や生活環境の変化といった、環境要因が影響しているのではないか、と考えられています。
なぜベーチェット病になるの?~遺伝と環境の複雑な関係~
ベーチェット病のはっきりとした原因は、まだわかっていません。
しかし、発症には遺伝的な要因と環境要因の両方が複雑に関わっていると考えられています。
遺伝要因
- HLA-B51: ベーチェット病と最も強く関連する遺伝子の型として知られています。しかし、健康な日本人でも約15%はこの型を持っており、逆にベーチェット病患者さんの約30%はこの型を持っていません。そのため、HLA-B51を持っているからといって必ず発症するわけではなく、診断の補助的な情報にとどまります。
- その他の遺伝子: 近年のゲノムワイド関連解析(GWAS)という研究手法により、HLA-B51以外にも、HLA-A26、IL10、IL23R、ERAP1、STAT4など、多くの遺伝子がベーチェット病の発症しやすさに関わっていることがわかってきました。
- GWAS:ゲノム(全遺伝情報)を網羅的に調べ、病気と関連する遺伝子の特徴を見つける研究方法。
- ERAP1:細胞の中で、免疫に関わる目印(ペプチド)の長さを調節する酵素。HLAとの相互作用が病気の発症に関わると考えられています。
- 他の病気との関連: これらの遺伝子の中には、強直性脊椎炎、乾癬、クローン病といった他の炎症性疾患の発症に関わるものも含まれており、これらの病気とベーチェット病は、遺伝的に似た部分があると考えられています。
環境要因
- 感染症: 虫歯や歯周病の原因菌である「レンサ球菌」などの細菌や、ウイルスへの感染が、発症の引き金になる可能性が指摘されています。
- その他: 喫煙(特に神経症状との関連)、歯科治療、皮膚への刺激(ケガ、鍼治療など)なども、症状を悪化させる要因となる可能性があります。
ベーチェット病は、これらの遺伝的ななりやすさに、何らかの環境要因が加わることで発症すると考えられています。 また、免疫系の異常な反応(自己炎症)も、病気の発症や悪化に関わっていることがわかってきています。
ベーチェット病の治療はどうするの?~最新の治療戦略~
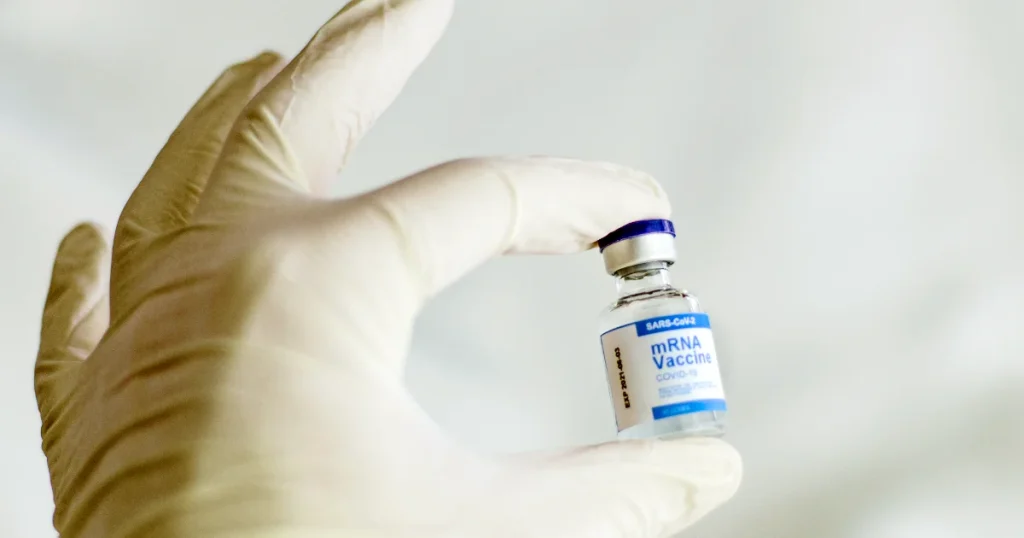
ベーチェット病の治療は、症状の種類や重症度に合わせて行われます。残念ながら、根本的に治す治療法はまだありませんが、炎症を抑え、症状をコントロールし、再発を防ぐことを目指します。
基本的な治療
- ステロイド薬: 炎症を強力に抑える薬。点眼薬、軟膏、内服薬、点滴など、症状に応じて使い分けられます。
- コルヒチン: 口内炎や皮膚症状、関節炎などに効果があります。痛風発作の予防にも使われる薬です。
- 非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs): 関節炎などの痛みを和らげます。
免疫抑制薬
症状が重い場合や、ステロイドだけではコントロールが難しい場合に用いられます。
- アザチオプリン、シクロスポリン、メトトレキサートなど: 免疫系の働きを全体的に抑えることで、炎症を鎮めます。
生物学的製剤(抗TNF-α抗体)
近年、ベーチェット病の治療は大きく進歩しました。その立役者となったのが、「生物学的製剤」と呼ばれる新しいタイプの薬です。 特に、炎症を引き起こす中心的な物質である「TNF-α」の働きをピンポイントで抑える「抗TNF-α抗体」は、従来の治療では効果が不十分だった、難治性の眼症状や、特殊型(神経、血管、腸管)ベーチェット病に対して、高い効果を発揮し、治療成績を大きく改善させました。
- インフリキシマブ(レミケード®)
- アダリムマブ(ヒュミラ®)
これらの薬は、日本でもベーチェット病の治療薬として承認されています。
その他の新しい治療薬
- アプレミラスト(オテズラ®): 口内炎に対して有効性が示されており、乾癬の治療薬としても使われています。
- 抗IL-17抗体、JAK阻害剤など: 乾癬や関節リウマチの治療薬ですが、ベーチェット病との遺伝的な関連性から、ベーチェット病への効果も期待され、研究が進められています。
治療における課題
抗TNF-α抗体の登場により、ベーチェット病の治療は大きく進歩しましたが、まだ課題も残っています。 特に、神経、血管、腸管などの「特殊型」ベーチェット病に対しては、抗TNF-α抗体の有効性を裏付ける質の高い研究(大規模な臨床試験など)がまだ少ないのが現状です。
もしや?と思ったら…早期発見・早期治療のために

ベーチェット病は、症状が多彩で診断が難しい病気ですが、早期に診断し、適切な治療を開始することが、症状の悪化や合併症を防ぐために非常に重要です。
- 繰り返す口内炎: 特に、痛みが強く、治りにくい口内炎が何度もできる場合は注意が必要です。
- その他の症状: 皮膚の発疹、目の充血や痛み、視力低下、陰部の潰瘍、原因不明の関節痛、腹痛や下痢などが続く場合も、ベーチェット病の可能性があります。
これらの症状が気になる場合は、まずはかかりつけ医に相談するか、リウマチ科、膠原病内科、眼科、皮膚科などの専門医を受診しましょう。
受診の際には、
- いつから、どんな症状があるか
- 症状はどのくらいの頻度で起こるか
- 症状の経過(良くなったり悪くなったりするか)
- これまでの病歴や治療歴
などを、できるだけ詳しく伝えることが、正確な診断の手がかりとなります。
まとめ
ベーチェット病は、全身に様々な症状が現れる複雑な病気ですが、近年、その病態解明や治療法は着実に進歩しています。 日本のベーチェット病は、腸管型が増加するなど、その姿を変えつつありますが、抗TNF-α抗体などの新しい治療薬の登場により、多くの患者さんが症状をコントロールできるようになってきました。
しかし、まだ原因は完全には解明されておらず、特に特殊型の治療には課題も残っています。 今後は、患者さん一人ひとりの症状や遺伝的な特徴に合わせた、より個別化された治療法(オーダーメイド治療)の開発が期待されます。
原因不明の症状に悩んでいる方は、一人で抱え込まず、ぜひ専門医に相談してみてください。 早期発見・早期治療が、あなたの未来を守る鍵となります。
参考文献
- Kirino Y, Nakajima H. Clinical and Genetic Aspects of Behçet’s Disease in Japan. Intern Med. 2019 May 1;58(9):1199-1207.
健康・医学関連情報の注意喚起
本記事は、ベーチェット病に関する一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の医学的アドバイスを提供するものではありません。 ベーチェット病の診断や治療については、必ず医療従事者にご相談ください。