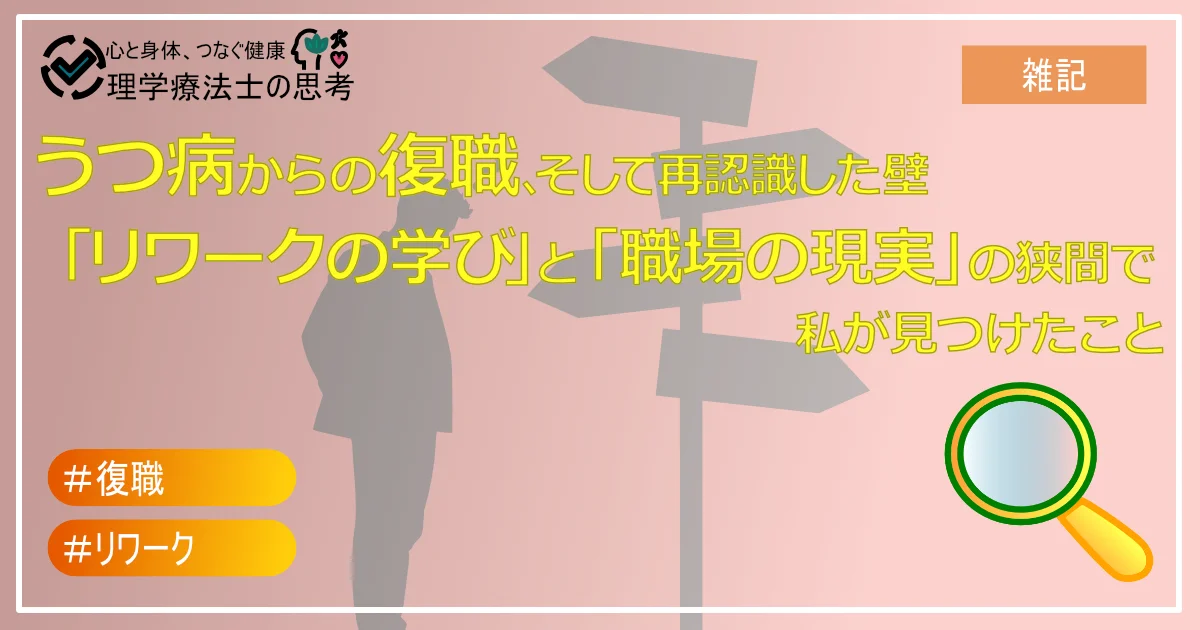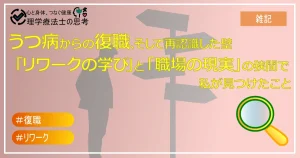うつ病など、心の不調からの復職は、長いトンネルを抜けた先に見える一つの光かもしれません。しかし、それは決してゴールではなく、新たなスタートラインです。そして、そのスタートラインの先には、しばしば「復職後の壁」とも言うべき、新たな課題が待ち受けていることがあります。
私自身、うつ病に加え、ストレスが引き金となったパニック障害やベーチェット病と共に生きる中で、復職というプロセスを経験しました。
その過程で直面した、復職支援(リワーク)で学んだ「理想の働き方」と、職場という「現実の要求」との間の大きなギャップ、そしてそのジレンマについて、私の体験を共有させていただければと思います。
この記事が、
- うつ病などから復職し、同様の悩みを抱えている方
- これから復職を目指している方
- 復職者を支えるご家族や同僚、上司、人事担当者の方
- 組織におけるメンタルヘルス対策や働き方について考えている方
にとって、何かの気づきや考えるきっかけとなれば幸いです。
光と道標:リワークプログラムで得た「自分を守る術」
休職期間中、私は復職支援プログラム(リワーク)に参加しました。そこは、単に職場に戻るための準備をするだけでなく、これからの人生で自分自身を守りながら生きていくための術を学ぶ、貴重な場所でした。
リワークで得た特に重要な学びは、以下のようなものです。
- 自己理解を深める: 自分がどんな状況でストレスを感じやすいのか、どんな思考の癖があるのか、そして自分の心身の限界点はどこにあるのかを客観的に知ること。
- セルフケアの徹底: 「体調が最優先」であること。一度心身を壊してしまうと、完全に元通りになるのは難しく、不可逆的なダメージを負う可能性もある(私自身、複数の病気を抱えることになりました)。だからこそ、無理をしない、限界を超える前に休むことの重要性を痛感しました。
- 適切なコミュニケーション: 自分の状態や考えを正直に、かつ相手に受け入れられやすい形で伝えるスキル。助けが必要な時に、適切に「相談」したり、「交渉」したりする力。
- 柔軟な思考: 物事を「0か100か」「できるかできないか」だけで考えないこと。「少しずつできることを増やす」「中間択を探す」という、段階的でしなやかな考え方。
リワークでの学びは、暗闇の中に差し込む光のように、私に復職への希望と、具体的な対処法を与えてくれました。「これなら、きっと大丈夫だ」と、そう思えた時期もありました。
現実の壁:職場が求める「成果」と「配慮」の限界
しかし、いざ職場に復帰すると、そこにはリワークで学んだ理想とは異なる、「現実」が待っていました。
もちろん、職場も可能な範囲で配慮をしてくれようとはしていました。そのことには感謝しています。しかし、組織である以上、そこには無視できない論理が存在します。
- 「成果」への要求: どんな組織であれ、存続のためには一定の成果や生産性が求められます。個々の事情への配慮も、この前提の中で行われざるを得ません。
- 「配慮」の限界:
- リソースの制約: 経営状況や人員不足など、組織が持つリソースには限りがあり、一人のスタッフに対してかけられる配慮(業務量の調整、人員配置など)にも自ずと限界があります。
- 他のスタッフへの影響: 特定のスタッフへの配慮が、他のスタッフの負担増に繋がる可能性があります。また、「あの人だけ特別扱いされている」といった不平等感を生み出す懸念も、組織としては考慮せざるを得ない点です。私の職場でも、管理職の方がこの点に苦慮されている様子は伝わってきました。
リワークで学んだ「自分のペースで、無理なく」という働き方は、この「成果」と「配慮の限界」という現実の壁の前で、なかなかスムーズには実践できませんでした。
ジレンマ:「理想の働き方」と「現実の要求」の狭間で
ここに、復職後の私が陥った大きなジレンマがあります。
- リワークで学んだ「自分を守る働き方」を優先しようとすると… → 職場で求められる成果やスピードについていけず、焦りや罪悪感を感じてしまう。
- 職場の要求に応え、「成果」を出そうとすると… → リワークで学んだ「無理しない」「体調優先」という原則を破り、以前のように自分を追い込み、心身をすり減らしてしまう。
まさに、板挟みの状態でした。
リワークで学んだ「0か100ではない、中間択を探す」という考え方を頼りに、なんとかバランスを取ろうと試みました。無理のない範囲で、少しずつできることを増やしていこう、と。
しかし、そんな矢先に、予期せぬ環境の激変が訪れます。院内での新型コロナウイルス感染症の発生と、それに伴う感染対策の強化・業務負荷の増大。そして、ちょうどそのタイミングが、私が第一子の産後パパ育休から復帰した直後だったのです。
急激に増大した負荷に対し、私の心身はすぐには適応できませんでした。大きなストレスを抱え、次第に対応できなくなり、ついには以前のように体が動かなくなってしまいました。
その時、気づいたのです。私は無意識のうちに、「なんとかこの環境に適応しなければ」「周りに迷惑をかけられない」と、必死に頑張ろうとしていた自分に。そして、それが結果的に、リワークで学んだはずの「自分を守る」という原則から、再び遠ざかることに繋がっていたのだと。
さらに、上司からのフィードバックも、意図せず私を元の思考パターンに戻す力として働いてしまった側面がありました。おそらく配慮の意図もあったのだと思いますが、他のスタッフの状況などを伝えられると、「やはり自分が頑張らないと迷惑がかかる」というプレッシャーを感じ、ますます「自分を守る」ための行動(例えば、できないことを正直に伝える、休息を優先するなど)が取りにくくなってしまったのです。これでは、また体調を崩した頃の自分に戻ってしまう…。
見えてきた道:環境と働き方の「再選択」という可能性
この経験を通して、私は一つの結論に至りました。
それは、現在の職場環境と、今の私が目指すべき(あるいは、病気と共に生きていく上で目指さざるを得ない)働き方との間には、残念ながら埋めがたいギャップが存在する、ということです。そして、この環境で働き続けることは、自分自身にとって再発のリスクを高める可能性がある、と。
ここで得た重要な気づきは、「環境に適応することだけが全てではない」ということです。もちろん、ある程度の適応は必要です。
しかし、自分に合わない環境に無理やり自分をねじ込もうとすることが、心身をさらに蝕むのであれば、それは正しい選択とは言えないのではないか。時には、環境そのものを変える、あるいは働き方そのものを変えるという選択肢を真剣に考える必要があるのだ、と。
今の私にとって、元の自分に戻ることは、病気の再発に直結しかねません。リワークでの学びを実践し、自分を守りながら持続可能な形で働くためには、環境の側を変える必要があると感じました。
ですから、今後は以下の方向で、自分の道を探していこうと考えています。
- 自分を守れる「環境」を探す: 成果のみを追求するのではなく、個々の状況に応じた柔軟な働き方が可能で、従業員の心身の健康を本当に大切にする文化のある職場環境を視野に入れる。
- 無理しない「働き方」を模索する: 正社員という形にこだわらず、業務内容や労働時間、働く場所など、子育て(我が家は共働きです)との両立も考慮しながら、自分のペースで、心身ともに「持続可能」な働き方を具体的に考えていく。
これは決して「逃げ」ではなく、私自身と、そして大切な家族の未来を守るための、前向きで「戦略的な再選択」なのだと捉えています。
おわりに:もし、あなたが同じような壁に直面しているなら
うつ病などからの復職後の道のりは、個人差はあれど、決して平坦なものではないかもしれません。リワークなどで学んだ理想と、職場の現実とのギャップに悩み、苦しんでいるのは、決してあなただけではないと思います。
大切なのは、自分の心と体の声に、誰よりも正直に耳を傾けることです。自分の限界を知り、それを超えないように自分を守ること。そして、もし今の環境がどうしても自分に合わないと感じるなら、勇気を出して環境や働き方を変えるという選択肢を持つことです。
完璧を目指す必要はありません。主治医やカウンセラー、リワークのスタッフ、信頼できる家族や友人、地域の支援機関など、利用できるサポートは遠慮なく活用してください。焦らず、少しずつ、あなたにとっての「持続可能な働き方」を見つけていくプロセスそのものが、回復への大切な一歩となるはずです。
そして、もしあなたが復職者を支える立場にあるなら、その方が直面しているかもしれないジレンマや、組織として配慮できることの限界といった構造的な課題にも目を向け、共に解決策を模索していく視点を持っていただけたら、これほど心強いことはありません。
この記事が、同じような壁に直面している誰かの心に、少しでも寄り添うことができたなら幸いです。