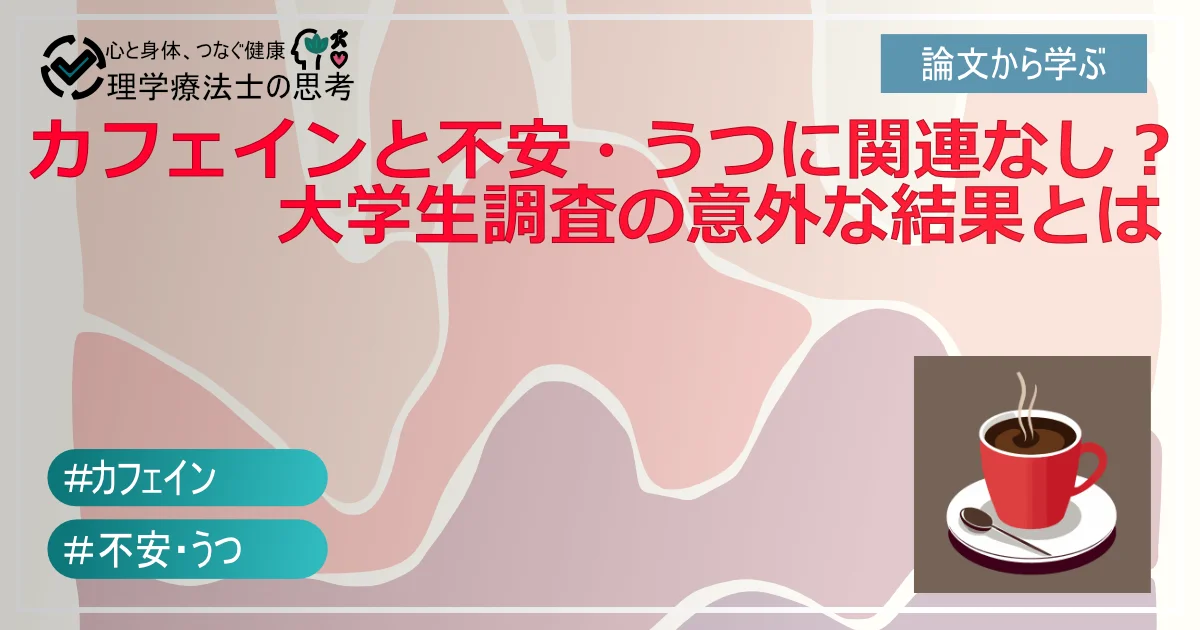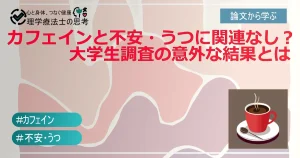「カフェインを摂りすぎると不安になる」 「コーヒーを飲むと気分が落ち込む気がする…」
カフェインとメンタルヘルス、特に不安やうつ病との関係については、ネガティブなイメージを持っている方も多いのではないでしょうか?
実際、理学療法士の思考の中でカフェインに関してご紹介した研究など、高用量のカフェインがパニック発作を引き起こしたり、不安を増強させたりする可能性を示す報告もあります。
しかし、今回ご紹介する研究は、少し意外な結果を示しています。サウジアラビアの大学生を対象に行われた調査では、日常的なカフェイン摂取量と、うつ病・不安・ストレスの重症度との間に、明確な関連が見られなかったというのです。
こんにちは!理学療法士のPTケイです。今回は、この興味深い研究結果を詳しく見ていくと共に、なぜこのような結果になったのか、そしてカフェインと私たちのメンタルヘルスの関係について、改めて考えてみたいと思います。
研究紹介:サウジアラビアの大学生を対象とした調査
まずは、今回ご紹介する研究の概要です。
2023年にサウジアラビアなどの研究グループ(筆頭著者:テンディ・M・マッキ)は、メディナの大学生におけるカフェイン消費とうつ病、不安、ストレスレベルとの関連を調査する横断研究を行いました。
その結果、調査対象の大学生の間では高レベルのうつ病、不安、ストレス症状が報告されましたが、毎日のカフェイン摂取量とこれらの症状の重症度との間に統計的に有意な関連は見られなかったと報告しました。(Makki TM, et al. Cureus. 2023)
この研究は「横断研究」という種類の調査で、ある一時点での状態を切り取って分析するものです。サウジアラビア・メディナにあるタイバ大学の学生さん520名(平均年齢約21歳、約74%が女性)に協力してもらい、オンラインアンケートを使って以下の情報を集めました。
- 普段のカフェイン摂取量: コーヒー(アラビアコーヒー、スペシャルティコーヒー、レギュラーコーヒー)、紅茶、コーラなどをどれくらい飲むか質問し、1日の総カフェイン摂取量を推定。
- 精神的な健康状態: DASS-21という、うつ病・不安・ストレスの症状の程度を評価する質問票に回答してもらう。
- その他、年齢、性別、学部、喫煙状況、精神疾患の既往歴など。
そして、収集したデータをもとに、「カフェインをたくさん摂っている学生ほど、うつ・不安・ストレスの症状も重いのか?」という関連性を統計的に分析しました。
驚きの結果:カフェインと精神症状に「関連なし」
分析の結果、研究チームも予想外だったかもしれない、驚きの結果が出ました。
- カフェイン摂取量と、うつ病・不安・ストレスの各症状の重症度との間に、統計的に意味のある関連は見られなかった
のです。つまり、「カフェインを多く摂っている学生ほど、うつ症状が重い」とか、「カフェイン摂取量が少ない学生ほど、ストレスレベルが低い」といった明確な傾向は、この調査対象の学生さんたちにおいては確認できませんでした。
これは、「カフェインはメンタルヘルスに悪影響を与える」という一般的なイメージや、一部の先行研究の結果とは異なるものです。
一方で… 深刻なメンタルヘルスの実態も
カフェインとの関連は見られなかったものの、この研究ではもう一つ、非常に重要な点が明らかになりました。それは、調査対象となった大学生の多くが、非常に高いレベルの精神的な不調を抱えていたという事実です。
DASS-21の結果によると、
- 約72%の学生に何らかのうつ症状があり、うち51%は「極めて重度」
- 約75%の学生に何らかの不安症状があり、うち61%は「極めて重度」
- 約65%の学生に何らかのストレス症状があり、うち46%は「極めて重度」
と分類されました。これは非常に高い割合であり、対象となった大学生たちが大きな精神的負担を抱えている可能性を示唆しています。
ちなみに、彼らのカフェイン摂取量の中央値(全体を順番に並べた時の真ん中の値)は1日あたり約325mgで、これはFDA(アメリカ食品医薬品局)が推奨する成人の上限400mgに近い値であり、日本の若者の平均摂取量と比較しても多いと考えられます。摂取源としては、アラビアコーヒーやスペシャルティコーヒー、紅茶などが主でした。
なぜ「関連なし」? 考えられる理由と研究の限界
では、なぜこの研究では、カフェイン摂取と精神症状の重症度に関連が見られなかったのでしょうか? 研究者たち自身も考察していますが、いくつかの理由が考えられます。
- 横断研究の限界(因果関係不明): 最も大きな理由として、これが横断研究である点が挙げられます。ある一時点での関連しか見ていないため、「カフェインが原因で精神症状が起きた」のか、「精神症状がある人がカフェインを多く(あるいは少なく)摂るようになった」のか、その時間的な前後関係や因果関係は全く分かりません。
- 他の要因の影響(交絡因子): 大学生のメンタルヘルスには、カフェイン以外にも、学業のプレッシャー、睡眠不足、経済的な問題、人間関係、将来への不安、食生活など、非常に多くの要因が影響します。今回の研究ではこれらの要因が十分に考慮されていない可能性があり、それらが結果に影響を与えた(交絡した)可能性も否定できません。
- 文化的な背景やカフェイン摂取の動機: サウジアラビアという文化圏では、コーヒー(特にアラビアコーヒー)が社交の場で重要な役割を果たしている場合があります。カフェイン摂取の動機が、単なる覚醒目的だけでなく、コミュニケーションや文化的な習慣と結びついている場合、精神状態との単純な関連が見えにくくなる可能性も考えられます。
- カフェインの種類や摂取パターン: アラビアコーヒーなど、日本とは異なる種類のカフェイン源が主であることや、一度に大量摂取するのか、少量ずつ頻回に摂取するのかといったパターンも影響するかもしれません。
- 測定の限界: カフェイン摂取量も精神症状も自己申告に基づいているため、正確性に限界があります。また、DASS-21は症状の重症度を見るものであり、臨床的な診断とは異なります。
- データ収集時期の影響(COVID-19パンデミック後): この調査は2022年7月、つまりCOVID-19のパンデミックがある程度落ち着いた後とはいえ、その影響が残っている時期に行われました。パンデミックは世界中の人々のメンタルヘルスや生活習慣(カフェイン摂取パターン含む)に大きな変化をもたらした可能性があります。そのため、パンデミックの影響が、今回の研究結果(特に高い精神症状レベルや、カフェインとの関連が見られなかったこと)に何らかの形で影響を与えた可能性も考慮する必要があります。
これらの理由から、この研究の「関連なし」という結果だけを見て、「カフェインは大学生のメンタルヘルスに全く影響しない」と結論づけるのは早計です。
あくまで「この特定の集団(サウジアラビアの大学生)において、この調査方法・時期では、日常的なカフェイン摂取量と精神症状の重症度との間に明確な統計的関連は見つからなかった」と解釈するのが適切でしょう。
カフェインとメンタルヘルス:単純ではない複雑な関係
今回の研究結果は、カフェインとメンタルヘルスの関係が一筋縄ではいかない、非常に複雑なものであることを改めて示唆しています。(そのためPTケイは、カフェインに関する研究論文を引き続き調査していこうと考えています。)
- 「量」による影響の違い: 高用量ではパニック発作のリスクを高める可能性(前回の記事)。しかし、日常的な量では影響が小さい、あるいは他の要因の方が大きい可能性。
- 「個人差」: カフェインに対する感受性は人それぞれ。遺伝的な要因も関わると言われています。
- 「性差」: 前回の記事で紹介した別の研究では、女性の方が不安との関連が見られやすい可能性が示唆されました。
- 「状況」や「期待」: ストレスが高い状況で飲むのか、リラックスして飲むのか。また、「これを飲めば元気になるはず」といった期待感も影響する可能性があります。
- 「文化」や「習慣」: カフェイン摂取がどのような意味を持つか、社会的な背景も無視できません。
- 「時代背景」: 今回の研究のように、パンデミックのような大きな社会情勢も影響を与える可能性があります。
「カフェイン=悪」と単純に決めつけるのではなく、これらの様々な要因が絡み合って影響が現れる、と考える方がより現実に近いのかもしれません。
まとめ
今回は、サウジアラビアの大学生を対象とした、カフェイン摂取と精神症状(うつ・不安・ストレス)の関連を調べた横断研究をご紹介しました。
- この研究では、日常的なカフェイン摂取量と、うつ・不安・ストレスの症状の重症度との間に、統計的に有意な関連は見られませんでした。これは、一部の先行研究や一般的なイメージとは異なる結果です。
- ただし、これは横断研究であり、因果関係を示すものではありません。また、研究デザインや対象集団の特性、未測定の要因などが結果に影響している可能性があり、解釈には注意が必要です。
- 一方で、調査対象となった大学生の多くが深刻な精神的不調を抱えている実態も明らかになり、メンタルヘルスサポートの重要性が示唆されました。
- カフェインとメンタルヘルスの関係は非常に複雑で、摂取量、個人差、性差、文化、状況など多くの要因が絡み合っています。
結局のところ、「カフェインをどれくらいなら摂っても大丈夫か」という問いに対する万能な答えはありません。大切なのは、ご自身の心と体の声に耳を傾け、カフェインを摂取した時の変化を客観的に観察することです。そして、もしカフェインと体調不良の関連を感じたり、メンタルヘルスの不調に悩んでいたりする場合は、一人で抱え込まず、必ず医師や専門家に相談してください。
今回の研究結果が、カフェインとの付き合い方や、メンタルヘルスについて改めて考えるきっかけとなれば幸いです。
参考文献
Makki TM, Alharbi ST, Alharbi AM, Alsharif AS, Aljabri AM. Caffeine Consumption and Levels of Depression, Anxiety, and Stress Among University Students in Medina, Saudi Arabia: A Cross-Sectional Study. Cureus. 2023;15(10):e48033. Published 2023 Oct 31. doi:10.7759/cureus.48033
健康・医学関連情報の注意喚起:
本記事は、カフェインとメンタルヘルスに関する一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の医学的アドバイスを提供するものではありません。 うつ病、不安障害、ストレス関連障害などの診断や治療、カフェイン摂取に関する判断については、必ず医療従事者にご相談ください。