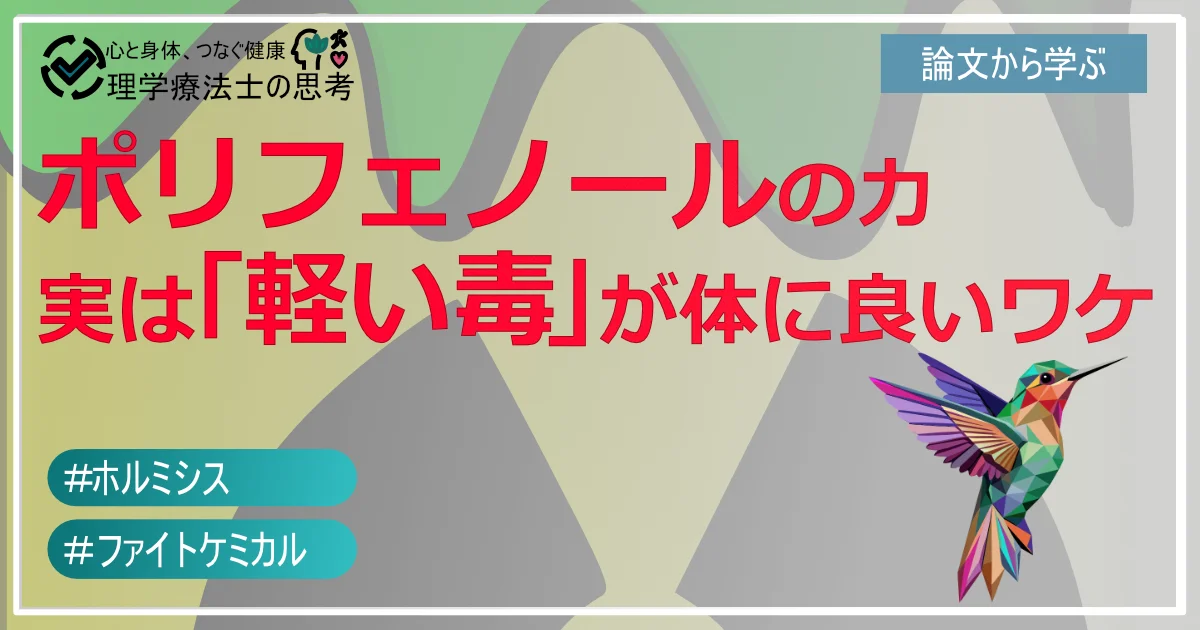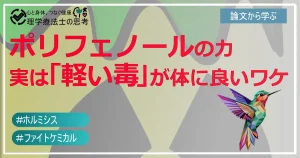「ポリフェノールは体に良い」「抗酸化作用で老化防止!」 健康に関心のある方なら、一度は耳にしたことがある言葉ではないでしょうか?
緑茶のカテキン、赤ワインのレスベラトロール、大豆イソフラボンなど、様々な食品に含まれるポリフェノールは、健康効果が期待される成分として大人気ですよね。
しかし、「なぜポリフェノールは体に良いのか?」その本当の理由について、深く考えたことはありますか? 単純な「抗酸化作用」だけでは説明がつかない現象も多いのです。
こんにちは!あなたの心と体の健康をサポートする理学療法士のPTケイです。今回は、ポリフェノールの健康効果について、私たちが持っているイメージを少し覆すかもしれない、興味深い日本の研究者の総説・オピニオン論文をご紹介します。もしかしたら、ポリフェノールの本当の力は、「体に優しい」からではなく、むしろ「体に軽いストレスを与える」ことにあるのかもしれません。
研究紹介:ポリフェノールの作用機序への新しい視点
まずは、今回参考にする論文の概要です。
2022年に日本の研究者ムラカミ アキラ氏は、ポリフェノールの生理活性発現メカニズム、特にストレス応答経路に関する考察についての総説・オピニオンを発表しました。
この論文では、ポリフェノールは生体にとって異物として作用し、適度なストレスを与えることで生体の防御・適応応答(ホルミシス効果)を引き出し、結果的に健康効果(機能性)を発揮する可能性があり、一方で過剰摂取は害になりうると論じています 。
この論文は、これまでの常識に一石を投じ、ポリフェノールの働きをより深く理解するための新しい切り口を提示しています。
ポリフェノールは味方?それとも「異物」?
私たちはポリフェノールを「体に良い成分」として捉えがちです。しかし、この論文では、まずポリフェノールは栄養素ではなく、生体にとっては「異物」であると認識すべきだと指摘しています 。
その根拠として、
- 栄養素のように、消化管で特定の輸送体(トランスポーター)によって積極的に吸収される仕組みがないこと 。
- ごく微量が体内に吸収されたとしても、薬物と同じように代謝され、速やかに体外へ排泄されること 。
などが挙げられています。
「第7の栄養素」と呼ばれることもあるポリフェノールですが、生物学的な観点から見ると、薬や、もっと言えば「軽い毒」に近い存在だと考える方が実態に近いのかもしれません 。
この認識が、ポリフェノールの本当の働きを理解する上で非常に重要になります。
「軽いストレス」が鍵?ホルミシス効果とは
では、「異物」であり「軽い毒」であるポリフェノールが、なぜ体に良い効果をもたらすのでしょうか? そこで登場するのが「ホルミシス」という考え方です 。
ホルミシスとは、「通常は有害なものでも、量が少なければ、逆に体にとって有益な刺激となる」という現象のことです 。身近な例でいえば、
- 適度な運動(ストレス)は筋力をアップさせる(有害なほどの過度な運動は体を壊す)
- 適度な日光浴(紫外線ストレス)はビタミンD合成を促す(過度な日光浴は皮膚がんリスクを高める) といった現象がホルミシス効果の一例です。
ポリフェノールも同様に、体にとっては「異物」というストレスになります。細胞内に侵入したポリフェノールは、
- それ自体が酸化を促進したり(酸化ストレス)
- 化学構造が変化して細胞内のタンパク質に結合したり(タンパク質ストレス) することがあります。
しかし、このストレスが「適度」であれば、私たちの体はそれに抵抗し、適応しようとします。具体的には、
- 抗酸化酵素(体のサビを防ぐ酵素)の働きを高める
- 分子シャペロン(タンパク質の傷みを修復する)を増やす
- 解毒酵素(異物を無毒化して排泄する酵素)を活性化させる といった防御・適応システムがスイッチONになるのです 。
つまり、ポリフェノールを摂取することで、体が本来持っている防御力をトレーニングし、ストレスに対する抵抗力を高めている、と考えることができるのです 。これが、ポリフェノールの機能性の本質的なメカニズムの一つではないか、とこの論文では提唱しています。
- 用語解説:
- ホルミシス: 有害な作用を持つものでも、微量であれば逆に良い効果を示す現象。
- 酸化ストレス: 体内で活性酸素などの酸化物質が過剰になり、体の抗酸化能力とのバランスが崩れて細胞がダメージを受ける状態。
- タンパク質ストレス: タンパク質の構造異常や機能不全が細胞に引き起こすストレス状態。
緑茶EGCGの脂肪分解:新メカニズムの可能性
この「ストレス応答」という視点から、緑茶ポリフェノールの代表格であるEGCG(エピガロカテキンガレート)の脂肪分解作用についても、新しいメカニズムが提唱されています 。
EGCGが脂肪を分解する効果があることは知られていますが、「なぜ?」という根本的なメカニズムは不明でした。この論文の著者らは、以下のステップで説明しています。
- EGCGが細胞にストレスを与える: 脂肪を溜め込んだ肝臓細胞にEGCGを加えると、まず細胞内に酸化ストレスやタンパク質ストレスが生じます 。
- 防御応答でエネルギー(ATP)を消費: 細胞はこれらのストレスに対抗するため、抗酸化酵素や分子シャペロンなどを活性化させますが、この防御応答にはエネルギー(ATP)が必要です。そのため、細胞内のATPが一時的に減少します 。
- エネルギー不足を補うために脂肪分解!: 細胞はエネルギー不足(ATP減少)を感知すると、新たなエネルギー源を求めて、細胞外からグルコースを取り込んだり、細胞内に蓄積していた中性脂肪(TG)を分解したりしてATPを作り出そうとします 。
- エネルギー恒常性の回復: 結果として、中性脂肪が分解され、細胞内のATPレベルは元の状態に回復します 。
つまり、EGCGの脂肪分解効果は、EGCGが直接脂肪を溶かすのではなく、EGCGが引き起こす「ストレス」と、それに対する「細胞のエネルギー危機管理システム」の結果として現れる、という新しい考え方です 。
著者らは、香辛料ターメリックの成分であるクルクミンについても、同様のメカニズムを示唆する結果を得ています 。
ただし、これはまだ培養細胞レベルでの発見であり、私たちの体の中で実際にこのメカニズムがどれほど働いているかは、今後の研究(動物実験やヒトでの検証)が必要です 。
- 用語解説:
- EGCG (エピガロカテキンガレート): 緑茶に最も多く含まれるポリフェノール(カテキン)の一種。強い生理活性を持つとされる。
- ATP (アデノシン三リン酸): 細胞内でエネルギーの貯蔵・供給を担う物質。「エネルギー通貨」とも呼ばれる。
「過ぎたるは猶及ばざるが如し」適量の重要性
ここまで読むと、「やっぱりポリフェノールはすごい!」と思われるかもしれません。しかし、忘れてはいけないのは、ポリフェノールはあくまで「異物(軽い毒)」であるという側面です。
ホルミシス効果は「適度な」ストレスによって引き起こされます。もしポリフェノールの量が多すぎて、ストレスが「過度」になれば、それは有益な効果どころか、体に害を与える可能性があります 。
実際、この論文の著者らは、マウスを用いた実験で、緑茶ポリフェノールが中程度の量では有益な効果を示した一方で、高用量では肝臓や腎臓に障害を引き起こしたことを報告しています 。
テレビCMなどでは「機能性成分たっぷり!」といった表現をよく見かけますが、「多ければ多いほど良い」というのは、少なくともポリフェノールのようなファイトケミカル(植物由来の化学物質)には当てはまらない可能性が高いのです 。
重要なのは、効果と安全性のバランスが取れた「至適用量」を見つけることです。しかし、この至適用量は、年齢、性別、遺伝的体質、健康状態、ライフスタイルなどによって、一人ひとり異なると考えられます 。
残念ながら、現時点では、個々人に合った至適用量を科学的に決定する方法は確立されていません 。
まとめ
今回は、ポリフェノールの健康効果について、「異物」に対する「ストレス応答(ホルミシス)」という新しい視点から解説したレビュー論文をご紹介しました。
- ポリフェノールは栄養素ではなく、体にとっては「異物」であり、軽いストレスを与える存在である 。
- その適度なストレスが、体の防御システムを活性化させ(ホルミシス効果)、結果的に健康に良い影響(機能性)をもたらす可能性がある 。
- 緑茶EGCGの脂肪分解作用も、このストレス応答メカニズムで説明できるかもしれない 。
- しかし、ポリフェノールは過剰に摂取すると害になる可能性があり、「多ければ多いほど良い」わけではない 。
- 効果と安全性を両立する「至適用量」が存在するはずだが、それは個人差が大きいため、今後の研究課題である 。
ポリフェノールを含む機能性食品やサプリメントを利用する際には、「体に良い成分だから」と安易に考えるだけでなく、その「異物」としての性質も理解し、過剰摂取に注意することが大切です。そして、「自分にとっての適量」はどれくらいなのか、という視点を持つことが、今後の健康管理において重要になってくるでしょう。
参考文献
Murakami A. ポリフェノールはなぜ効くか? 日本調理科学会誌. 2022;55(1):54-56. doi:10.11402/cookeryscience.55.54
健康・医学関連情報の注意喚起
本記事は、ポリフェノールに関する一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の食品や成分の効果効能を保証したり、医学的アドバイスを提供するものではありません。 特定の食品やサプリメントの摂取、健康上の問題については、必ず医療従事者にご相談ください。