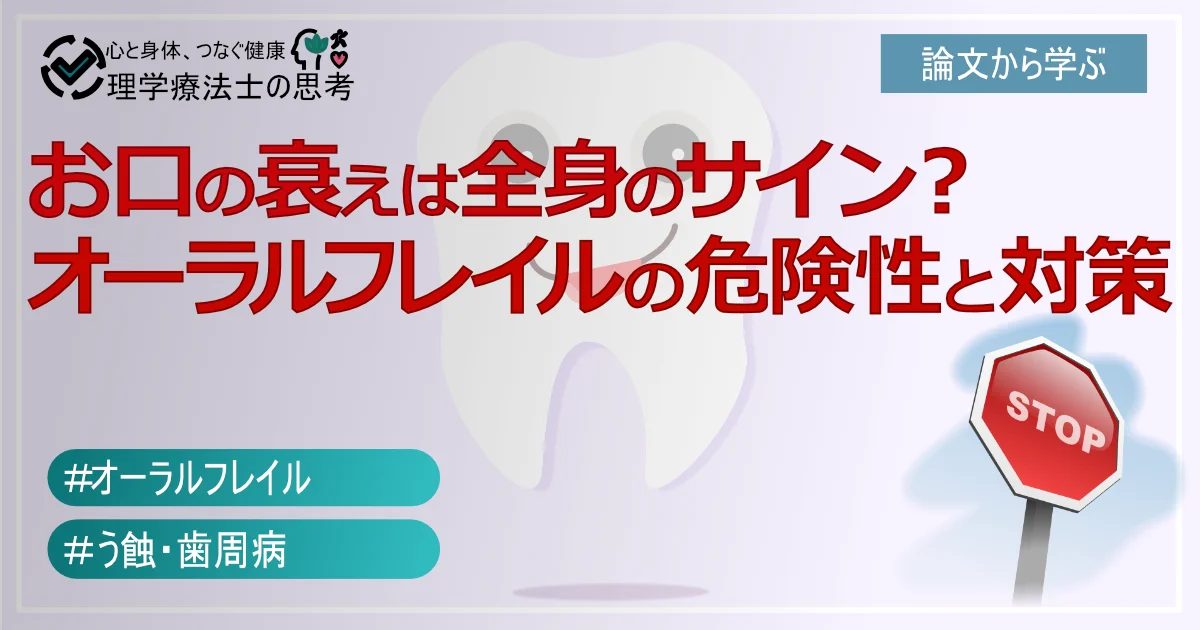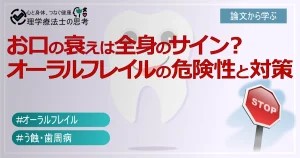「最近、食事の時にむせやすくなったな…」 「硬いものが食べにくくて、柔らかいものばかり選んでしまう」 「なんだか滑舌が悪くなった気がする…」
年齢を重ねると、お口周りのちょっとした変化を感じることが増えるかもしれません。「年のせいだから仕方ない」そう思っていませんか?
でも、ちょっと待ってください! そのお口の些細な衰え、もしかしたら「オーラルフレイル」のサインかもしれません。そして、それは単にお口の問題だけでなく、全身の衰え(フレイル)の始まりである可能性が指摘されているのです。
こんにちは!あなたの心と体の健康をサポートする理学療法士のPTケイです。
今回は、この「オーラルフレイル」について、その重要性、原因、そして私たちができる対策について、専門家による総説論文(多くの研究をまとめた報告書)を参考に、詳しく解説していきます。お口の健康が、いかに全身の健康、そして私たちのQOL(生活の質)に繋がっているか、一緒に見ていきましょう。
研究紹介:オーラルフレイルと地域医療の役割
まずは、今回参考にする論文の概要です。
2020年に日本の歯科医師・研究者である笹本祐馬先生らが発表した総説「オーラルフレイルと地域医療の役割」では、オーラルフレイル(口腔機能の軽微な衰え)は全身のフレイルの前段階であり、早期発見と歯科専門職だけでなく多職種による介入(栄養指導、リハビリテーション等)が重要であるとまとめられています。
この総説は、オーラルフレイルの全体像を理解し、私たちが何をすべきかを考える上で、非常に示唆に富む内容となっています。
オーラルフレイルって何? なぜ注意が必要なの?
まず、「オーラルフレイル」とは何でしょうか? これは、「オーラル(Oral = 口腔の)」と「フレイル(Frailty = 虚弱)」を組み合わせた言葉で、簡単に言うとお口周りの機能が些細なレベルで衰えてきた状態を指します。
具体的には、
- 食べこぼしが増える
- 食事中にむせる、飲み込みにくさを感じる
- 硬いものが噛みにくくなる
- 滑舌が悪くなる(話しにくくなる)
- 口の中が乾燥しやすくなる
といった、一つ一つは小さな変化かもしれません。
しかし、このオーラルフレイル、なぜ注意が必要なのでしょうか? それは、オーラルフレイルが、全身のフレイル(加齢による心身の衰弱)の初期段階、いわば「入口」であると考えられているからです。
オーラルフレイルを放置すると、
- 噛む力や飲み込む力が低下する
- 食事量が減ったり、柔らかいものばかりになったりして栄養が偏る(低栄養)
- 筋肉量が減少し、サルコペニア(加齢性筋肉減弱症)につながる
- これらの結果、全身のフレイルが進行し、転倒、骨折、入院、要介護状態のリスクが高まる
という悪循環に陥ってしまう可能性があります。 つまり、お口の健康は全身の健康のバロメーターであり、オーラルフレイルのサインに早く気づき、適切に対処することが、健康で自立した生活を長く続けるために非常に重要になるのです。
忍び寄る口のトラブル:オーラルフレイルの原因
オーラルフレイルは、加齢に伴う様々な口腔内の変化が複合的に関与して起こります。主な原因となる口のトラブルを見てみましょう。
- 歯の喪失: 加齢とともに歯を失う方は少なくありません。主な原因は「う蝕(うしょく=虫歯)」と「歯周病」です。歯が減ると、当然噛む力が低下し、食べられるものが制限され、栄養の偏りや食事量の減少につながります。また、歯がないことは見た目にも影響し、QOL(生活の質)の低下にも繋がります。
- 歯周病: 歯周病は、歯周病菌の感染によって歯茎や歯を支える骨(歯槽骨)が破壊される病気です。進行すると歯がグラグラになり、最終的には抜けてしまいます。歯周病は単に歯を失う原因になるだけでなく、慢性的な炎症が全身に影響を及ぼし、糖尿病、心血管疾患、認知症、骨粗鬆症などのリスクを高めることも分かっています。フレイルやサルコペニア自体も歯周病のリスクを高めるとされており、悪循環を生む可能性があります。
- う蝕(虫歯): 高齢者の虫歯は、歯の根元(根面う蝕)にできやすいのが特徴です。痛みが出ると食事が困難になり、歯の喪失にも繋がります。特に介護施設入所者では虫歯の割合が高くなる傾向があります。
- 口腔乾燥症(ドライマウス): 加齢自体で唾液の分泌量が必ずしも減るわけではありませんが、服用している薬(降圧剤、抗うつ薬など)の副作用や、全身疾患の影響で口が渇きやすくなることがあります。唾液には口の中を清潔に保ち、食べ物をまとめ、飲み込みやすくする重要な役割があります。唾液が減ると、虫歯や歯周病のリスクが高まるだけでなく、話しにくさ、食べにくさ、飲み込みにくさ(嚥下障害)にも繋がります。
これらの口腔内のトラブルが、噛む力(咀嚼機能)、飲み込む力(嚥下機能)、話す力(構音機能)などの口腔機能全体の低下を引き起こし、オーラルフレイルへと繋がっていくのです。
もしかして私も?オーラルフレイルのサインと評価法
「自分は大丈夫かな?」と気になった方もいるかもしれません。オーラルフレイルの兆候は、日常生活の中での小さな変化として現れます。以下のようなサインに注意してみましょう。
- 食事に関するサイン:
- 以前より硬いものが食べにくくなった(例:たくあん、さきいかなど)
- 食事の時にむせることが増えた
- 食べこぼしをするようになった
- 食事に時間がかかるようになった
- 柔らかいものばかり好んで食べるようになった
- お口に関するサイン:
- 滑舌が悪くなった、話しにくくなった
- 口の中が乾きやすい
- 口臭が気になるようになった
これらのサインがいくつか当てはまる場合は、オーラルフレイルの可能性を考えてみても良いかもしれません。
医療機関や専門機関では、以下のような検査で口腔機能をより詳しく評価します。
- 咀嚼能力: 特定の食品を噛めるかどうか、咬合力測定器など
- 舌の機能: 舌の動きの速さや巧みさ(オーラルディアドコキネシス:パタカ測定)、舌が押し出す力(舌圧測定)
- 嚥下(飲み込み)機能: 反復唾液嚥下テスト(30秒間に何回唾液を飲み込めるか)、嚥下内視鏡検査など
- 口腔乾燥: 口腔水分計など
- 用語解説:
- オーラルディアドコキネシス: 「パ」「タ」「カ」といった音を連続して速く発音してもらい、1秒あたりの回数を測定することで、唇や舌、軟口蓋の動きの巧みさや速さを評価する検査。
- 反復唾液嚥下テスト(RSST): 30秒間に意識的に何回唾液を飲み込めるかを数える簡単なテスト。嚥下機能のスクリーニングに用いられる。
オーラルフレイルに負けない!今日からできる対策
オーラルフレイルは、早期に気づき、適切な対策を行うことで、進行を予防したり、改善したりすることが可能です。対策の柱は「口腔ケア」「栄養」「運動」の3つです。
1. 口腔ケア:お口を清潔に保つ
- 丁寧な歯磨き: 虫歯や歯周病の最大の原因である歯垢(プラーク)を取り除く基本です。歯ブラシだけでなく、歯間ブラシやデンタルフロスも活用しましょう。入れ歯の方も、入れ歯の清掃と粘膜のケアが重要です。
- 定期的な歯科受診: 自分では取り切れない歯石の除去や、虫歯・歯周病の早期発見・治療のために、定期的に歯科医院を受診しましょう。プロによるクリーニングや、個々に合った歯磨き指導を受けることも大切です。
- 舌の清掃: 舌の表面に付着した汚れ(舌苔)は口臭の原因になったり、細菌の温床になったりします。舌ブラシなどで優しく清掃しましょう。
- 保湿ケア: 口腔乾燥が気になる場合は、保湿ジェルやスプレーを使用したり、唾液腺マッサージ(後述の運動参照)を行ったりするのも良いでしょう。
2. 栄養:バランスの取れた食事を
- 偏食を避ける: 噛みにくいからといって柔らかいものばかり食べていると、栄養が偏り、さらに噛む力が衰える悪循環に。食品の硬さや大きさを工夫し、多様な食品を摂取するよう心がけましょう。
- タンパク質をしっかり摂る: 筋肉(舌や喉の筋肉も含む)を維持するために、肉、魚、卵、大豆製品などから良質なタンパク質を摂取しましょう。
- 歯周組織や全身の健康に良い栄養素: 論文では、歯肉の健康に良いとされる栄養素として、DHA(魚油)、ビタミンC・E、β-カロテン(緑黄色野菜)、カルシウム(牛乳・乳製品)、オメガ3脂肪酸(青魚など)などが挙げられています。抗酸化作用のある野菜や果物も積極的に摂りたいですね。
3. 運動:口と全身を動かす オーラルフレイル対策には、お口周りの運動と全身の運動の両方が重要です。
- 口腔周囲筋のトレーニング:
- 舌の運動: 舌を前後左右、上下に大きく動かす。舌で頬の内側を押す。舌を上あごに押し付ける(舌圧トレーニング)。
- 口唇の運動: 口を大きく開け閉めする。「イー」「ウー」と口を大きく動かす。唇をすぼめたり横に引いたりする。
- 頬の運動: 口を閉じて頬を膨らませたり、へこませたりする。
- 軟口蓋のトレーニング: 息を吹きかける練習(プローイング)など。 (論文には、歯科用ミラーなどを使った抵抗運動なども紹介されています)
- 全身運動:
- ウォーキング、軽い筋トレ、ストレッチなど、全身の筋肉を維持し、サルコペニアを予防するための運動も非常に重要です。
- 特に、息を吐きながら行う運動(呼気筋トレーニング)や、発声練習なども、間接的に嚥下機能に関わる筋肉を鍛える効果が期待できます。
栄養と運動は相互に影響しあうため、両方をバランス良く行うことが、より高い効果に繋がります。
地域で支えるオーラルフレイル対策
オーラルフレイル対策は、個人の努力だけでなく、地域全体で支えていく視点も重要です。
論文では、歯科医師が中心となりつつも、医師、看護師、栄養士、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、介護支援専門員(ケアマネージャー)、介護福祉士など、多職種が連携して、個々の高齢者の状態に合わせた口腔ケア、栄養指導、運動指導などを包括的に提供していく必要性が強調されています。
クリニックでの診療だけでなく、訪問診療や地域の介護予防教室などを通じて、オーラルフレイルの早期発見と介入の機会を増やしていくことが、超高齢社会である日本の大きな課題と言えるでしょう。
まとめ
今回は、「オーラルフレイル」について、その重要性、原因、対策、そして地域での取り組みについて解説しました。
- オーラルフレイルは、お口の些細な衰えであり、全身のフレイルの入口となる危険なサインです。
- 歯の喪失、歯周病、う蝕、口腔乾燥などが主な原因となります。
- 対策の基本は「口腔ケア」「栄養」「運動」。これらを継続することが重要です。
- 口腔機能は、適切なケアとトレーニングで維持・改善が可能です。
- オーラルフレイル対策には、歯科医師を中心とした多職種連携と地域でのサポートが不可欠です。
お口の健康は、美味しく食事を楽しみ、人と会話し、笑顔で過ごすといった、私たちのQOL(生活の質)の根幹を支えています。そして、それは全身の健康にも密接に繋がっています。「年のせい」と諦めずに、日々のセルフケアを大切にし、もし気になる症状があれば、早めに歯科医師や他の専門家に相談しましょう。
参考文献
笹本祐馬, 笹本恭子, 篠崎愛, 渋谷 麻希, 佐藤茂, 河野哲朗, 岡田裕之. オーラルフレイルと地域医療の役割. 国際抗老化再生医療学会雑誌. 2020;3:12-22.
健康・医学関連情報の注意喚起:
本記事は、オーラルフレイルに関する一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の診断や治療法を推奨するものではありません。 口腔内の問題や全身の健康状態については、必ず歯科医師または医師にご相談ください。