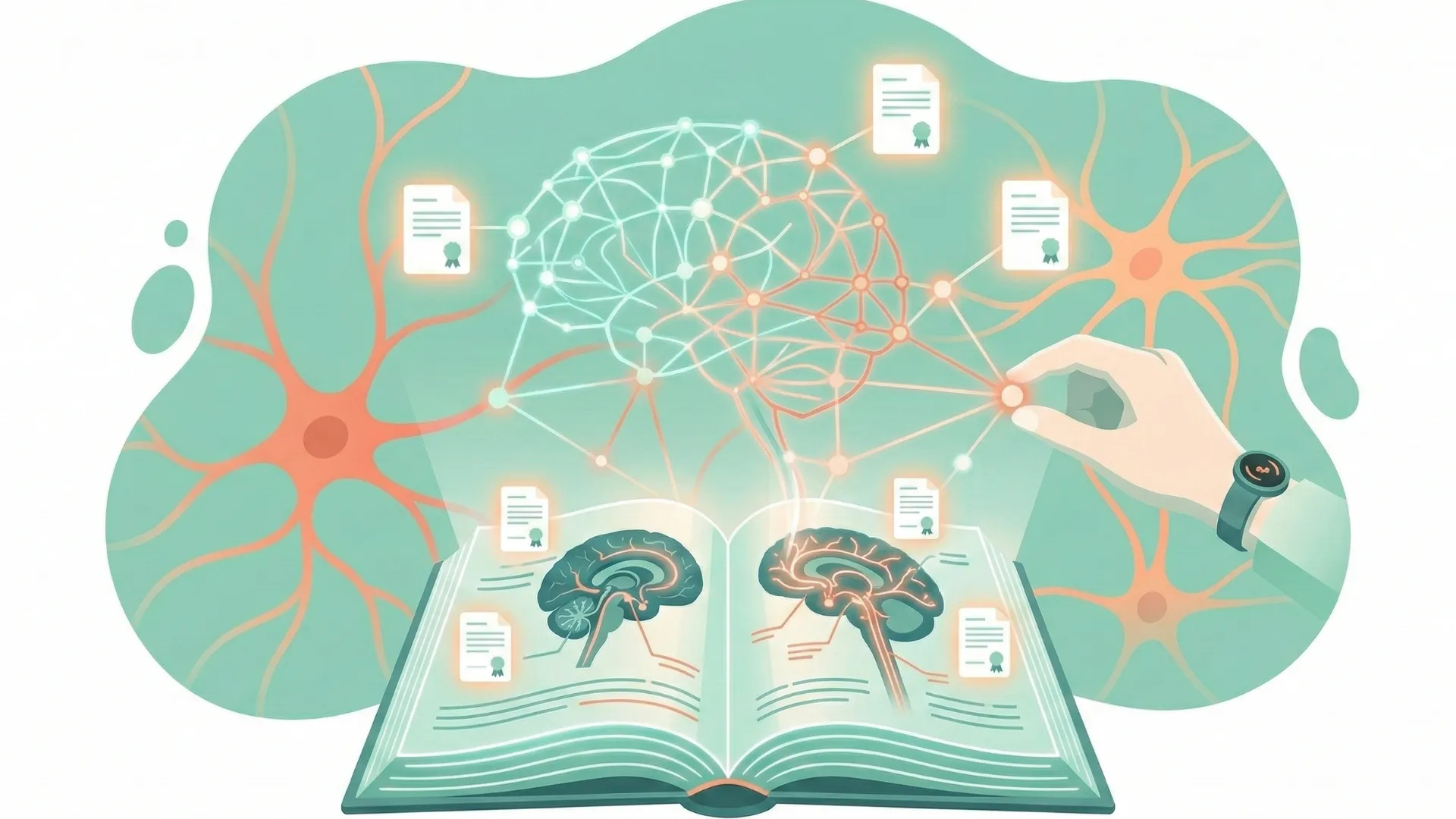「親にはいつまでも元気でいてほしい」
誰もがそう願っているはずです。そのために、「毎日ちゃんと散歩しているかな?」「塩分は摂りすぎていないかな?」と、親の健康を気遣っている方も多いのではないでしょうか。特に、日課のウォーキングや体操を欠かさない親御さんをお持ちなら、「うちの親は健康意識が高いから大丈夫」と安心しているかもしれません。
ですが、もしその安心が、大きな見落としに繋がっているとしたら…?
こんにちは。理学療法士のPTケイです。私自身、うつ病やベーチェット病といった心と体の不調と付き合いながら、日々患者さんと向き合っています。だからこそ、教科書通りの健康法だけでなく、日々の生活に潜む「見過ごされがちなリスク」に目を向けることの重要性を痛感しています。
実は、近年の研究で「たとえ毎日運動していても、”あること”をしていると、その効果が帳消しになりかねない」という、衝撃的な事実が明らかになってきました。
その”あること”とは、「座っている時間」です。
「え?座っているだけでしょう?疲れているんだから休むのは当たり前じゃないか」
そう思われるかもしれません。しかし、この「座りすぎ」という静かな習慣が、知らず知らずのうちに親御さんの心身を蝕み、深刻な健康リスクを高めている可能性があるのです。
この記事では、最新の研究論文に基づきながら、なぜ「座りすぎ」が危険なのか、そして、大切な親をそのリスクから守るために、私たちが今日から何ができるのかを、理学療法士として、そして一人の人間として、できるだけ分かりやすく、具体的にお伝えしていきます。「運動しているから大丈夫」という安心の陰に隠れた、本当のリスクに一緒に向き合っていきましょう。
研究紹介:日本の研究者が警鐘を鳴らす「座りすぎ」の脅威
まず、今回の記事の根拠となる研究をご紹介します。これは特定の実験を行ったものではなく、これまで世界中で行われてきた「高齢者の座りすぎ」に関する数多くの研究結果を、専門家がまとめた非常に信頼性の高いレビュー論文です。
2014年に日本で、早稲田大学のオカ コウイチロウ氏らが中心となった研究グループは、高齢者における「座りすぎ」の実態、健康への影響、そして対策の現状についてのレビュー論文を発表しました。その結果、高齢者の「座りすぎ」は、推奨される身体活動(ウォーキングなど)を行っているか否かに関わらず、総死亡リスクの増加や心身の健康悪化と関連する、新たな健康リスクであると報告しました。
つまり、「運動でプラスの健康貯金をしても、座りすぎによってマイナスの借金を重ねてしまい、結果的に健康状態が悪化する」という可能性を強く示唆しているのです。
この論文は、私たち理学療法士の間でも大きな話題となりました。リハビリで患者さんに運動を指導するだけでなく、退院後の「生活における座る時間」にも目を向けなければ、真の健康寿命の延伸には繋がらない、ということを改めて突き付けられたからです。
では、具体的にどのようなリスクが明らかになったのでしょうか。次の章から、論文で示された衝撃的なデータを、さらに詳しく掘り下げていきます。
運動しても帳消しにできない?論文で判明した「座りすぎ」3つの深刻なリスク
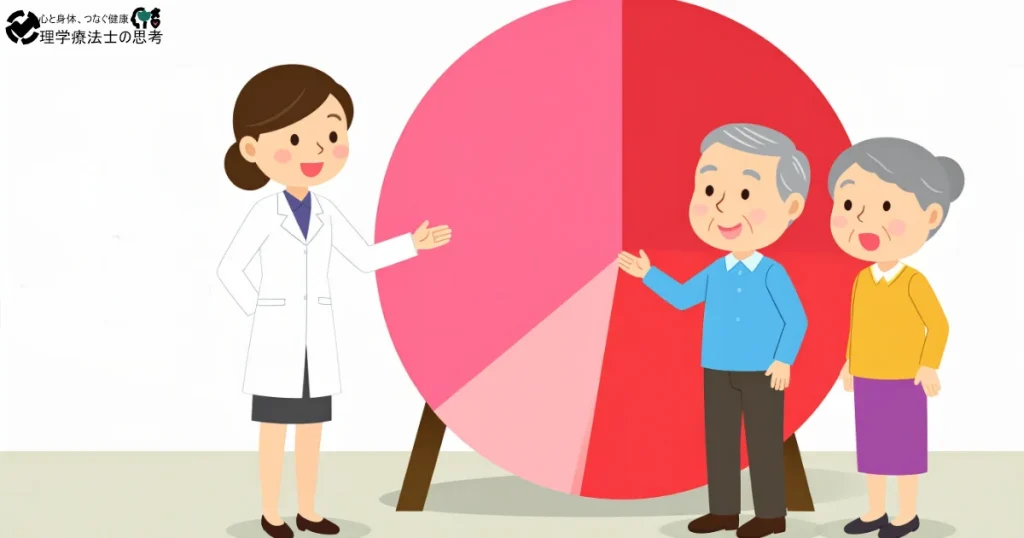
この論文では、世界中の研究を分析することで、「座りすぎ」が私たちの想像以上に深刻な影響を及ぼすことが明らかにされています。ここでは、特に重要な3つのリスクについて、具体的なデータを交えながら解説していきます。
1. 衝撃のデータ!「座りすぎ」は死亡リスクを最大1.65倍に高める
まず最も衝撃的なのが、座っている時間が長ければ長いほど、寿命そのものが短くなるという事実です。
スペインとオーストラリアの追跡調査が示す厳しい現実
この論文で紹介されている、非常に大規模で信頼性の高い二つの研究を見てみましょう。
一つ目は、スペインで行われた研究(Martínez-Gómez D, et al., 2013)です。この研究では、60歳以上の高齢者3,465人を平均9年間も追跡調査しました。その結果、1日の総座位時間が8時間未満の人たちに比べて、8時間以上座っている人たちは、総死亡リスク(あらゆる原因を含めた死亡リスク)が30%も高くなることが示されました。
- 研究デザイン: コホート研究(特定の集団を長期間追跡し、要因と結果の関連を調べる研究手法)
- 対象者: 60歳以上のスペイン在住高齢者 3,465名
- 追跡期間: 平均9.0年
さらに驚くべきは、オーストラリアの高齢女性を対象とした研究(Pavey TG, et al., 2012)の結果です。この研究では、6,656人の高齢女性を9年間追跡しました。
- 1日の総座位時間が4時間未満のグループに比べ、
- 8時間~11時間のグループでは、総死亡リスクが1.45倍
- 11時間以上のグループでは、総死亡リスクが1.65倍
と、座る時間が長くなるにつれて、階段を上るように死亡リスクが上昇していくことが明らかになったのです。
- 研究デザイン: コホート研究
- 対象者: オーストラリアの高齢女性 6,656名
- 追跡期間: 9年
11時間と聞くと非常に長く感じるかもしれませんが、朝起きて新聞を読み、朝食後しばらくテレビを見て、昼食後もソファでうたた寝、夜はまたテレビ…。こうした生活を送っていると、案外あっという間に達してしまう時間です。
「8時間」が分かれ道?あなたの親は大丈夫?
これらの研究から、「1日8時間」というのが、健康リスクが大きく跳ね上がる一つのボーダーラインである可能性が見えてきます。
「仕事で8時間座りっぱなし」というのは現役世代では珍しくありませんが、定年退職後の高齢者においても、知らず知らずのうちにこの時間を超えているケースは少なくないのです。
では、なぜただ座っているだけで、これほどまでに死亡リスクが高まってしまうのでしょうか。
なぜ座るだけでリスクが上がるのか?血流と代謝の悪化がカギ
理学療法士の視点から解説すると、座り続けることの最大の問題点は「重力に抗う筋肉の活動が極端に少なくなること」です。
立っている時、私たちの身体、特に足の筋肉は、倒れないように常に微細な活動を続けています。この筋肉の収縮と弛緩がポンプの役割(筋ポンプ作用)を果たし、心臓から遠い足の血液をスムーズに上半身へと送り返しているのです。
しかし、座っている状態では、この筋ポンプ作用がほとんど働きません。その結果、
- 全身の血流が悪化する: 足に血液が滞り、むくみや冷えの原因になるだけでなく、血栓(血の塊)ができやすくなります。この血栓が肺や脳に飛ぶと、エコノミークラス症候群(急性肺血栓塞栓症)や脳梗塞といった命に関わる病気を引き起こす可能性があります。
- 糖や脂肪の代謝が低下する: 筋肉は体内で最も多くの糖質を消費する臓器です。しかし、筋肉の活動が低下すると、血液中の糖がエネルギーとして使われにくくなり、血糖値が上がりやすくなります。これが、次に解説するメタボリックシンドロームや糖尿病のリスクを高める大きな原因となるのです。
つまり、座りすぎは、運動不足とはまた別のメカニズムで、全身の血管や代謝システムを静かに、しかし着実に蝕んでいくのです。
2. 見えないところで蝕まれる身体。メタボリックシンドロームとの深い関係
「最近、親のお腹周りが気になる…」
そう感じている方もいるかもしれません。実はそのポッコリお腹も、「座りすぎ」が原因の一つである可能性が高いのです。
テレビ視聴時間が長いほど危険?具体的なデータで解説
先ほどの論文では、座りすぎとメタボリックシンドロームの関連についても、複数の研究を挙げて警鐘を鳴らしています。
用語解説:メタボリックシンドローム
内臓脂肪の蓄積に加えて、高血圧、高血糖、脂質異常症(中性脂肪が多い、または善玉コレステロールが少ない)のうち、2つ以上を合併した状態のこと。一つ一つの症状は軽くても、重なると動脈硬化を急速に進行させ、心筋梗塞や脳卒中といった命に関わる病気のリスクが格段に高まります。
オーストラリアで行われた研究(Gardiner PA, et al., 2011)では、60歳以上の高齢者を対象に、テレビの視聴時間とメタボリックシンドロームの関連を調査しました。その結果は非常に明確でした。
1日にテレビを1.14時間未満しか見ないグループと比べて、3時間以上見ているグループは、メタボリックシンドロームを保有している割合が、男女ともに1.42倍も高かったのです。
- 研究デザイン: 横断研究(ある一時点の健康状態と要因の関連を調べる研究手法)
- 対象者: 60歳以上のオーストラリア在住高齢者 1,958名(男性896名、女性1,062名)
さらにこの研究では、テレビ視聴時間だけでなく、1日の総座位時間についても分析しています。総座位時間が3.43時間未満のグループに比べ、6.65時間以上のグループは、メタボリックシンドロームの保有率が男性で1.57倍、女性で1.56倍も高くなることが分かりました。
「運動しているから大丈夫」は間違い!独立したリスクとしての「座りすぎ」
ここで非常に重要なポイントがあります。日本の研究(Inoue S, et al., 2012)では、この「座りすぎ」のリスクが、運動習慣の有無とは独立している可能性を示しています。
この研究では、65歳~74歳の高齢者1,806名を、テレビの視聴時間(長い/短い)と、推奨される身体活動量(週150分以上の運動)を満たしているか(十分/不十分)で4つのグループに分けて比較しました。
その結果、「テレビ視聴が長く、運動も不十分なグループ」と比べて、「テレビ視聴が長いが、運動は十分に行っているグループ」でも、過体重・肥満の割合はわずか7%しか低くなりませんでした。
一方で、「テレビ視聴が短く、運動は不十分なグループ」は、肥満の割合が42%も低かったのです。
- 研究デザイン: 横断研究
- 対象者: 65~74歳の日本の地域在住高齢者 1,806名
これは、私たちに衝撃的な事実を突きつけます。
たとえ毎日1時間のウォーキング(運動十分)を頑張っても、残りの多くの時間をテレビの前で座って過ごしている(テレビ視聴が長い)と、その運動効果が大きく損なわれてしまう可能性があるのです。
運動による「健康へのプラス効果」と、座りすぎによる「健康へのマイナス効果」は、単純に足し引きで相殺できるものではない、ということです。それぞれが独立したリスクとして、私たちの体に影響を与えているのです。
3. 体だけでなく心も蝕む…認知機能と心の健康への悪影響
「座りすぎ」の影響は、身体的なものに留まりません。実は、私たちの脳の働き(認知機能)や心の健康にまで、深刻な影を落とすことが分かってきています。
「テレビを見る」と「パソコンを使う」で影響が違う?驚きの研究結果
「うちの親はテレビばかり見て、頭を使わないから心配だ」
「最近はパソコンで調べ物をしたり、ゲームをしたりしているから、まだボケないかな」
このように、同じ「座る」という行為でも、その内容によって脳への影響は違うのではないか、と感じている方もいるかもしれません。その直感は、ある意味で正しいようです。
フランスで行われた研究(Kesse-Guyot E, et al., 2012)では、高齢者の座位行動の種類と認知機能の関連を調べました。
その結果、
- テレビの視聴時間が長い人ほど、物事を計画し、順序立てて実行する能力である「実行機能」が低い傾向にありました。
- 一方で、パソコンを1日1時間以上利用する人は、パソコンを全く利用しない人に比べて、言葉を記憶する「言語記憶」や「実行機能」が高いという結果でした。
- 研究デザイン: 横断・縦断研究(複数時点でデータをとり、変化を追う研究手法)
- 対象者: フランス在住の高齢者 2,179名
この結果だけを見ると、「テレビはダメで、パソコンなら良いのか」と考えてしまいがちです。しかし、この研究には続きがあります。追跡調査を行うと、パソコンの利用時間が増加した人は、利用時間が減少した人に比べて、言語記憶も実行機能も、逆に有意に低下してしまったのです。
これは非常に示唆に富む結果です。
テレビをぼーっと受動的に見続けることは、脳への刺激が少なく、認知機能の低下に繋がりやすいのかもしれません。一方で、パソコンでの調べ物やゲームは、能動的に頭を使うため、適度であれば脳に良い刺激となる可能性があります。
しかし、それも度が過ぎれば、運動不足や社会的な孤立を招き、結果的に認知機能を低下させる悪影響の方が上回ってしまう、ということを示しているのではないでしょうか。
ぼーっとする時間が増えた?それは「座りすぎ」のサインかも
さらに、別の研究(Balboa-Castillo T, et al., 2011)では、座っている時間の長さが、健康関連QOL(生活の質)にどう影響するかを調べています。
その結果、余暇時間に座って過ごす時間が長い人ほど、
- 体の痛みを感じやすい
- 活力(バイタリティ)が低い
- 社会生活機能(他者との交流など)が低い
- 心の健康状態が悪い
といった、身体的な側面だけでなく、精神的な健康度が低いことと強く関連していることが明らかになりました。
用語解説:健康関連QOL (Quality of Life)や加齢が、身体的、精神的、社会的な側面にどの程度影響しているかを測る指標。「自分自身の健康状態にどれだけ満足して生活できているか」を示すものです。
理学療法士として多くの高齢者の方と接していると、「何もやる気が起きない」「外に出るのが億劫だ」といった声をよく耳にします。こうした意欲の低下(アパシー)は、うつ病の入り口となることもあり、非常に注意が必要です。
そして、この意欲の低下と「座りすぎ」は、「卵が先か、鶏が先か」という悪循環に陥りやすい関係にあります。
「意欲が湧かないから、つい座ってしまう」
→「座っている時間が長くなることで、さらに血流が悪化し、脳への刺激も減る」
→「結果として、ますます意欲が低下し、身体機能も衰える」
→「外に出るのがもっと億劫になり、さらに座る時間が増える…」
この負のスパイラルを断ち切ることが、介護予防の観点からも極めて重要なのです。
あなたの「座りすぎリスク」をチェック!生活習慣シミュレーター
ここまで読んで、「うちの親は、一体どのくらいのリスクがあるんだろう?」と不安に思った方も多いかもしれません。そこで、あなたの、あるいはご家族の1日の生活習慣から、おおよその「座位時間」と「リスクレベル」を判定できる簡単なシミュレーターをご用意しました。
ぜひ、下の項目に1日の平均的な時間を入力して、「判定する」ボタンを押してみてください。
【あなたの座りすぎリスク判定アプリ】
1日の生活時間シミュレーター
あなたの1日の平均的な活動時間を入力してください。(合計が24時間になるように調整してください)
今日からできる!親の「座りすぎ」を防ぐための具体的アクションプラン

さて、リスクが分かったところで、次はいよいよ具体的な対策です。
「座る時間を減らせと言っても、何をすればいいの?」
「運動が苦手な親に、無理強いはしたくない…」
ご安心ください。必要なのは、ハードなトレーニングではありません。日常のちょっとした意識と工夫で、「座りっぱなし」を「ちょこっと動く」に変えることが可能です。理学療法士の視点から、今日からすぐに実践できる具体的なアクションプランを提案します。
ステップ1:まずは「座る時間」の見える化から始めよう
対策の第一歩は、現状把握です。先ほどのシミュレーターも役立ちますが、より正確に把握するために、一度、親御さん(あるいはご自身)の1日の生活をメモに書き出してみることをお勧めします。
- 何時に起きて、何時に寝るか?
- テレビは何時から何時まで見ているか?
- 食事にかける時間は?
- 趣味の時間は?その時、座っているか、立っているか?
このように時間を書き出してみると、「意外とこんなに座っていたんだ!」という驚きの発見があるはずです。この「気づき」こそが、行動を変えるための最も重要なモチベーションになります。タイマー機能のついたキッチンタイマーやスマートスピーカーを活用し、「1時間経ったら音を鳴らす」設定にするのも、座りっぱなしを防ぐ良い方法です。
ステップ2:「ついでに動く」を合言葉に!生活の中のちょこっと運動
「さあ、運動するぞ!」と意気込む必要はありません。生活の中の「ついで」の動作を増やすだけで、座位時間は劇的に減らせます。
- CM中に立ち上がる、足踏みをする
テレビは最大の「座りすぎ誘発装置」ですが、見方を変えれば絶好の「運動のきっかけ」になります。30分の番組なら、5〜6回はCMが入ります。その度に立ち上がって、軽く足踏みをしたり、アキレス腱を伸ばしたりするだけで、血流は大きく改善されます。これを習慣化するだけで、1日に30分以上の「脱・座りすぎ時間」を生み出せます。 - 電話は歩きながらかける
友人や家族との長電話は、格好の「ながら運動」のチャンスです。受話器を片手に、部屋の中をゆっくりと歩き回りながら話してみましょう。話に夢中になっているうちに、気づけばかなりの歩数を稼げているはずです。 - 1時間に1回は用事を作る
「1時間経ったら、必ず席を立ってコップ1杯の水を飲みに行く」「トイレに行く」など、強制的に立ち上がるための「自分ルール」を作りましょう。特に水分補給は、脱水予防や血流改善にも繋がるため一石二鳥です。 - 洗濯物は立ったまま畳む
床に座って洗濯物を畳んでいませんか?アイロン台やテーブルの上などを活用し、立ったまま畳むようにするだけで、20〜30分の座位時間を削減できます。
ステップ3:環境を変えれば行動が変わる!座りすぎを防ぐ部屋づくり
人の行動は、意志の力だけでなく、環境に大きく左右されます。座りたくなる環境を、少しだけ「立ちたくなる」環境に変えてみましょう。
- テレビのリモコンを少し離れた場所に置く
ソファに座ったまま、手の届く範囲にリモコンを置くのはやめましょう。チャンネルを変えたり音量を調整したりするたびに、一度立ち上がって数歩歩く。この小さな手間が、座りっぱなしを防ぎます。 - よく使うものは、あえて分散させて置く
例えば、本や雑誌、新聞、老眼鏡などを一箇所にまとめず、部屋の別々の場所に置いてみましょう。「あれを取りに行く」という小さな目的が、自然と立ち上がるきっかけを生み出します。 - スタンディングデスクを取り入れてみる
これは少しハードルが高いかもしれませんが、新聞を読んだり、書き物をしたりする際に、高さのあるカウンターやテーブルを活用するのも一つの手です。ずっと立っている必要はありません。「30分座ったら、10分立つ」といったサイクルを試してみるだけでも、体への負担は大きく変わります。
ステップ4:家族の協力が最大のカギ!一緒に楽しむ健康習慣

高齢者の方が一人で生活習慣を変えるのは、時に難しいこともあります。そこで重要になるのが、私たち家族のサポートです。
- 「座りすぎは体に悪いらしいよ」と情報共有する
この記事を見せながら、「こんな研究結果があるんだって。ちょっと気をつけてみない?」と、命令ではなく、相談ベースで話を持ちかけてみましょう。リスクを共有することで、本人の意識も高まります。 - 一緒に「ちょこっと運動」を楽しむ
実家に帰省した際には、「CMになったら一緒に足踏みしよう!」と誘ってみたり、食後に5分だけ一緒に散歩に出かけたりするのも良いでしょう。一人では続かなくても、誰かと一緒なら楽しく続けられることは多いものです。 - プレゼントを工夫する
もし何かプレゼントをする機会があれば、室内で履ける少しクッション性の良いシューズや、万歩計(活動量計)などを贈るのもお勧めです。新しいアイテムは、行動を変える良いきっかけになります。
大切なのは、完璧を目指さないことです。まずは「昨日より5分でも座る時間を減らす」という小さな目標からで構いません。その小さな成功体験の積み重ねが、やがて大きな健康資産となって返ってくるはずです。
まとめ
今回は、運動習慣があっても見過ごされがちな「座りすぎ」という隠れたリスクについて、論文を基に詳しく解説してきました。最後に、今日の重要なポイントをもう一度振り返っておきましょう。
- 「座りすぎ」は独立した健康リスクである: たとえ毎日運動していても、1日の大半を座って過ごしていると、その効果が帳消しになる可能性があります。研究では、1日8時間以上の座位行動で死亡リスクが30%、11時間以上では1.65倍にも高まることが示されています。
- 身体だけでなく心にも影響する: 座りすぎは、血流や代謝を悪化させ、メタボリックシンドロームや肥満のリスクを高めるだけでなく、認知機能の低下や意欲の減退といった、心の健康にも深刻な影響を及ぼす可能性があります。
- 対策は「ちょこっと動く」意識から: ハードな運動は必要ありません。「CM中に立つ」「電話は歩きながら」といった、日常生活の中の小さな工夫で座位時間を減らすことが、健康寿命を延ばすための最も効果的で現実的な第一歩です。
私自身、理学療法士として多くの患者さんと接する中で、退院時にどれだけ身体機能が回復しても、ご自宅での生活が座りっぱなしに戻ってしまえば、あっという間に心身の活力が失われていくケースを何度も見てきました。
この記事を読んで、「うちの親、危ないかも…」と少しでも感じたなら、それが行動を起こす絶好のタイミングです。まずは今日の夕食後、親子でこの記事について話してみることから始めてみませんか?「座る時間を少しだけ減らしてみようか」その一言が、大切な親御さんの未来を、より明るく、健康的なものに変えるきっかけになるかもしれません。
参考文献
岡 浩一朗, 柴田 愛, 石井 香織, 宮脇 梨奈. (2014). 高齢者における座り過ぎ ―その実態と健康影響および座り過ぎ対策の現状―. ストレス科学研究, 29, 20-27.
健康・医学関連情報の注意喚起
本記事は、「座りすぎ」に関する一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の医学的アドバイスを提供するものではありません。
心臓病や関節疾患など、特定の疾患の診断や治療については、必ず主治医や理学療法士などの医療従事者にご相談ください。