 PTケイ
PTケイこんにちは。理学療法士のPTケイです。…おや、こんにちはAさん。
少し顔色が優れないようですが、どうかしましたか?



あ、ケイさん…。こんにちは。実は最近、よく眠れていなくて…。



そうでしたか。何か睡眠のために試していることはあるんですか?



はい。
よく言われるように、寝る前にリラックスできる音楽を聴いているんですけど…。
なんだか、あんまり意味がない気がして。むしろ「これを聴けば眠れるはず!」って思うと、逆に目が冴えてしまうことさえあるんです。



なるほど…。
音楽を聴いているのに、かえって眠れなくなってしまう、と。



そうなんです。「本当にこの聴き方で合ってるのかな?」って、だんだん不安になってきちゃって。



その感覚、非常によくわかります。
そしてAさん、その「かえって目が冴えてしまう」という感覚は、気のせいではないかもしれませんよ。
実は、科学的に見ても、それは起こりうることなんです。



え、そうなんですか!?



はい。
最近のある研究で、音楽と睡眠の関係について、私たちの常識を少し見直す必要があるような、興味深い事実が明らかになりました。
簡単に言うと、音楽の効果を最大限に引き出すためには、「ただ聴くだけ」では不十分で、ある”個人の特性”に合わせた科学的な聴き方がある、ということです。



科学的な聴き方…。なんだか難しそうですね。



ご安心ください。
決して難しい話ではありませんよ。
この記事を最後まで読んでいただければ、その「科学的な聴き方」とは何かが分かり、Aさんが今夜からすぐに実践できる、ご自身の睡眠を改善するための具体的なヒントが手に入ります。



本当ですか!ぜひ、教えてください!



もちろんです。
それでは、あなたの睡眠音楽の常識をアップデートする、脳科学の世界へご案内しますね。
この記事でわかること(1分で解説)
- 音楽を聴くと、あなたの脳内で具体的に何が起こっているのか
- 脳波レベルで見る「良い睡眠」と、音楽がそれをどう作り出すか
- 音楽で深く眠れる人とそうでない人を分ける、たった一つの心理的特性
- 論文の全データから導き出した、あなた専用の「安眠音楽ToDoリスト」
それでは、あなたの睡眠を次のレベルへ引き上げる、科学の世界へご案内します。
研究紹介
今回深く掘り下げるのは、私たちの素朴な疑問に、脳科学の視点から鋭く切り込んだこちらの研究です。
2019年にイギリスの科学雑誌『Scientific Reports』でマレン・ジャスミン・コルディ氏らは、リラックスできる音楽が健康的な睡眠に及ぼす影響についての実験的研究を行いました。その結果、音楽は主観的な睡眠の質を改善し、特に「暗示性」が低い参加者において、客観的な睡眠の質(深い睡眠)を向上させたと報告しました。
なぜ音楽で眠くなる?脳の中で起きている3つの変化
「音楽を聴くとリラックスする」というのは感覚的にわかりますが、私たちの脳の中では、具体的にどのような変化が起きているのでしょうか。
この研究では、睡眠ポリグラフ(PSG)という専門機器で脳波を測定し、そのメカニズムを明らかにしました。
【変化①】脳の”アイドリング”を止め、スムーズに眠りへ誘う
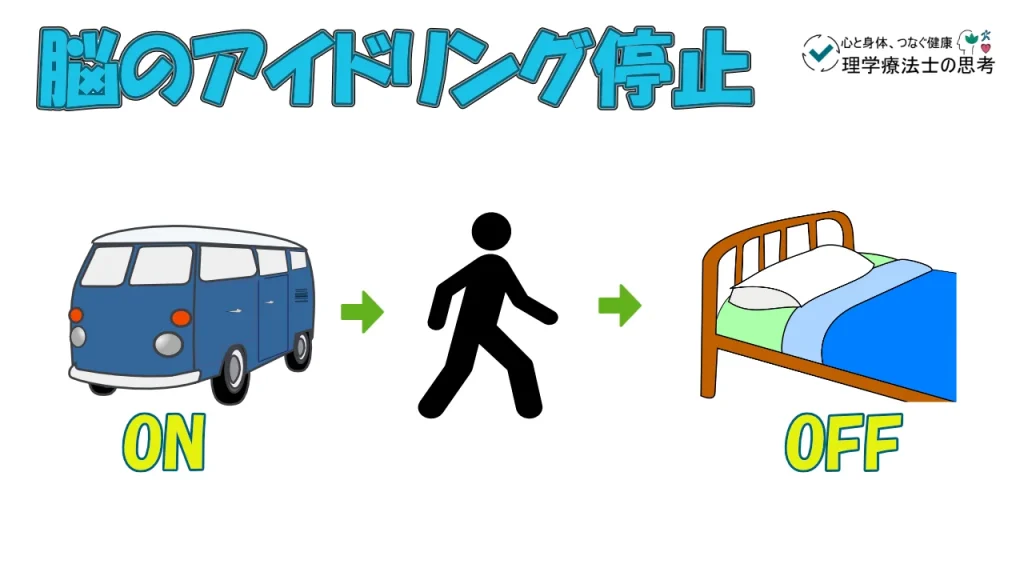
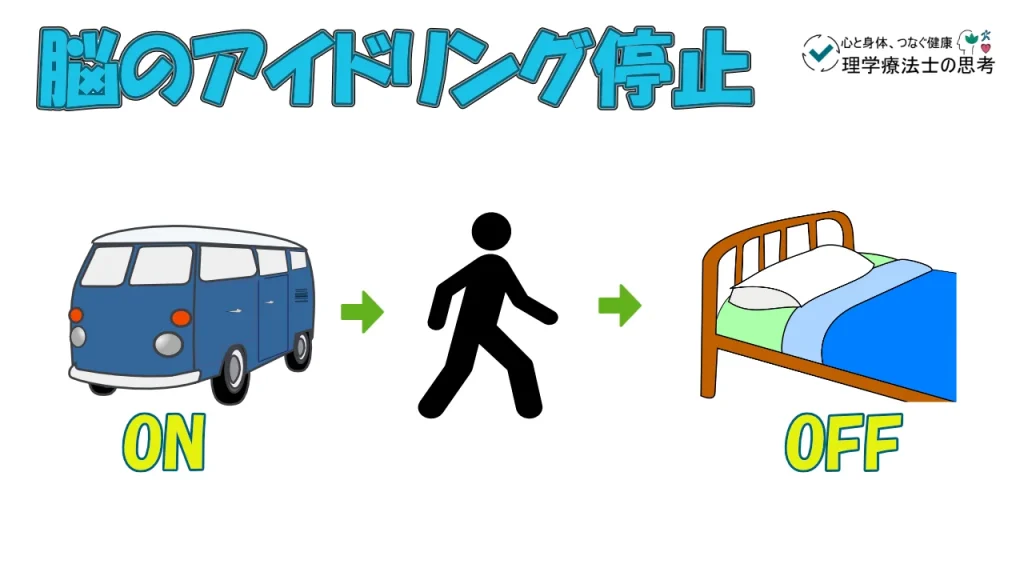
ベッドに入っても、仕事のことや明日の予定が頭を巡ってなかなか眠れない…。これは脳がまだ興奮状態で、アイドリングを続けているような状態です。
研究の結果、音楽を聴いた参加者は、脳が本格的な睡眠に入る前の「うとうと」状態、専門的には「睡眠段階N1」の時間が有意に短縮されることがわかりました。
これは、音楽が脳の不要なアイドリングを鎮め、“電源オフ”の状態、つまり本当の睡眠へとスムーズに移行する手助けをしてくれることを意味します。
音楽は、覚醒と睡眠の間のスイッチを、スムーズに切り替えてくれる存在なのです。
【変化②】脳を”大掃除”する深い眠りを、質・量ともに高める


睡眠の目的は、単に体を休ませるだけではありません。脳の疲労を回復させ、記憶を整理する「脳の大掃除」の時間でもあります。この大掃除が最も活発に行われるのが、「徐波睡眠(SWS)」と呼ばれる最も深い眠りの段階です。
この研究では、特定の条件を満たした人々において、音楽を聴くことでこの「徐波睡眠」の時間が平均で46%も増加しました。(この条件については後ほど詳しく解説します。)
さらに、論文の本文を詳しく見ると、脳波の「質」にも変化が見られました。
音楽を聴いた後の睡眠では、「SWA/ベータ比」という数値が上昇していました。
SWA/ベータ比とは?
脳波の中でも、深いリラックス状態を示すゆっくりとした波(SWA)と、覚醒や興奮を示す速い波(ベータ波)の比率のこと。この数値が高いほど、脳がしっかりと休息できている「質の高い睡眠」とされています。
つまり、音楽は深い睡眠の「時間(量)」を増やすだけでなく、その「質」をも高めてくれる可能性が示されたのです。
【変化③】脳の”過剰な警戒モード”を解除する
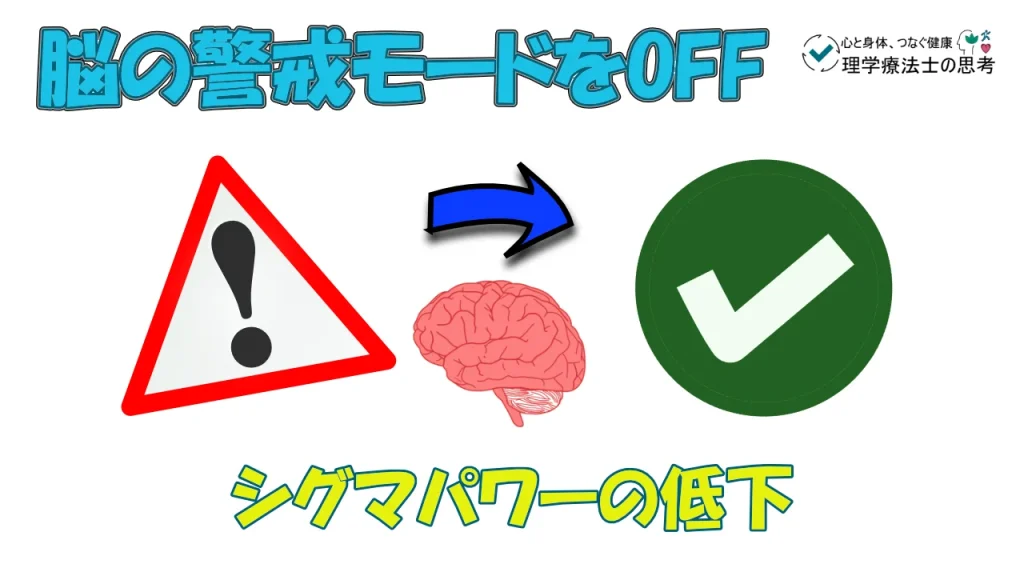
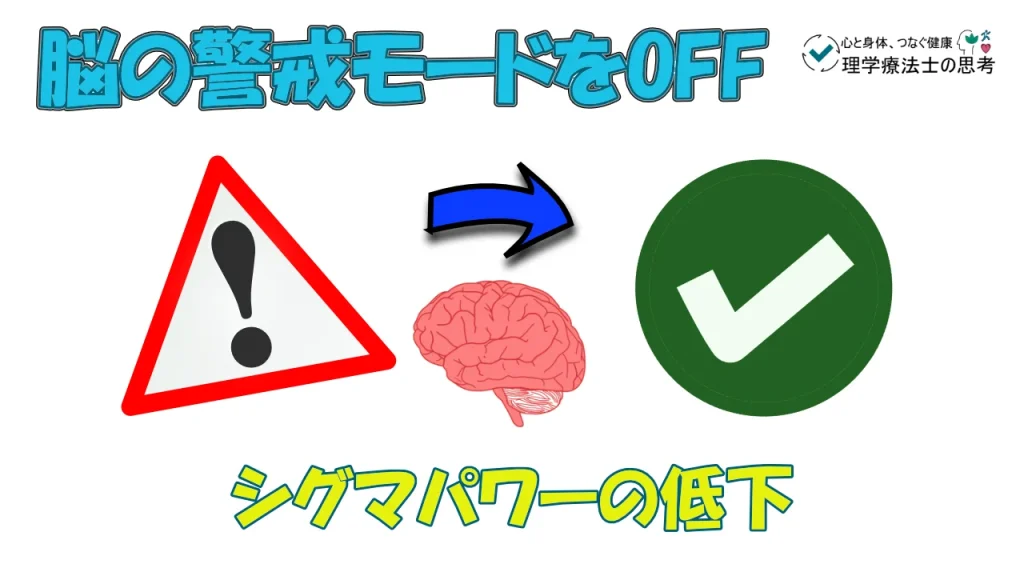
論文の本文には、もう一つ興味深いデータがあります。それは「シグマパワー」の低下です。
シグマパワーとは?
睡眠中の脳波に含まれる特定の周波数帯域(11-15Hz)の強さのこと。
睡眠中の記憶の定着などに関わるとされていますが、一方で過剰な脳活動の指標となることもあります。
研究では、音楽を聴いた後の睡眠で、このシグマパワーが低下する傾向が見られました。これは、音楽が脳の過剰な情報処理や”警戒モード”を鎮め、より深く安定した休息状態へと導いている可能性を示唆しています。
日中のストレスや情報過多で脳が疲れ切っている現代人にとって、音楽は脳を強制的にリラックスさせるスイッチの役割を果たしてくれるのかもしれません。
【重要】音楽の効果を最大化する”たった一つ”の条件
さて、ここまで読むと「音楽はすごい!」と感じるかもしれません。しかし、この研究の最も重要な発見は、これらの効果、特に「深い睡眠を増やす」という強力な効果が、すべての人に平等に現れるわけではないという点です。
効果を分けるたった一つの条件、それはあなたの「暗示性」でした。
あなたはどっち?効果を分ける「暗示性」とは
暗示性 (Suggestibility)
外部からの言葉や情報(暗示)によって、個人の感覚や思考、行動が影響を受ける度合いのこと。例えば、人から「これは効くよ」と言われたものを素直に信じやすい人は「暗示性が高い」、まず自分で事実を確認したい人は「暗示性が低い」傾向があります。
研究では、参加者をこの「暗示性」によって高低2つのグループに分け、脳波の変化を比較しました。
その結果は、研究者たちも「予想とは逆だった」と述べるほど衝撃的なものでした。
深い睡眠(徐波睡眠)が46%も増加し、睡眠の質(SWA/ベータ比)が向上したのは、すべて「暗示性が低い」グループの人々だったのです。
研究者が驚いた「逆説的な結果」の真相
なぜ、「これは睡眠に良い音楽だ」という情報を信じやすいはずの「暗示性が高い」人々よりも、客観的・批判的な「暗示性が低い」人々のほうが、劇的な効果を得られたのでしょうか。
論文の考察には、次のような可能性が示唆されています。
- 「言葉」からの解放: 暗示性が低い人は、言葉による直接的な指示やコントロールを好まない傾向があるかもしれません。「リラックスしなさい」と言われるよりも、言語を介さない音楽の響きに、ただただ身を委ねる方が、何の抵抗もなく心身を解放できた可能性があります。
- 「期待」というプレッシャー: 逆に暗示性が高い人は、「この音楽で眠らなければ」「リラックスしなければ」という期待や情報そのものが、無意識のプレッシャーとなり、かえって脳の活動を高めてしまったのかもしれません。
この結果は私たちに重要な教訓を与えてくれます。それは、最高の睡眠を得るための音楽とは、「効果を期待して聴く」ものではなく、「ただ心地よさに身を委ねる」ものであるということです。
今夜からできる!科学的根拠に基づく安眠音楽ToDoリスト
この研究結果を踏まえて、あなたの睡眠の質を最大化するための具体的なアクションプランを3つのステップでご紹介します。
Step1: 自分のタイプを知る
まずは、自分がどちらのタイプに近いかを知ることが第一歩です。下のチェックリストで、あなたの傾向を確認してみましょう。
あなたの「暗示性」傾向チェック
自分に近いと思う項目にチェックを入れてください。
Step2: 最適な音楽を選ぶ
- 歌詞のない曲を選ぶ: 脳が言葉を処理するのを防ぎ、リラックスに集中させます。
- テンポはゆっくり: 人間の心拍数に近いBPM60~80程度の曲が、心身を落ち着かせます。
- 音量の変化が少ない曲: 急な音の変化は脳を覚醒させてしまいます。一定の音量で流れる曲を選びましょう。
- 自然音も効果的: 波の音、雨音、川のせせらぎなど、規則的で心地よいゆらぎを持つ自然音も非常におすすめです。
Step3: 「聴き方」を最適化する
- タイミング: 就寝の15~30分前から聴き始めましょう。
- 音量: 「聞こえるか聞こえないか」くらいの、ごく小さな音量に設定します。
- タイマー: 30~60分程度で自動的に切れるようにスリープタイマーを設定し、睡眠の途中で音が邪魔にならないようにしましょう。
- 最も重要な心構え:
- 暗示性が低いタイプの方: 「眠るための音楽」と意識せず、ただの「心地よいBGM」として、音の響きそのものに身を任せてみてください。
- 暗示性が高いタイプの方: 音楽に加えて、アロマや間接照明など、「これで絶対リラックスできる」と思える環境を整えることが、相乗効果を生みます。
読者の学びを促進するQ&A
論文のさらに詳しい内容について、気になる疑問にお答えします。
- 論文に「音楽を聴いた後の方が記憶力が低下した」という記述がありましたが、本当ですか?
-
非常に鋭いご質問です。
確かに、この研究で行われた単語のペアを覚える記憶テスト(PAL)では、音楽を聴いた後の睡眠の方が、わずかに成績が低下するという結果が出ました。
しかし、これは非常に僅かな差であり、研究者たちも「不可解である」として明確な結論を出していません。
深い睡眠は記憶の定着に重要であるため、この結果は他の研究とは異なるものです。
この昼寝研究の特殊な条件下での結果である可能性が高く、現時点で「音楽が記憶に悪い」と結論づけるのは早計です。
むしろ、深い睡眠が増えることによる長期的なメリットの方が大きいと考えられます。
- 自分の好きな音楽(ロックやポップスなど)ではダメなのでしょうか?
-
リラックス効果が最優先なので、テンポが速かったり歌詞が感情を揺さぶったりする曲は、交感神経を刺激してしまい、入眠儀式としては逆効果になる可能性が高いです。
好きな音楽は日中の気分転換などに活用し、睡眠前は脳を鎮めることに特化した音楽を選ぶことを強くお勧めします。
ただし、あなたにとってその曲が「絶対的な安心感」をもたらすのであれば、試してみる価値はあるかもしれません。
まとめ
今回は、音楽と睡眠の関係を脳科学の視点から解き明かした研究を元に、本当に効果的な音楽の活用法について深掘りしました。
- 音楽は脳を「睡眠モード」に切り替える:脳のアイドリング(N1睡眠)を止め、深い睡眠(徐波睡眠)の質と量を高め、過剰な警戒モード(シグマパワー)を解除する働きがあります。
- 効果の鍵は「暗示性」:特に、客観的で自分のペースを好む「暗示性が低い」人は、音楽の恩恵を最大限に受け、深い睡眠が劇的に増加する可能性があります。
- 「期待せず、身を委ねる」が最高の聴き方:「眠らなければ」という意識を手放し、ただ心地よい音の響きに体を預けることが、脳を真のリラックスに導く秘訣です。
今日の情報が、あなたの睡眠の質を根本から見直し、明日への活力を取り戻すきっかけとなれば、これ以上嬉しいことはありません。
参考文献
Cordi, M. J., Ackermann, S., & Rasch, B. (2019). Effects of relaxing music on healthy sleep. Scientific Reports, 9(1), 9079.
健康・医学関連情報の注意喚起
本記事は、睡眠と音楽に関する一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の医学的アドバイスを提供するものではありません。
不眠症などの診断や治療については、必ず医療従事者にご相談ください。

