 Aさん
Aさんはぁ…今日も全然寝付けなかったな。明日は早番なのに、体が全然休まらないよ…。



わかる…。羊を数えても、ホットミルクを飲んでもダメ。逆に目が冴えちゃって。もうどうしたらいいのか…。



お二人とも、お疲れ様です。そのお悩み、本当によくわかります。
実はその『寝つけない』原因、体温のコントロールにあるのかもしれませんよ。



え、体温ですか?寒いから眠れない、というのはわかるのですが…。



ええ。でも実は、『体を温める』ことが、逆に体の中心部の温度を下げて、深い眠りを誘うという、ちょっと意外なメカニズムが科学的に明らかになっているんです。
この記事を読めば、あなたのその寝付けない悩みの原因と、明日からできる具体的な対策がわかります。
一緒に、質の高い睡眠を取り戻しましょう!
1分でわかる要約
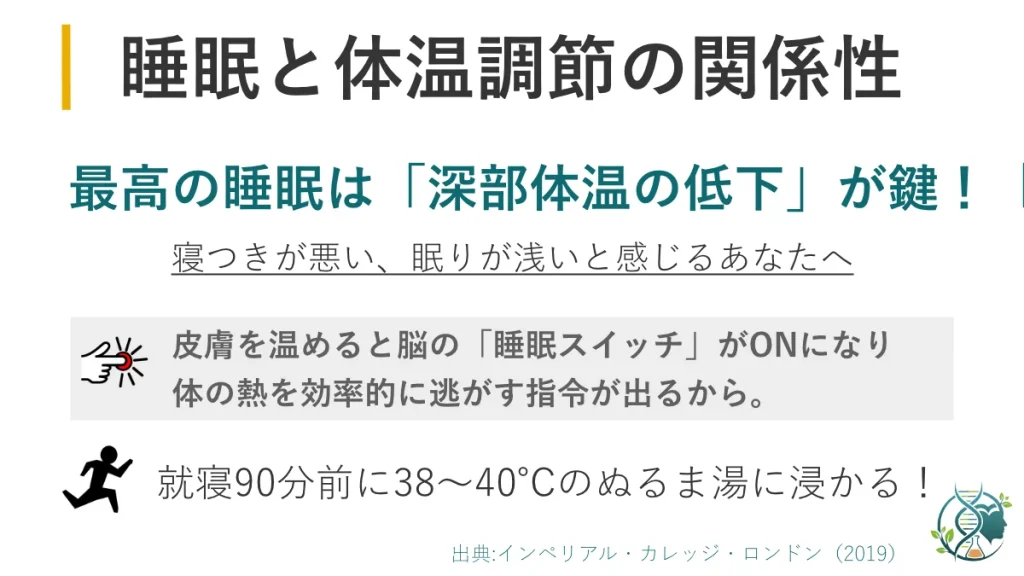
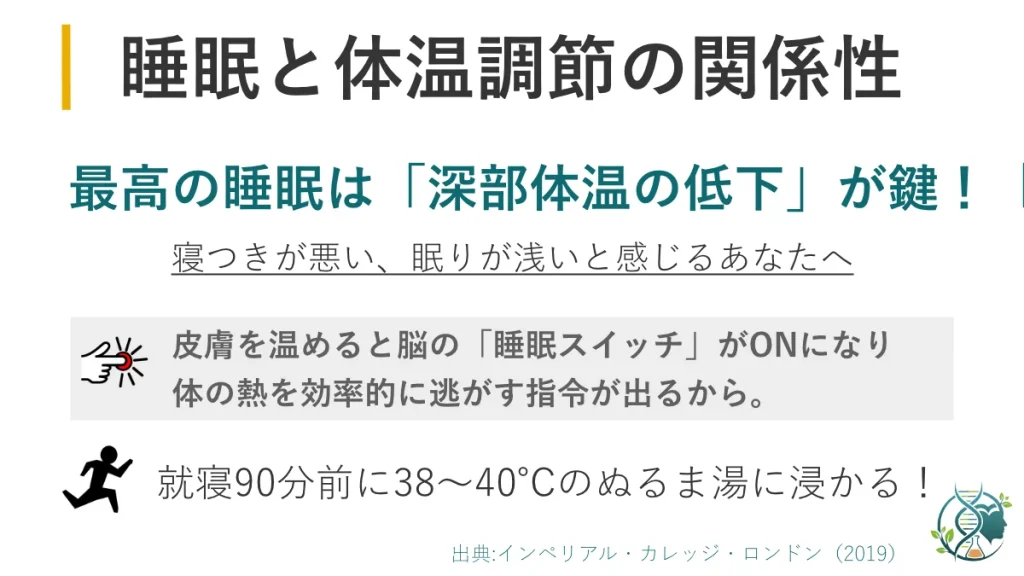
✅ この記事の結論 (1分要約)
- 深い眠りは体温の上昇ではなく、体の中心部の温度(深部体温)が『低下する』タイミングで訪れます。
- 皮膚を温めると脳の「睡眠スイッチ」が入り、手足から熱を逃がして深部体温を下げる指令が自動的に出されます。
- 最も効果的なのは、就寝90分前に38~40℃のぬるめのお湯に15分ほど浸かる入浴法です。
- 寝室は涼しめ(19~21℃)に保ちつつ、寝具で体を温める「頭寒足熱」が、この仕組みを最大限に活かします。
論文の紹介
2019年、イギリスのインペリアル・カレッジ・ロンドンらが発表した研究によると、
哺乳類が睡眠前に体を温めようとする行動は、脳の特定のスイッチを入れ、深い眠りと体の冷却を同時に引き起こすことが示唆されています。
今回は、この興味深い研究を紐解いていきましょう。
最高の睡眠は「深部体温の低下」が鍵!
①眠気は「深部体温」が下がる時に訪れる


私たちの体には、「概日リズム(※サーカディアンリズム)」という約24時間周期の体内時計が備わっています。このリズムに従って、体温も一日の中で上がったり下がったりを繰り返します。
※概日リズム
私たちの体温、ホルモン分泌、睡眠と覚醒などをコントロールしている、約1日周期の体内リズムのこと
活動的な日中は体温が高く、夜になってリラックスする時間になると、体は熱を外に逃がして深部体温(※体の内部の温度)を徐々に下げていきます。
そして、この深部体温が最も急激に下がるタイミングで、私たちは最も強い眠気を感じるのです。
つまり、「眠りにつく」という行為は、単に疲れたから起こるのではなく、体温が「お休みモード」へと切り替わるダイナミックなプロセスの一部なんですね。



私は、自律神経の影響か、寝るときに寒い気がするけど、布団をかけるとすぐに暑く感じてしまうような感覚になると眠れなくなります。
そういったときは、一度別の部屋でちょっと涼しめの状況でゆっくりしていると、徐々に眠くなります。
深部体温が下がると眠くなるということを知っていると、自分なりに合った方法が見つかると、入眠しやすくなると思います。
②皮膚を温めると脳の「睡眠&冷却スイッチ」がONになる


では、どうすればスムーズに深部体温を下げられるのでしょうか?ここで逆説的ながら重要になるのが、「皮膚を温める」という行為です。
今回の研究で注目されたのが、脳の視索前野(しさくぜんや)という部分。
ここは、体温調節と睡眠の両方をコントロールする司令塔のような場所です。
脳の「睡眠&冷却スイッチ」がONになる仕組み
- 皮膚を温める: お風呂に入ったり、温かい布団にくるまったりすると、皮膚の温度センサーがその情報をキャッチします。
- 脳へ信号が伝わる: 「温かい」という信号が、脳の司令塔である「視索前野」に送られます。
- スイッチON!: 視索前野にある特殊な神経細胞(NOS1ニューロン)が活性化。これが「睡眠&冷却スイッチ」です。
- 2つの指令が同時に出る:
- 指令①「眠れ!」: 脳の覚醒を促す部分の活動を抑え、眠りを誘います。
- 指令②「熱を逃がせ!」: 手足の末梢血管を広げる(※血管拡張)よう指令を出し、血液を体の表面に集めて熱を効率的に外へ逃がします。
この結果、皮膚は温かいのに、体の中心部は冷えるという現象が起こり、私たちは自然で深い眠りへと入っていくことができるのです。
お風呂上がりに手足がポカポカして、心地よい眠気に襲われるのは、まさにこの脳のスイッチが働いている証拠だったんですね。



理学療法士として患者さんのリハビリをしていると、体を温めることの重要性を実感します。
血行が良くなるだけでなく、筋肉の緊張がほぐれ、リラックス効果があるからです。
この論文を読んで、温めることが脳のレベルで直接「休息」のスイッチを入れるのだと知り、長年の経験が科学的に裏付けられたようで、とても興奮しました。
③効果を最大化する「入浴法」と「寝室環境」がある


このメカニズムを最大限に活用すれば、寝つきの悪さは改善できるかもしれません。
重要なのは「タイミング」と「温度」です。
就寝の90分前に入浴を終える
論文でも紹介されている「温浴効果」を最大化するには、
就寝の1〜2時間前、特に90分前までに入浴を終えるのが理想的です。
入浴で一時的に上がった深部体温が、その後、ベッドに入るまでの時間で自然に下がっていきます。この体温の下降カーブが、最も強い眠気を誘発するのです。
熱すぎるお湯(42℃以上)は交感神経を刺激してしまい逆効果。
38℃〜40℃程度のぬるめのお湯に15分ほど浸かるのがおすすめです。
寝室の環境で「頭寒足熱」を作る
快適な睡眠のためには、室温を19〜21℃程度に保つのが良いとされています。しかし、それだけでは不十分。
- 寝具で「微気候」を作る: 掛け布団や毛布を使い、体と寝具の間に31〜35℃の温かい空間(微気候)を作ることが大切です。これにより、皮膚の温度センサーが刺激され、脳のスイッチが入りやすくなります。
- 手足は温かく、頭は涼しく: 血管が集中する手や足は、熱を逃がすための重要なラジエーターです。靴下を履いて寝る場合は、締め付けの少ないゆったりしたものを選び、熱がこもりすぎないようにしましょう。一方で、頭部を冷やすと、より深いノンレム睡眠が得られやすいという研究もあります。



私は、冬でも寝ているときに足は暑い気がして、布団から出さないと落ち着かないことが多いです。しかし、そのまま出していると今度は足が冷えてしまい寝付けなくなってしまいます。
しかし、少し足を布団から出してもレッグウォーマーを活用して、末端を温めつつ、足底から熱を放散するような感じがして良いです。
一つの例ですが参考になればと思います!
【PTケイのQ&A】
まとめ
- 私たちの眠気は、体の中心部の温度(深部体温)が低下する時に最も強くなる。
- お風呂などで皮膚を温めると、脳の司令塔(視索前野)にある「睡眠スイッチ」がONになる。
- このスイッチは、眠りを誘う指令と、手足の血管を広げて熱を逃がす指令を同時に出す。
- 就寝90分前の入浴と、寝具で作る温かい微気候が、質の高い睡眠への鍵となる。
最後に
情報の海の中で、「あれも良い」「これも良い」と様々な健康法に振り回され、疲れ果ててしまうことがあります。かつての私がそうでした。
しかし、今回ご紹介したように、私たちの体に元々備わっている素晴らしいメカニズムを理解し、そのスイッチを少しだけ押してあげるだけで、心身は驚くほど応えてくれます。
一度にすべてを完璧にやろうとしなくて大丈夫です。
今夜は、いつもより少しだけ長く湯船に浸かってみる。
ただそれだけで、あなたの体は「お休み」への準備をスムーズに始めてくれるはずです。
その小さな一歩が、あなたを穏やかで深い眠りへと導いてくれることを、心から願っています。
参考文献
- Harding EC, Franks NP, Wisden W. The Temperature Dependence of Sleep. Front Neurosci. 2019;13:336. Published 2019 Apr 24. doi:10.3389/fnins.2019.00336
注意喚起
本記事は、睡眠に関する情報提供を目的としており、医学的アドバイスを提供するものではありません。症状の診断や治療については、必ず専門の医療機関にご相談ください。


