「先輩から『もっと全体を見て!』と言われるけど、具体的にどこをどう見ればいいのか分からない…」
「痛みを訴える部位にアプローチしても、なかなか改善しない…」
臨床に出始めたばかりの新人理学療法士や、実習中の学生の皆さんの中には、このような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。目の前の患者さんのために、学校で学んだ知識を必死にアウトプットしようとしても、思うような結果が出ずに焦りや無力感を感じてしまうこともありますよね。
その悩みを解決する大きなヒントが、今回ご紹介する『固定部位』と『過剰運動部位』という考え方です。
この記事では、まず結論として「なぜこの考え方が重要なのか」を提示し、その理由と具体的な臨床での活かし方を、PREP法に沿って分かりやすく解説していきます。この記事を読み終える頃には、あなたの臨床の視野がグッと広がり、患者さんの身体を評価・治療するための新たな武器が手に入っているはずです。
身体の不調を紐解く鍵は「動かない部位」にある
結論からお伝えします。
身体の痛みや不調を改善するためには、「動きすぎている部位(過剰運動部位)」に目を向けるのではなく、その根本原因となっている「動かなくなっている部位(固定部位)」を見つけ出し、アプローチすることが極めて重要です。
痛みを訴えている場所と、その痛みを引き起こしている原因の場所は違うかもしれない。この視点を持つだけで、あなたの臨床推論は格段に深まります。では、なぜ「固定部位」へのアプローチがそれほどまでに重要なのでしょうか。
その理由を「固定部位」と「過剰運動部位」、それぞれの正体を探りながら解説していきます。
そもそも「固定部位」って何?【その硬さの正体を探る】
固定部位とは、その名の通り、身体の中で動きが悪くなり、「硬さ」が際立っている部位を指します。あなたが臨床で患者さんに触れたとき、「なんだかこのあたり、板みたいに硬いな」「皮膚が全然動かないな」と感じる場所、それが固定部位です。
では、この「硬さ」の正体は何なのでしょうか。大きく分けて2つの要因が考えられます。
硬さの正体①:結合組織の「粘性」の上昇
私たちの身体は、筋肉や骨、皮膚、内臓など、様々な組織が結合組織によって結びつけられ、支えられています。この結合組織は、コラーゲン線維やヒアルロン酸などを含む「基質」と呼ばれるもので満たされており、この基質の「粘性」が身体のしなやかさに大きく関わっています。
用語解説:結合組織(けつごうそしき) 身体の様々な組織や器官を繋ぎ、支持し、保護する役割を持つ組織の総称です。皮膚の真皮、腱、靭帯、脂肪組織、さらには血液や軟骨、骨も広義の結合組織に含まれます。
用語解説:粘性(ねんせい) いわゆる「ねばりけ」のことです。例えば、冷蔵庫から出したばかりの蜂蜜をイメージしてください。硬くてなかなか伸びませんが、少し温めるとサラサラになりますよね。これが「温度依存性」です。また、蜂蜜をスプーンで速くかき混ぜようとすると強い抵抗を感じますが、ゆっくり混ぜると抵抗は少なくなります。これが「速度依存性」です。
身体の固定部位も、この蜂蜜とよく似ています。長時間同じ姿勢でいることによる不動や、血行不良による冷えなどが原因で、結合組織の基質の粘性が高まり、組織全体の「硬さ」を生み出してしまうのです。
硬さの正体②:「層間の滑り」の低下
私たちの身体は、皮膚、皮下脂肪、浅筋膜、深筋膜、そして筋肉といった組織が、まるでミルフィーユの層のように重なり合ってできています。健康な状態であれば、これらの層と層の間は互いにスムーズに滑り合い(滑走し)、私たちが自由に関節を曲げ伸ばししたり、身体を捻ったりすることを可能にしています。
しかし、固定部位では、前述した粘性の高まりや、脱水、不動などによって、この層間の滑りが著しく低下しています。ミルフィーユの層と層がくっついてしまい、一枚の分厚いパイ生地のようになってしまっている状態を想像してみてください。これでは、スムーズに動けるはずがありません。この滑りの悪さが、関節の可動域制限や、動かしたときの抵抗感、そして痛みに繋がってくるのです。
なぜ「過剰運動部位」が生まれてしまうのか?【痛みの犯人は別にいる】
さて、やっかいな「固定部位」が身体のどこかにできてしまうと、私たちの身体は非常に賢く、そして健気に、その動きの悪さを別の場所で補おうとします。この、固定部位の分まで頑張って働きすぎている部位こそが、「過剰運動部位」です。
過剰運動部位は、その名の通り、本来求められる以上の動きを強いられるため、常に不安定で、組織にかかるストレスも非常に大きくなります。その結果、筋肉や靭帯、関節包などが微細な損傷を繰り返し、炎症や痛みを引き起こすのです。
臨床でよく見る例:股関節が硬い人の「腰痛」
この「固定部位」と「過剰運動部位」の関係性を理解するために、非常に分かりやすい臨床例を一つご紹介します。それは、股関節(固定部位)と腰椎(過剰運動部位)の関係から生じる腰痛です。
- 原因(固定部位の発生) 長時間のデスクワークや、運動不足によって、股関節の前面にある筋肉や筋膜が硬く縮こまってしまいます。これにより、股関節を後ろに伸ばす動き(伸展)が制限された「固定部位」が完成します。
- 代償(過剰運動部位の発生) 私たちが歩いたり、椅子から立ち上がったりする際には、股関節の伸展が不可欠です。しかし、股関節が固定されていて伸展できないため、身体はそのすぐ上にある腰椎を過剰に反らせることで、足りない動きを代償しようとします。この瞬間、腰椎は「過剰運動部位」と化します。
- 結果(痛みの発生) 本来、安定しているべき腰椎が、歩くたびに、立ち上がるたびに過剰に動かされることで、腰椎の椎間関節や周囲の筋肉に絶えずストレスがかかり続けます。この負担が積み重なった結果、ある日「腰痛」として症状が現れるのです。
この場合、患者さんは「腰が痛い」と訴えますが、いくら腰(過剰運動部位)に対してマッサージや電気治療を施しても、その場しのぎにしかなりません。なぜなら、腰痛の根本原因は、股関節の硬さ(固定部位)にあるからです。この大元の原因にアプローチしない限り、腰は過剰な運動を強いられ続け、痛みは何度も繰り返されることになるのです。
【実践編】固定部位と過剰運動部位の見つけ方
では、臨床でどのようにして、この「固定部位」と「過剰運動部位」を見つけ出せばよいのでしょうか。難しく考える必要はありません。私たちが学校で学んだ基本的な評価を、少し視点を変えて組み合わせるだけです。
1. 姿勢を観察する(視診)
まずは、患者さんがリラックスして立っている姿、座っている姿を前後左右からじっくりと観察します。
- 左右の非対称性はないか?(例:肩の高さ、骨盤の高さ、膝の向き)
- 矢状面でのアライメントはどうか?(例:頭部が前方に出ていないか、骨盤が過度に前傾・後傾していないか、猫背になっていないか)
例えば、右肩が左肩よりも明らかに下がっている場合、右の胸郭や肩甲骨周囲の組織が下方向に引っ張られるように硬くなっている、つまり「固定部位」になっている可能性があります。
2. 動きを分析する(運動分析)
次に、患者さんにいくつかの基本的な動作を行ってもらい、動きの質を観察します。
- 立位体前屈:背骨全体が滑らかなカーブを描いて屈曲しているか?それとも、一部分だけがカクンと深く折れ曲がり(過剰運動)、他の部分は全く動いていない(固定)ように見えないか?
- 歩行:腕の振りは左右対称か?足関節や股関節の動きは十分に出ているか?骨盤や体幹が左右にグラグラと過剰に揺れていないか(過剰運動)?
動きが硬い、小さい、出ていない部分が「固定部位」、逆に動きが大きすぎる、不安定な部分が「過剰運動部位」の候補となります。
3. 実際に触れてみる(触診)
視診と運動分析で仮説を立てたら、いよいよ理学療法士の最大の武器である「手」を使って触診します。
- 皮膚の動き:固定部位と疑われる場所の皮膚を、指で優しくつまんでみてください。上下左右、斜め、あらゆる方向に動かしてみましょう。周囲と比べて、明らかに動きが悪く、分厚く、つまみにくい場所はありませんか?それが「層間の滑り」が低下しているサインです。
- 筋の硬さ:筋肉を軽く押圧したときの弾力を感じてみましょう。健康な筋肉は適度な弾力がありますが、固定部位となっている筋肉は、まるで板のように硬く、押してもほとんど沈み込まないことがあります。
この触診によって得られる感覚的な情報と、視診・運動分析による視覚的な情報を統合することで、「固定部位」と「過剰運動部位」の確信度を高めていくのです。
【治療編】明日から使える!固定部位へのアプローチ戦略
原因となっている「固定部位」を特定できたら、いよいよ治療です。アプローチの基本方針は、「固定部位の硬さを取り除き、本来の動きを取り戻すこと」。過剰運動部位は、固定部位が改善すれば、過剰に働く必要がなくなり、自然と負担が減っていきます。
ここでは、新人理学療法士でも安全かつ効果的に実践できる基本的なアプローチを3ステップでご紹介します。
ステップ1:まずは温める(温熱療法)
固定部位の硬さの正体の一つは「粘性」の高まりでした。そして、粘性には「温度依存性」があることを思い出してください。
つまり、アプローチの前に、ホットパックなどで固定部位をじっくりと温めることは、非常に有効な準備となります。組織の温度が上がることで粘性が低下し、その後のアプローチが格段に行いやすくなります。まるで、硬くなった蜂蜜を湯煎するようなイメージです。
ステップ2:皮膚・筋膜を優しく動かす(ソフトティッシュ・モビライゼーション)
温まって組織が緩みやすくなったら、次は「層間の滑り」を改善させるアプローチです。
固定部位の皮膚やその下にある筋膜を、「優しく」「ゆっくり」と、様々な方向に滑らせてみましょう。ここでのポイントは、決して強い力でゴシゴシこすらないことです。粘性の「速度依存性」を考慮し、相手の組織の抵抗を感じ取りながら、それに逆らわないように、あくまでゆっくりと動かすことが、組織間の滑走を引き出すコツです。
ステップ3:関節の遊びを引き出す(関節モビライゼーション)
皮膚や筋膜といった浅層の組織が緩んできたら、より深層の関節にアプローチします。関節がスムーズに動くためには、関節包や靭帯といった組織の柔軟性によって生まれる、数ミリ単位の「遊び」の動きが不可欠です。
固定部位では、この「遊び」が失われていることが多いため、関節モビライゼーションの手技を用いて、この微細な動きを回復させていきます。これは専門的な技術を要するため、まずは学校で学んだ基本に忠実に、正しい肢位、正しい固定、正しい力の方向を意識して、丁寧に行うことを心がけましょう。
さあ、明日からの臨床で試してみよう!
「固定部位」と「過剰運動部位」という概念、いかがでしたでしょうか。この視点は、決して特別なものではなく、私たちが日々行っている評価と治療に、一本の軸を通してくれる考え方です.
まずは、あなたが今担当している患者さんを、この視点でもう一度見直してみてください。
- 「この患者さんの『固定部位』はどこだろう?」
- 「痛みを訴えているこの場所は、もしかしたら『過剰運動部位』かもしれない?」
- 「だとしたら、本当の原因である『固定部位』はどこに隠れているんだろう?」
そして、勇気を出して、硬いと感じる部分を優しく触れ、温め、ゆっくりと動かしてみてください。きっと、今までとは違う患者さんの反応や、身体の変化を感じ取れるはずです。その小さな成功体験の積み重ねが、あなたを理学療法士として大きく成長させてくれるでしょう。
まとめ
最後に、この記事の重要なポイントをまとめます。
- 【最重要】 痛みの原因は、痛い場所(過剰運動部位)ではなく、遠く離れた「動かない場所(固定部位)」にあることが多い。
- 【硬さの正体】 固定部位の硬さは、結合組織の「粘性の上昇」と、組織の「層間の滑りの低下」によって生み出される。
- 【評価のコツ】 視診・運動分析・触診を組み合わせ、「動きのない場所」と「動きすぎている場所」を見極める。
- 【治療の鉄則】 治療は、原因である「固定部位」から始める。アプローチは「温めて、ゆっくり優しく」が基本。
- 【臨床の醍醐味】 一つの固定部位を解放することが、全身の動きの連鎖を改善し、根本的な問題解決に繋がる。
この考え方をあなたの臨床の引き出しの一つに加えて、ぜひ明日からの患者さんへのアプローチに活かしてみてください。応援しています!
参考文献
本記事は、筆者がBiNI Approachで学んだ概念および一般的な理学療法の知識を基に、新人理学療法士・学生向けに再構成したものです。より深く学びたい方は、関連する書籍やセミナーへの参加をお勧めします。
健康・医学関連情報の注意喚起
本記事は、理学療法における身体の捉え方に関する情報提供を目的としたものであり、特定の医学的アドバイスを提供するものではありません。 腰痛などの症状の診断や治療については、必ず医師や理学療法士などの医療従事者にご相談ください。




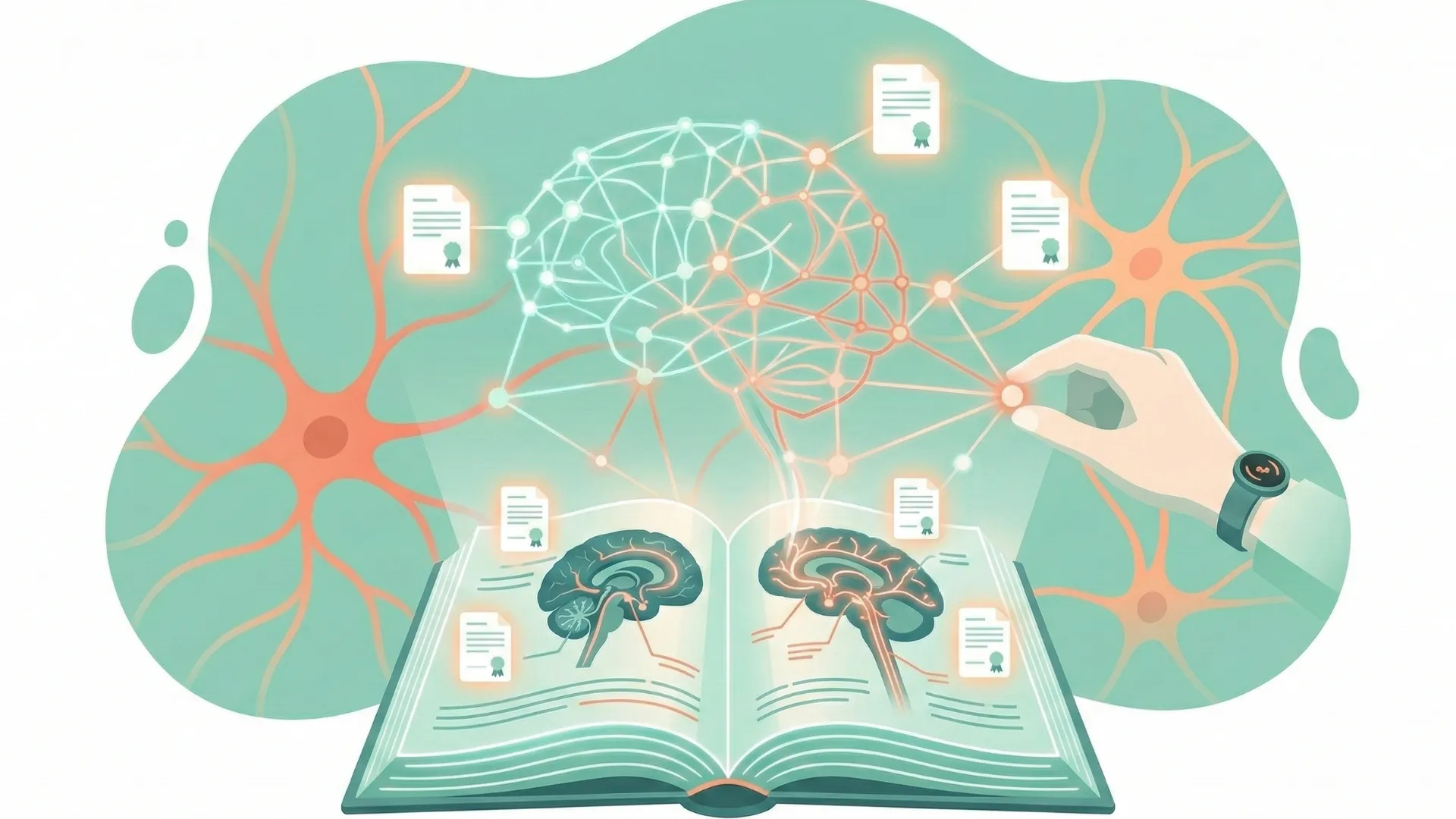


コメント
コメント一覧 (2件)
ceebus様はじめまして。
同じ群馬県でBiNI Approarchを学んでおります。
nabechanと申します。
よろしければ、情報交換や一緒に頑張っていけるとうれしいです。
nabechan様
ぜひ一緒に頑張りましょう。よろしくお願いいたします。