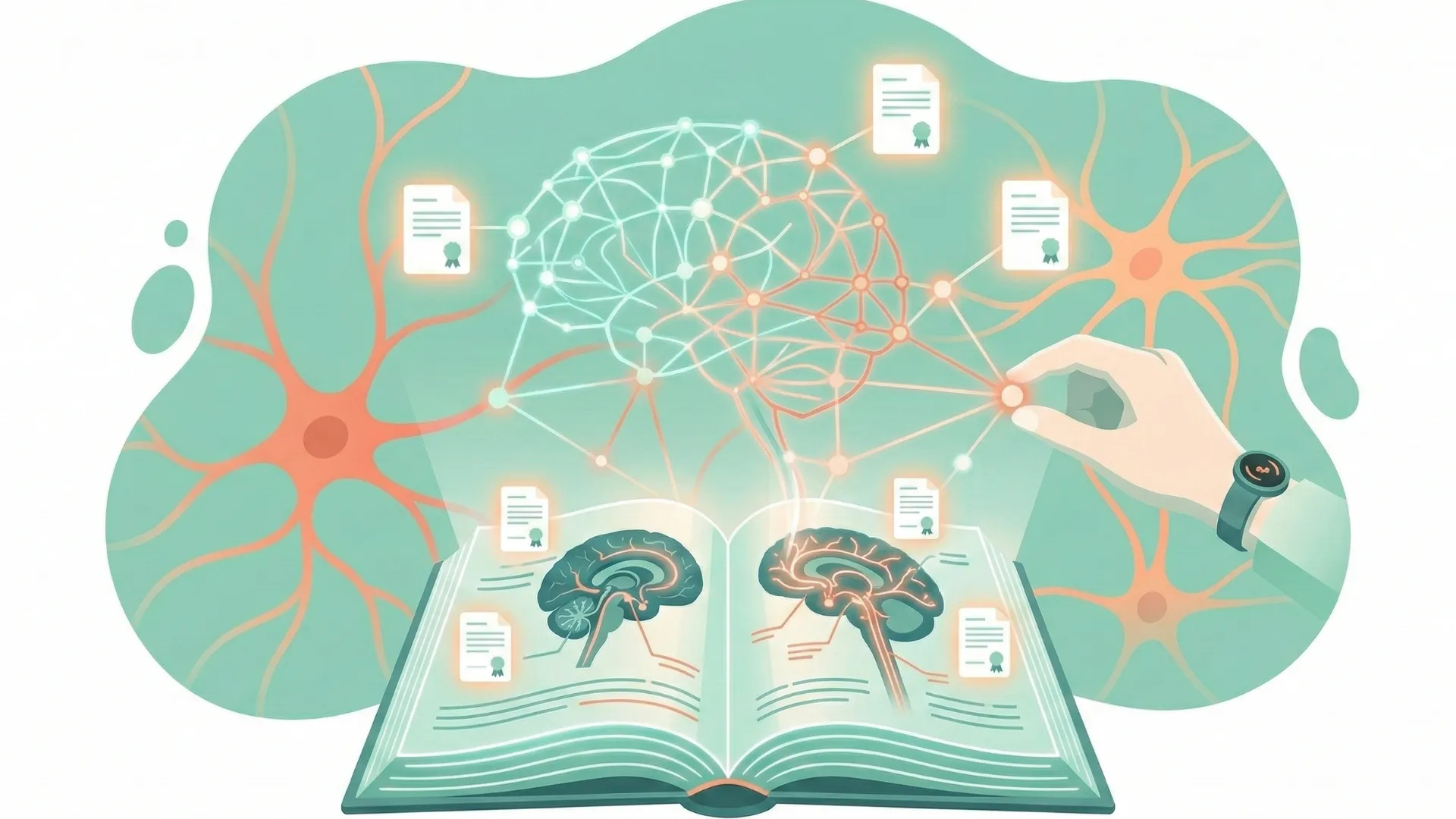はじめに:「あれもこれも」が招いた落とし穴 – 複数目標に挑む際の注意点
キャリアアップや自己実現のために、複数の資格試験や目標に同時に挑戦しようと考えることは、向上心のある方なら誰しも一度は経験するかもしれません。2018年の冬、私もまさにその渦中にいました。認定理学療法士試験(しかも運動器と脳血管の同時受験!)とBiNIアプローチのアシスタント試験という、大きな目標を複数抱え、雪が降り積もるようにプレッシャーも積み重なっていたことを思い出します。
当時は「絶対に合格したい!」という強い気持ちで、限られた時間の中で必死に勉強計画を立てていました。しかし、今振り返ると、その計画は「たくさんのことに同時に挑戦しすぎてうまくいかなかった典型例」であったと言わざるを得ません。
この記事では、当時の私の経験と反省を踏まえ、複数の大きな目標、特に資格試験のようなものに挑む際に陥りがちな落とし穴と、それを避けて成功に近づくための「心構え」について、2025年の視点から深掘りしていきます。
1. 2018年、私の無謀な(?)挑戦計画とその背景
当時の私は、理学療法士としての専門性を高めたいという強い思いから、複数の目標を同時進行で達成しようとしていました。
- 目標:
- 認定理学療法士試験(運動器分野)合格
- 認定理学療法士試験(脳血管分野)合格
- BiNIアプローチ アシスタント試験 合格
- 当時の状況:
- 仕事も多忙を極め、平日の勉強時間確保が困難な状況。
- 認定試験は3月3日、BiNIアシスタント試験は4月1日と、試験日が近接。
- 「職場にも宣言しており、絶対に合格したい」という強いプレッシャー。
当時の勉強計画(概要):
- 2月: 認定理学療法士の勉強を中心に。特に指定研修と脳卒中分野、ガイドラインに注力。BiNIは臨床での実践を意識。
- 3月: BiNIの勉強を中心に。教科書、過去の勉強会資料の復習、暗記。
- 学習スタイル: インプット(資料読み込み)→ 整理(パワーポイント)→ アウトプット(ブログ)という流れを基本としたいが、時間的制約が懸念。
今見返すと、各試験の範囲の広さや難易度を考えると、この計画がいかにタイトで、無謀な挑戦であったかが分かります。当時は「やるしかない」という気持ちが先行していましたが、結果として全てを中途半端にしてしまうリスクを内包していました。
2. 「多兎を追う者」が陥りがちな落とし穴:なぜ失敗しやすいのか?
複数の大きな目標に同時に挑戦することは、一見効率的に見えるかもしれませんが、そこにはいくつかの落とし穴が存在します。
- エネルギーと集中力の分散: 人間の集中力やエネルギーには限りがあります。複数の目標に同時に取り組むと、それぞれの目標に注げるエネルギーが分散し、結果的にどの目標に対しても中途半半端な努力しかできなくなる可能性があります。
- 時間管理の複雑化と破綻: 各目標に対する学習計画、進捗管理、優先順位付けなどが複雑になり、管理しきれなくなるリスクがあります。一つの遅れが他の計画にも影響し、雪だるま式に破綻することも。
- 精神的なプレッシャーの増大: 「全てを達成しなければならない」というプレッシャーは、精神的な余裕を奪い、不安や焦りを増大させます。これがパフォーマンスの低下に繋がることもあります。
- 中途半端な結果と自己肯定感の低下: 全ての目標を達成できれば良いですが、一つでも達成できないと、「自分はダメだ」と自己肯定感が低下し、次の挑戦への意欲を削いでしまう可能性があります。
- 「やったつもり」になる危険性: 複数のことを同時進行していると、それぞれの学習の深さが足りず、「勉強したつもり」「理解したつもり」になってしまうことがあります。本質的な理解やスキルの定着には繋がりにくいです。
2018年当時の私も、まさにこれらの落とし穴にはまりかけていた、あるいは既にはまっていたのかもしれません。
3. 複数目標に挑む際の「賢明な心構え」とは?
では、複数の目標に挑戦したい場合、どのような心構えで臨むべきなのでしょうか。当時の反省を踏まえ、いくつかのポイントを提案します。
3.1. 現実的な自己評価と目標の優先順位付け
- 自分のキャパシティを客観的に把握する: 自分が1日に確保できる勉強時間、集中力を持続できる時間、ストレス耐性などを冷静に評価します。「理想」ではなく「現実」に基づいた計画が重要です。
- 目標の「真の価値」を見極める: なぜその資格を取りたいのか? その目標を達成することで何が得られるのか? 自分にとって本当に重要な目標は何かを深く問い直し、優先順位を明確にします。
- 「全てを同時に」にこだわらない: 複数の目標があっても、それらを全て同じタイミングで達成する必要はありません。時期をずらす、段階的に取り組むなど、時間軸を考慮した計画を立てましょう。
3.2. 「選択と集中」の勇気を持つ
- 最も重要な目標にリソースを集中する: 優先順位の高い目標に対して、時間とエネルギーを重点的に配分します。時には、優先度の低い目標を一時的に「諦める」勇気も必要です。
- 「やらないこと」を決める: 限られた時間の中で成果を出すためには、「何をやるか」だけでなく、「何をやらないか」を決めることも重要です。
3.3. 質の高いインプットとアウトプットを意識する
- 学習方法の最適化: 2018年当時の私が目指していた「インプット→整理→アウトプット」という流れは、理解を深める上で非常に有効です。しかし、時間的制約がある場合は、全ての範囲でこれを徹底するのは難しいかもしれません。重要度の高い分野に絞って深く学び、他の分野は効率的なインプット方法(要点のまとめ、過去問演習など)に切り替えるなど、メリハリをつけることが大切です。
- アウトプットの機会を確保する: 学んだことを自分の言葉で説明したり、問題を解いたりするアウトプットの機会は、知識の定着に不可欠です。
3.4. 心身の健康管理を最優先に
- 十分な睡眠の確保: 睡眠不足は集中力や記憶力の大敵です。
- 適度な休息とリフレッシュ: 勉強漬けにならず、適度に休息を取り、気分転換をすることも重要です。
- ストレスマネジメント: 過度なプレッシャーを感じたら、信頼できる人に相談したり、リラックスできる方法を見つけたりしましょう。
3.5. 周囲への「宣言」と「協力体制」の構築
- 目標を公言する: 職場や家族、友人に目標を宣言することで、良い意味でのプレッシャーが生まれ、モチベーション維持に繋がることがあります。
- 協力を求める: 家族に家事の分担をお願いしたり、職場の同僚に業務の調整を相談したりするなど、周囲の協力を得ることも検討しましょう。
4. 2018年の私へ、そして今、挑戦するあなたへ
2018年の2月、雪が降る中で複数の試験合格を目指していた私。あの時の情熱と努力は決して無駄ではありませんでしたが、もし今の私が当時の自分にアドバイスできるなら、「もう少し肩の力を抜いて、一つ一つの目標とじっくり向き合う時間も大切だよ」と伝えたいです。
「臨床6年の集大成をここに!」という意気込みは素晴らしいですが、焦りや過度なプレッシャーは、かえってパフォーマンスを低下させることもあります。「やるときはやる」というメリハリは大切にしつつも、心身のバランスを崩さないように、自分自身をコントロールしていくこと。それこそが、長期的な目標達成において最も重要な「腕の見せ所」なのかもしれません。
まとめ:目標達成の鍵は「賢明な選択」と「持続可能な努力」
複数の目標に挑戦することは、自己成長への意欲の表れであり、非常に素晴らしいことです。しかし、その思いが空回りしないためには、現実的な計画と賢明な心構えが不可欠です。
- 自分の限界と向き合い、優先順位をつける勇気を持つこと。
- 質の高い学習を心がけ、心身の健康を維持すること。
- そして何よりも、挑戦するプロセスそのものを楽しむこと。
これらのことを意識しながら、一歩一歩着実に進んでいけば、必ずや目標達成の日は訪れるはずです。この記事が、今まさに何かに挑戦しようとしているあなたの、そしてかつての私のような状況にある誰かの、一助となれば幸いです。