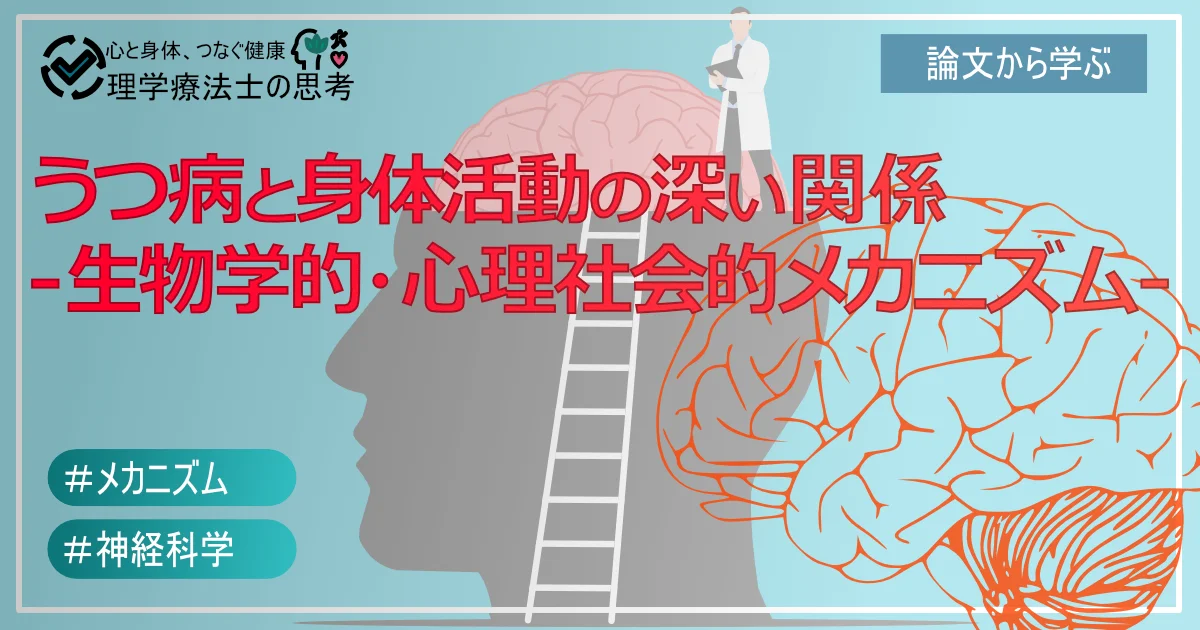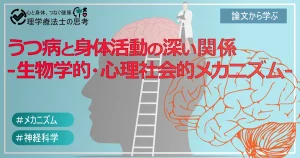皆さん、こんにちは!理学療法士のPTケイです。
「最近、気分が落ち込みやすい…」 「何だかやる気が出ない…」
そんな悩みを抱えていませんか?もしかしたら、その原因は「運動不足」かもしれません!
今回のブログでは、運動不足とうつ病の関係について、最新の研究結果をもとに、どこよりも詳しく解説していきます!
えっ、運動でうつが改善!?驚きの研究結果!
2019年 Aaron Kandola氏らの研究グループは、Neuroscience and Biobehavioral Reviewsに掲載された論文において、身体活動と抑うつ症状の関係性におけるメカニズムに関して発表しました。

この論文は、過去の研究をまとめたもので、運動がうつ病に効果があるメカニズムを詳しく調べています。まだまださらなる研究を要する部分もありますが、今回はその中でも、
- 生物学的なメカニズム(脳の働きや体の変化など)
- 心理社会的なメカニズム(心や社会との関わりなど)
の2つの側面に分けて、詳しく情報を整理して、解説していきます!
運動がうつ病に効くメカニズム:その1【生物学的メカニズム】
運動がうつ病に効果がある理由として、まず、体の内側で起こる変化、つまり「生物学的メカニズム」が考えられます。
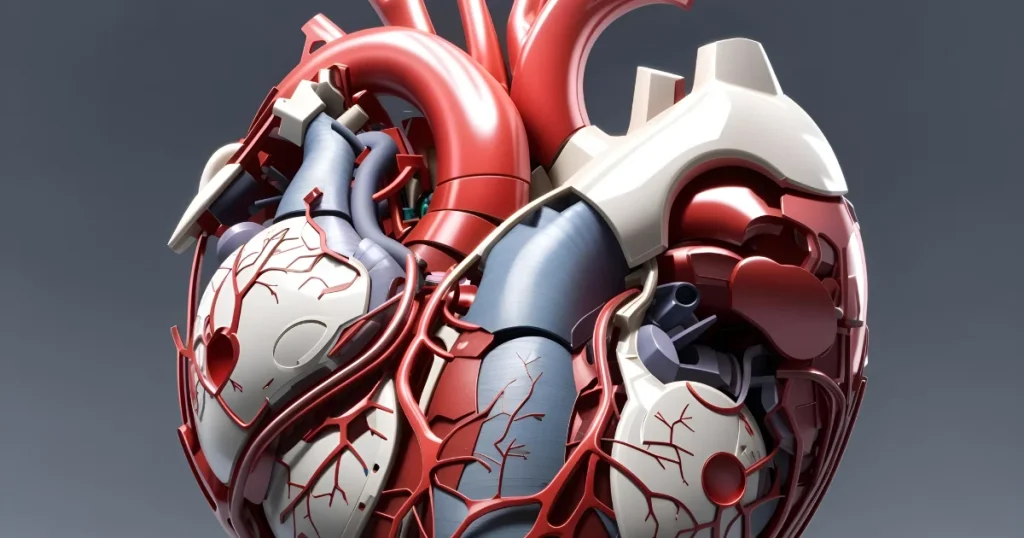
1. 脳の働きを活性化!
運動は、脳の「神経可塑性」を高めることがわかっています。神経可塑性とは、脳の神経細胞が新しく生まれたり(神経新生)、神経細胞同士のつながりが変化したりする能力のこと。
特に、記憶や学習に関わる「海馬」という部分の神経新生が、うつ病の改善に重要であると考えられています。
- BDNF(脳由来神経栄養因子)の増加: 運動は、脳内でBDNFというタンパク質の量を増やします。BDNFは、神経細胞の成長や生存を助け、神経細胞同士のつながりを強化する、いわば「脳の栄養剤」のような働きをします。
- 血管新生の促進: 運動は、脳の血管を新しく作る「血管新生」を促します。これにより、脳への血液供給が増え、神経細胞への栄養や酸素の供給が改善され、脳の働きが活発になります。
- 神経伝達物質の調整: 運動は、セロトニン、ノルアドレナリン、ドーパミンといった、気分や意欲に関わる神経伝達物質の量を増やしたり、バランスを整えたりする効果があると考えられています。
2. 体の炎症を抑える!
うつ病は、体内の慢性的な炎症と関係があることがわかってきています。運動には、この炎症を抑える効果が期待できます。
- 抗炎症性サイトカインの増加: 運動は、筋肉から「IL-6」という物質を放出させます。IL-6は、一見すると炎症を引き起こす物質(炎症性サイトカイン)のように思えますが、運動によって放出されるIL-6は、逆に炎症を抑える「IL-10」や「IL-1ra」といった物質の産生を促し、結果的に体の炎症を鎮める働きをします。
- 脂肪細胞の減少: 運動は、内臓脂肪を減らす効果があります。内臓脂肪は、炎症性物質を分泌するため、内臓脂肪が減ることで、体内の炎症が抑えられます。
- 免疫細胞の調整: 運動は、白血球の一種である単球に作用し、炎症を促進するM1マクロファージを抑制し、炎症を抑えるM2マクロファージを増やすことで、免疫系のバランスを整えます。
3. ストレスホルモンを調整!
ストレスを感じると、体内で「コルチゾール」というホルモンが分泌されます。コルチゾールは、心身をストレスに対応させるために必要なホルモンですが、長期間にわたって過剰に分泌されると、うつ病の発症リスクを高める可能性があります。
運動は、このコルチゾールの分泌を調整し、ストレスに対する体の反応を改善する効果が期待できます。
- HPA軸の機能改善: 運動は、ストレス反応に関わる「HPA軸(視床下部-下垂体-副腎皮質系)」の機能を改善し、コルチゾールの過剰な分泌を抑えると考えられています。
運動がうつ病に効くメカニズム:その2【心理社会的メカニズム】
次に、運動が心や社会との関わりに働きかける「心理社会的メカニズム」について見ていきましょう。

1. 自尊心を高める!
運動を続けることで、「体力がついた」「目標を達成できた」といった達成感や自信を得ることができます。これは、自分の体に対する肯定的なイメージ(身体的自己認識)や、自分には価値があるという感覚(自己効力感)を高め、自尊心を向上させる効果が期待できます。
2. 人とのつながりを増やす!
グループでの運動やスポーツは、人との交流の機会を増やし、孤立感を軽減する効果が期待できます。他の人からの励ましやサポート(社会的支援)は、うつ病の予防や改善に重要な役割を果たすことが知られています。
3. 自信をつける!
運動を継続して行うことで、体力向上や目標達成を繰り返し、成功体験を積み重ねることで、日常生活における自信の向上につながります。
ここがポイント!
この研究では、「運動」だけでなく、日常生活での「身体活動」(階段を使う、歩いて買い物に行くなど)も、うつ病予防に効果がある可能性を示唆しています。
つまり、「運動しなきゃ!」と意気込むだけでなく、普段の生活の中で、少しでも体を動かすことを意識することが大切なんです。
今日からできる!運動不足解消&うつ病予防のための3つのステップ
「運動が大切」なのはわかったけど、何から始めればいいの?

そんな方のために、今日からできる、3つのステップをご紹介します!
- まずは、今の自分の運動量を知ろう!
- スマホの歩数計アプリや、活動量計を使って、1日にどれくらい歩いているか、どれくらい体を動かしているかを把握しましょう。
- 目標を立てて、少しずつ運動量を増やそう!
- 「1日10分、ウォーキングをする」「エレベーターではなく階段を使う」など、無理のない範囲で目標を立てましょう。
- 慣れてきたら、少しずつ運動時間や強度を上げていきましょう。
- 自分に合った運動を見つけよう!
- ウォーキング、ジョギング、水泳、ヨガ、ダンス…など、運動の種類はたくさんあります。
- 「楽しい!」と思える運動を見つけて、継続することが大切です。
- 仲間と一緒に運動するのもオススメです!
まとめ:運動で、心も体もハッピーに!
今回の研究結果は、運動が、うつ病の予防と改善に、非常に大きな効果を持つ可能性を示しています。
「最近、ちょっと気分が落ち込みがち…」 「運動不足が気になる…」
そんな方は、ぜひ今日から、体を動かす習慣を始めてみてください。
運動で、心も体もハッピーな毎日を目指しましょう!
参考文献:
- Kandola, A., Ashdown-Franks, G., Hendriks, J., Sabiston, C. M., & Stubbs, B. (2019). Physical activity and depression: Towards understanding the antidepressant mechanisms of physical activity. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 107, 525-539.
健康・医学関連情報の注意喚起:
本記事は、うつ病と身体活動に関する一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の医学的アドバイスを提供するものではありません。 うつ病の診断や治療については、必ず医療従事者にご相談ください。