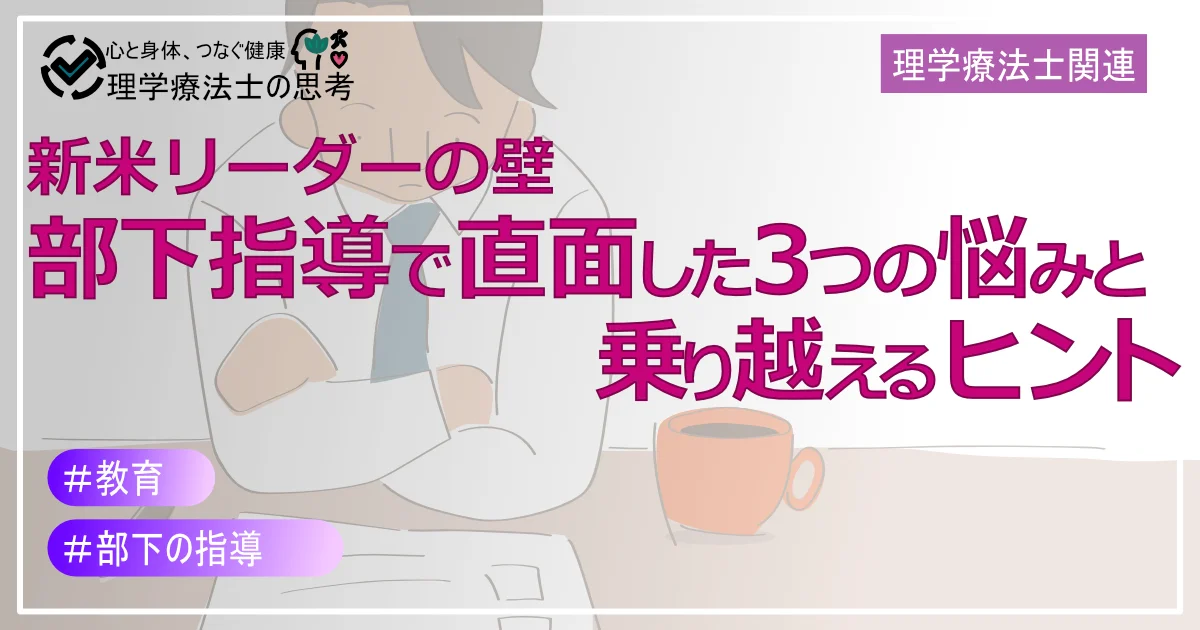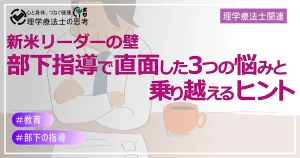こんばんは。日々の業務に追われ、なかなか専門分野のインプットやアウトプットが追いつかない今日この頃です。(専門記事の需要が少ないのも、少し悩みどころですが…)
さて、今回は少し視点を変えて、リーダーとしての役割、特に「部下指導」について、私が直面している悩みと、それに対して考えていることを整理してみたいと思います。
私が初めて部下を持ったのは臨床4年目、今から2年前(2015年)のことです。当時は部下も1人で、頼れる上司からのアドバイスを受けながら、手探りで指導にあたっていました。そして臨床6年目(2017年現在)になりリーダーを任され、部下は3人に増えました。リーダーという立場は想像以上に難しく、特に部下への関わり方については、日々試行錯誤と悩みの連続です。
今回は、特に私がリーダーとしてよく悩む3つの点と、それに対する現時点での考えや対策を共有します。同じように新米リーダーとして奮闘されている方の、何かのヒントになれば幸いです。
悩み1:見えない部下の状況 – 報告・連絡・相談(報連相)の壁
リーダーとしてチームを円滑に運営するには、部下の状況を正確に把握することが不可欠です。しかし、ここで最初の壁にぶつかります。
- 課題: 部下からの「報告・連絡・相談(報連相)」が十分でない、あるいは苦手な場合、彼らが何に困っているのか、どんな状況なのかを掴むのに苦労します。本人は「うまくやれている」と思っていても、リーダーから見ればもっと良い方法があったり、潜在的な問題が見えたりすることもあります。
- 悩み: 指示待ちではなく、リーダー側から能動的に状況を把握し、必要な声かけをしたい。しかし、どうすればそれに気づけるのか?他のスタッフから指摘されて初めて対応するのではなく、自ら気づいて先手を打ちたいのですが、日常業務の中で常に全員を詳細に見るのは難しく、対応が後手に回りがちです。
現時点での対策案:
- 意識的な観察: 自分の業務中であっても、少し視野を広げ、部下の様子や担当患者さんの状況に気を配る意識を持つ。
- 声かけの習慣化: 「何か困っていることはない?」と定期的に、かつ気軽に声をかける。報連相が苦手な部下にとっては、この一言が相談のきっかけになるかもしれない。
- 「報連相しやすい雰囲気」作り: ミスを恐れず相談できる、心理的な安全性のあるチーム作りを心がける。(言うは易しですが…)
悩み2:やる気を引き出す難しさ – モチベーション向上の壁
チーム全体のパフォーマンスを上げるためには、個々のメンバーのモチベーション維持・向上が欠かせません。しかし、これもまた難しい課題です。
- 課題: チーム全体のモチベーションには波があり、低下している時期にはミスが増えたり、担当患者さんの状況が悪化したりする傾向を感じます。リーダーとして、個々の意欲を高めるための働きかけが必要だと痛感しています。
- 悩み: モチベーションを高めるための指導やアドバイスを行いたいが、日々の業務に追われ、どうしても簡単な声かけや抽象的な指示になりがちです。「もっと頑張れ」だけでは、部下は何をどうすれば良いのか分からず、動けなくなってしまうことがあります。
現時点での対策案:
- 具体的な指導の実践: “Teaching is learning twice”(教えることは二度学ぶこと)という言葉もありますが、抽象論ではなく、「私ならこの場面ではこう考える、こう動く」といった具体的な思考プロセスや技術を、時間を取ってでも丁寧に伝える。
- 成功体験のサポート: 部下が「できた!」と感じられるような、少し挑戦的ながらも達成可能な業務を任せたり、成功に向けて側面的なサポートをしたりする。小さな成功体験が自信と次の意欲につながるはずです。
- 個々の関心への配慮: 可能であれば、部下が興味を持っている分野や、伸ばしたいと考えているスキルに関連する業務や学習機会を提供できないか考える。
悩み3:ミスへの向き合い方 – 叱る以外の指導法の壁
誰にでもミスはありますが、リーダーとしてそれにどう向き合い、指導していくかは非常に重要であり、同時に私の苦手な部分でもあります。
- 課題: ミスや改善が必要な点について、部下に伝えなければならない場面。しかし、私自身、強く言うのが得意ではなく、部下に甘く見られているのではないかと感じることがあります。(昔からそうでした…)
- 悩み: リーダーである以上、言うべきことは言わなければなりません。しかし、「怒る」ことだけが指導ではないはず。多くの書籍でも、感情的に怒る指導は推奨されていません。では、どうすれば効果的に、かつ相手の成長につながるように伝えられるのか?
現時点での対策案:
- 「部下のため」という本気度: 指導する際に最も大切なのは、「本当に相手の成長を思って伝えているか」という姿勢だと思います。一般論や建前ではなく、本気で向き合っていることが伝われば、厳しい内容でも受け止め方が変わるはずです。上から目線にならないよう、細心の注意を払う。
- 事実に基づいた客観的な指摘: 感情的にならず、具体的な事実(いつ、どこで、何が起きたか)に基づいて、問題点と改善策を冷静に伝える。
- 人格否定をしない: ミスという「行動」や「結果」に対して指摘するのであり、部下の「人格」を否定するような言い方は絶対に避ける。
- 信頼関係の維持: ミスを指摘する際も、「あなたの能力や意欲を信頼している」という基本的なスタンスを忘れない。信頼があるからこそ、改善への期待を伝えられる。
まとめ:部下と共に成長するリーダーを目指して
リーダーとして部下指導に悩む中で、現時点で私が重要だと感じているのは、まずリーダー自身が部下のことを真剣に考え、信頼し、その成長を心から願う姿勢を持つことです。
こちらが信頼しなければ、部下も心を開いてくれないでしょう。良い点は素直に褒め、改善が必要な点は真摯に、そして具体的に伝える。部下が経験を積み、成功体験を得られるように、必要な場面で考え抜いた具体的なアドバイスやサポートを提供する。
リーダーの一言や姿勢が、チームの雰囲気やモチベーションに大きく影響を与えることを自覚し、これからも試行錯誤しながら、部下と共に成長していけるリーダーを目指していきたいと思います。