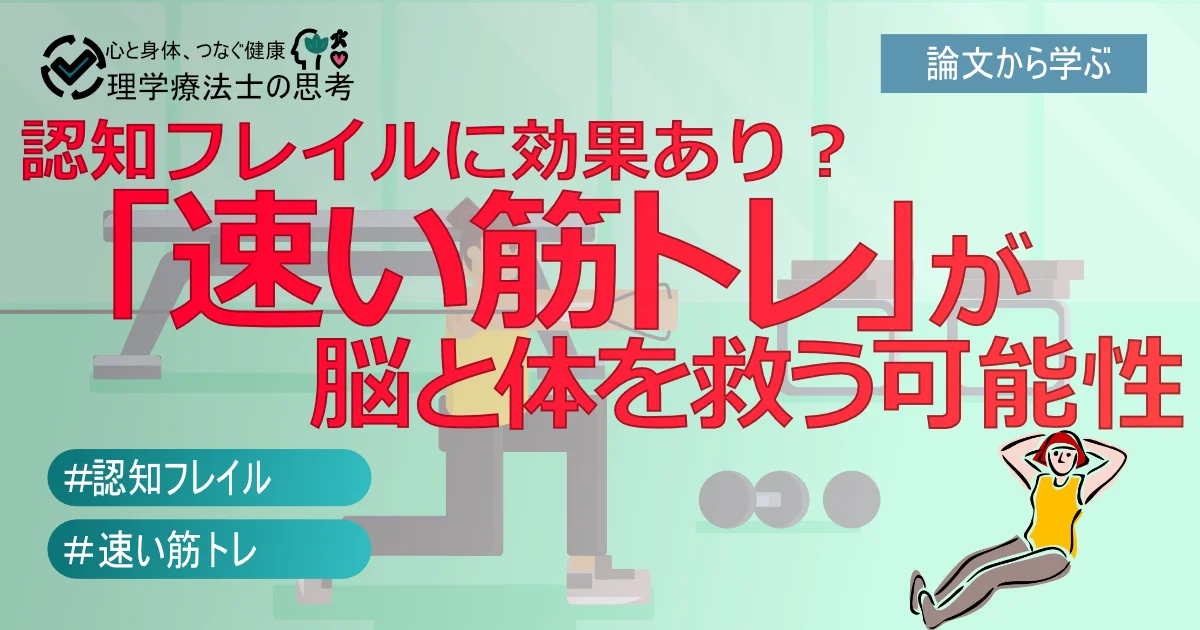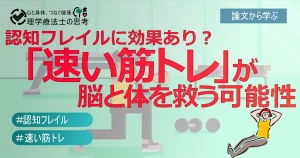「最近、なんだか物忘れが多くなった気がする…」
「以前より足腰が弱って、歩くのが少し億劫になったかも…」
そんな風に感じていませんか? もしかしたらそれは、「認知フレイル」のサインかもしれません。
認知フレイルとは、簡単に言うと「体の衰え(フレイル)」と「認知機能の軽度な低下」が同時に起こっている状態のこと。(認知機能の低下だけではなく身体的なフレイルと併存している)
ようするに、認知症ではないけれど、将来のリスクが高まっている注意が必要な段階です。
認知フレイルは、早めに対策することで進行を遅らせたり、改善したりできる可能性があると言われています。
でも、諦めるのはまだ早いかもしれません!
今回は、理学療法士のPTケイが、そんな認知フレイルに対して、「速い筋トレ」つまり高速レジスタンス運動が、認知機能や身体能力の改善に役立つ可能性があることを示した、韓国で行われた信頼性の高い研究(ランダム化比較試験)をご紹介します。
この研究結果を知れば、あなたも今日から何かを始めたくなるかもしれませんよ。
研究紹介:速い筋トレは認知フレイルにどう影響する?
まずは、今回ご紹介する研究の概要です。
2018年 韓国 ユン D.H.らは、認知フレイル高齢者における認知機能と身体能力に対する高速レジスタンス運動トレーニングの効果についてのランダム化比較試験(研究に参加する人をランダムにグループ分けして効果を比べる信頼性の高い研究方法)を行いました。その結果、高速レジスタンス運動は、認知機能(処理速度、実行機能)、身体能力(SPPB、TUG、歩行速度)、筋力(握力、膝伸展力)を有意に改善したが、フレイルスコアには有意な変化はなかったと報告しました。
この研究は、医学論文として専門誌「The Journal of Nutrition, Health & Aging」に掲載されています。
「速い筋トレ」が認知機能と身体能力を改善!研究結果を詳しく解説
この研究で最も重要なことは、「速い筋トレ」を16週間続けたグループで、認知機能の一部と身体能力が明らかに改善したという点です。
具体的にどのような研究が行われたのか見ていきましょう。
この研究は、認知フレイルの状態にあると判断された65歳以上の地域在住高齢者45名(最終的な分析対象者)を対象に実施されました。
参加者はランダムに2つのグループに分けられました。
- 高速レジスタンス運動グループ (介入群): 弾性バンド(ゴムチューブのようなもの)を使い、「速く」筋肉を収縮させる筋力トレーニングを週に3回行いました。
- 比較対照グループ (対照群): バランス運動や軽いストレッチ(こちらも弾性バンドを使用)を週に2回行いました。
そして、16週間後にそれぞれのグループで認知機能や身体能力がどのように変化したかを比較しました。
【認知機能への効果】
まず、脳の働きへの影響です。
「速い筋トレ」グループでは、軽い運動グループと比較して、以下の2つの認知機能が有意に改善しました。
- 処理速度: 情報を見て理解し、反応するまでのスピードが速くなりました。(統計学的なP値 = 0.036、効果量 = 0.21[小])
- 実行機能: 目標を立てて計画し、効率よく物事を進める能力が向上しました。(統計学的なP値 = 0.022、効果量 = 0.74[中])
これらの機能は、日常生活でテキパキと作業をこなしたり、段取り良く家事を進めたりする上でとても大切です。
用語解説
処理速度: 目や耳から入ってきた情報を見て、それが何かを理解し、どう対応するか判断するまでの一連の思考スピードのことです。
実行機能: 目標を達成するために、計画を立て、注意を向け、行動をコントロールし、効率的に物事を進めるための脳の高次機能のことです。「段取り力」や「自己制御力」とも言えます。
ただし、残念ながら、記憶力そのものや、頭の切り替えの速さ(認知の柔軟性)、注意力の持続時間(ワーキングメモリ)といった他の認知機能については、2つのグループ間で明確な差は見られませんでした(P値 > 0.05)。
【身体能力への効果】
次に、体の動きに関する結果です。こちらは非常に良好な結果が出ています。「速い筋トレ」グループは、軽い運動グループと比較して、以下の点で有意な改善が見られました。
- SPPB (総合的な下肢機能): バランス能力、椅子からの立ち上がり、歩行能力を総合的に評価するテストの点数が明らかに向上しました。(P値 = 0.001、効果量 = 0.81[中])
- TUG (移動能力): 椅子から立ち上がって3m歩き、方向転換して戻って座るまでの時間が短縮しました。(P値 < 0.001、効果量 = 0.65[中])
- 歩行速度: 歩くスピードが速くなりました。(P値 = 0.027、効果量 = 0.93[大])
効果量を見ると、特にSPPBや歩行速度の改善は中程度から大きいレベルであり、これは日常生活での動きやすさや活動範囲の拡大に繋がりうる、臨床的にも意義のある変化と考えられます。
用語解説
SPPB (Short Physical Performance Battery): 高齢者の下肢機能(①バランス保持、②4m歩行速度、③椅子からの5回連続立ち上がり)を評価するテストバッテリー。合計12点満点で、点数が高いほど機能が良いとされます。
TUG (Timed Up and Go test): 椅子に座った状態から立ち上がり、3m先の目印を回って再び椅子に座るまでの時間を測定するテスト。基本的な移動能力や転倒リスクの評価に広く用いられています。
【筋力への効果】
筋力についても嬉しい結果です。「速い筋トレ」グループでは、軽い運動グループよりも、以下の筋力が有意に向上しました。
- 握力: (P値 = 0.020、効果量 = 0.30[小])
- 膝を伸ばす力 (等速性筋力): (60°/秒: P値=0.004, ES=0.19[小]; 180°/秒: P値=0.001, ES=0.32[小])
握力や足の筋力は、物を持つ、立ち上がる、歩くといった基本的な動作はもちろん、転倒予防にも非常に重要です。
では、なぜ「速い筋トレ」、つまり高速レジスタンス運動がこれらの改善につながったのでしょうか?
論文の考察を参考にすると、いくつかの可能性が考えられます。
- 神経系の活性化: 筋肉を「速く」動かすという指令は、脳から筋肉への神経伝達をより活発にします。これが繰り返されることで、神経系の効率が上がり、処理速度のような認知機能にも良い影響を与えた可能性があります。
- 脳血流の増加・神経栄養因子の分泌促進: 運動によって脳への血流が増加したり、脳由来神経栄養因子(BDNF)のような脳細胞の成長や保護に関わる物質の分泌が促されたりすることも、認知機能改善の一因と考えられます。
- 身体機能向上による自信と活動性の向上: 筋力やバランスが向上することで、「動ける」という自信がつき、日常生活での活動量が増えることも考えられます。活動量が増えれば、脳への刺激も増え、認知機能維持にも繋がります。
この研究では、専門家の指導のもと弾性バンドを使ったトレーニングが行われましたが、ポイントは「できるだけ速く」筋肉を収縮させることです。
特別な器具がなくても、例えば普段の椅子からの立ち上がり動作を少し「速く」行うことを意識するだけでも、似たような刺激を筋肉や神経に与えることができるかもしれません。
このように、週3回程度の「速い筋トレ」は、16週間という比較的短い期間であっても、認知フレイル高齢者の脳(処理速度・実行機能)と体(下肢機能・筋力)の両方に良い影響を与える可能性があることが、このランダム化比較試験によって示唆されました。
結果の解釈における注意点
ただし、この研究結果を鵜呑みにせず、いくつかの注意点を理解しておくことも大切です。
- 全ての認知機能が改善したわけではない: 先ほども触れたように、記憶力や認知の柔軟性など、改善が見られなかった認知機能もありました。高速レジスタンス運動が万能というわけではありません。
- フレイル自体の改善は限定的: 「フレイル(虚弱)」の状態そのものを評価する指標(フレイルスコア)には、残念ながら介入による明確な改善は見られませんでした。フレイルは体重減少や疲労感、活動量の低下など、多くの要因が絡み合った状態です。運動だけで、しかも16週間という期間では、状態全体を改善するのは難しかったのかもしれません。より長期的な介入や、栄養改善など他のアプローチとの組み合わせが必要になる可能性があります。
- 研究の限界: この研究は、最終的な参加者の数が45名と比較的少なく、また韓国の特定の地域にお住まいの方を対象としています。そのため、この結果が他の国や地域の人々、あるいはもっと多くの人にそのまま当てはまるとは限りません(外的妥当性の限界)。また、研究から脱落した人も約30%おり、これも結果の解釈に影響を与える可能性があります。
これらの点を踏まえると、「速い筋トレは認知フレイルに有効な可能性があるが、その効果は限定的であり、さらなる研究が必要」と考えるのが現時点では妥当でしょう。
研究で行われた「速い筋トレ」プログラムとは?
では、この研究で実際に行われ、認知機能や身体能力の改善という結果に繋がった「高速レジスタンス運動」とは、具体的にどのようなプログラムだったのでしょうか?
この研究の介入グループは、運動指導の専門家の直接的な監督のもとで、以下のプログラムを週に3回、16週間にわたって実施しました。各セッションは約1時間で、ウォーミングアップ(10分)、メイントレーニング(40分)、クールダウン(10分)で構成されていました。
- 使用器具: 弾性運動バンド(ゴムチューブやセラバンドのようなもの)が使われました。
- 運動のポイント: 筋肉に力を入れる動き(収縮期)はできるだけ速く行い、一瞬(1秒)動きを止め、力を抜いて元の位置に戻る動き(伸張期)は**ゆっくり(2秒以上かけて)**行う、という指示でした。
- 運動強度: バンドの色で抵抗を調整し、運動している本人が「ややきつい」と感じる程度(自覚的運動強度 RPE 12-13)を目安に行われました。
- 運動種目(メイントレーニング): 以下の8種目の運動が、それぞれ12~15回を2~3セットずつ行われました。全身の様々な筋肉を使うように構成されています。
- シーテッド・ロー (Seated row): 座った状態でバンドを引き、主に背中の筋肉を鍛える運動。
- ユニラテラル・レッグプレス (Unilateral leg press): 座った状態で片足ずつバンドを押し出し、太ももの前の筋肉を鍛える運動。
- ペックデックフライ (Pec deck fly application): 座った状態でバンドを使い、胸の筋肉を鍛える運動。
- シーテッド・レッグレイズ (Seated leg raise): 座った状態で足を持ち上げ、お腹や太ももの付け根の筋肉を鍛える運動。
- ラテラル・レイズ (Lateral raise): 座った(または立った)状態でバンドを使い、肩の筋肉を鍛える運動。
- セミ・スクワット (Semi-squat): 浅めのスクワットで、お尻や太ももの筋肉を鍛える運動。
- ワイド・スクワット (Wide squat): 足を広めにしたスクワットで、主にお尻や太ももの内側の筋肉を鍛える運動。
- ブリッジ (Bridge): 仰向けに寝てお尻を持ち上げ、お尻や太ももの裏側の筋肉を鍛える運動。
このように、研究では専門家の指導のもと、体系立てられたプログラムが実施されました。ご自宅でこれと全く同じプログラムを行うのは難しいかもしれませんが、「弾性バンドを使用」「力を入れる動きは速く、戻す動きはゆっくり」「ややきついと感じる強度で」「全身の筋肉を対象に」「週3回程度」という要素が、認知フレイルに対する運動の効果を引き出す上で重要であったと考えられます。
もし、ご自身の認知機能や身体能力の低下が気になり、「速い筋トレ」を取り入れてみたいとお考えの場合は、まずかかりつけ医や理学療法士などの専門家に相談してみることをお勧めします。ご自身の体力や健康状態に合わせて、安全かつ効果的な運動プログラムを提案してもらえるでしょう。
運動を始める際の注意点
研究で行われたような運動や、ご自身で運動を始める際には、以下の点にご注意ください。
- 無理は禁物: 最初は回数や時間を少なめに設定し、「楽だけど少しきついかな?」と感じる程度から始めましょう。体力に合わせて徐々に増やしていくことが長続きのコツです。痛みを感じたらすぐに中止してください。
- 安全第一: 特に「速い動き」を行う際は、バランスを崩して転倒しないように十分注意が必要です。必ず安定した椅子を使ったり、壁や手すりの近くで行ったりするなど、安全な環境を確保しましょう。
- 準備運動と整理運動: 運動の前後に軽いストレッチなどを行うと、怪我の予防に繋がります。
- 水分補給: 運動中はこまめに水分を補給しましょう。
- 専門家への相談: 心臓病や高血圧、糖尿病などの持病がある方、膝や腰に強い痛みがある方、体力に自信のない方は、運動を始める前に必ず主治医の先生や理学療法士などの専門家に相談し、ご自身の状態に合った運動内容や強度についてアドバイスを受けてください。
まとめ
今回は、認知フレイルの高齢者に対する「速い筋トレ(高速レジスタンス運動)」の効果を検証した韓国の研究をご紹介しました。
この研究から、専門家の指導のもとで行われた週3回・16週間の高速レジスタンス運動プログラムによって、情報の処理スピードや計画実行能力といった認知機能の一部、そしてバランス能力、歩行能力、筋力が改善する可能性があることが示唆されました。これは、認知フレイルの進行予防や改善に向けたアプローチとして、運動、特に「速さ」を意識した筋トレが有効である可能性を示唆するものです。
一方で、記憶力やフレイルの状態そのものへの効果は限定的であり、研究の限界点(参加者数、期間など)も考慮する必要があります。
この研究で実際に行われたプログラムは、弾性バンドを使用し、力を入れる動きを速く、戻す動きをゆっくり行い、全身の筋肉を鍛えるものでした。ご自身で運動を始める際には、安全に十分配慮し、可能であれば専門家のアドバイスを受けることが望ましいでしょう。
日々の小さな工夫と継続が、将来の元気な心と体、そして自分らしい生活を守ることに繋がります。今回の情報が、皆さんの健康づくりのヒントになれば幸いです。
参考文献
Yun DH, Lee JY, Song W. The effect of resistance exercise training on cognitive function and physical performance in cognitive frailty: a randomized controlled trial. J Nutr Health Aging. 2018; 1 22(8):958-965. doi: 10.1007/s12603-018-1090-9.
健康・医学関連情報の注意喚起:
本記事は、認知フレイルと運動に関する一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の医学的アドバイスを提供するものではありません。 認知フレイルやその他の疾患の診断や治療については、必ず医療従事者にご相談ください。