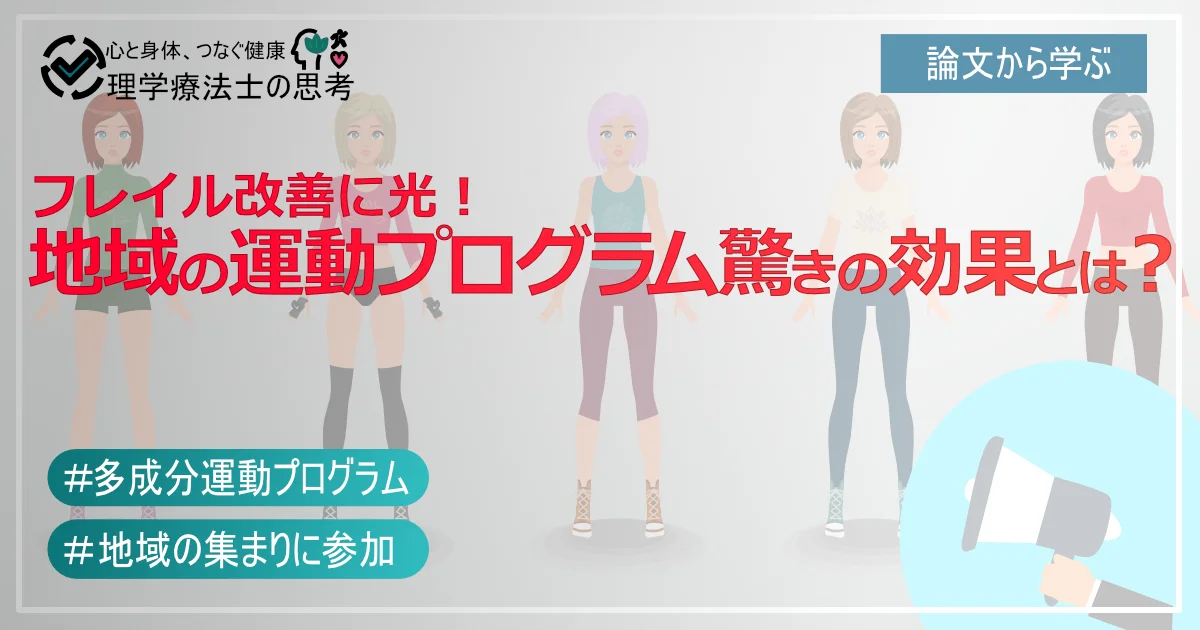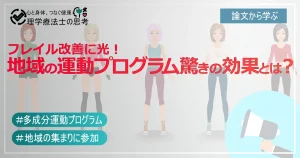「最近、足元がおぼつかない」
「疲れやすくて、外出が億劫になった」…
そんなお悩みはありませんか?
もしかしたら、それは「フレイル(虚弱)」のサインかもしれません。
フレイルは、加齢とともに多くの方が経験する可能性のある状態ですが、決して「年のせい」と諦める必要はありません。適切な対策、特に運動によって、フレイルの状態を改善したり、進行を遅らせたりできることが分かってきています。
こんにちは!理学療法士のPTケイです。
今回は、「地域で行われる運動プログラムって、本当にフレイルに効果があるの?」という疑問に答える、タイで行われた興味深い研究(ランダム化比較試験)をご紹介します。
この研究では、専門家が指導する運動と自宅での運動を組み合わせた「多成分運動プログラム」が、フレイルの高齢者にどのような影響を与えるかを詳しく調査しました。
驚きの結果と、私たちが日々の生活に取り入れられるヒントが満載ですよ!
研究紹介:フレイル改善への確かな一歩
まずは、今回ご紹介する研究の概要です。
2020年にタイの研究者ウラチャ・サジャポンらは、地域に住むフレイル高齢者に対する多成分運動プログラムが、フレイル状態、身体能力、および炎症性バイオマーカー(体内の炎症を示す指標)に与える影響についてのランダム化比較試験(研究に参加する人をランダムにグループ分けして効果を比べる信頼性の高い研究方法:エビデンスレベル2相当)を行いました。その結果、多成分運動プログラムは、フレイル状態を有意に改善し、身体能力(特にバランス)を向上させ、炎症マーカーを減少させたと報告しました。
この研究は、地域で暮らすフレイルの方々にとって、運動がいかに重要かを示す貴重なデータを提供してくれています。
どんな研究?何がわかったの?
まずは、この研究がどのようなものだったか、そして何が明らかになったのかを見ていきましょう。
【研究の概要】 この研究は、タイ北部の地域に住む、フレイル(Friedの基準で3項目以上該当)と判断された65歳以上の高齢者64名(平均年齢約78歳)を対象に行われました。参加者はランダムに2つのグループに分けられました。
- 運動プログラムグループ (MCEP群): 専門家の指導のもと、週3回、1回60分の「多成分運動プログラム(MCEP)」を12週間行い、その後さらに12週間、自宅で同様の運動を続けるよう指示されました(合計24週間)。
- 通常ケアグループ (対照群): 特別な運動プログラムは行わず、通常の医療ケアを受けました。
研究チームは、プログラム開始前、12週後、24週後に、参加者のフレイルの状態、身体能力(握力、バランス能力、歩行・移動能力、持久力)、そして血液中の炎症マーカー(IL-6、CRP)などを測定し、2つのグループ間で比較しました。
【驚きの研究結果!】 24週間のプログラムの結果、運動プログラムグループ(MCEP群)には、通常ケアグループと比較して、以下のような素晴らしい改善が見られました!
- フレイル状態が大幅に改善!: フレイルの程度を示すスコアが、プログラム開始前の平均3.18点(フレイル状態)から、12週後には1.59点、24週後には1.65点へと有意に改善しました。これはフレイルの状態から、フレイルの一歩手前の「プレフレイル」の状態まで回復したことを意味します!これは非常に大きな成果です。(群×時間交互作用 p < 0.01)
- バランス能力が向上!: 転倒リスクの指標となるバランス能力テスト(BBS: バーグバランススケール)の点数が、12週後、24週後ともに有意に向上しました。(群×時間交互作用 p < 0.01)
- 歩行・移動能力がアップ!: 椅子から立ち上がって歩き、戻ってくるまでの時間(TUG: Timed Up and Go test)が、12週後、24週後ともに有意に短縮しました。つまり、よりスムーズに動けるようになったということです。(群×時間交互作用 p < 0.01)
- 体内の炎症が軽減!: フレイルとの関連が指摘されている血液中の炎症マーカー(IL-6とCRP)が、プログラム開始12週後の時点で、通常ケアグループよりも有意に低下していました。(IL-6: p < 0.01, CRP: p < 0.05)運動が体の内部環境にも良い影響を与えたことが示唆されます。
- 用語解説:
- BBS (Berg Balance Scale): 高齢者のバランス能力を評価する標準的なテスト。14項目の動作を行い、点数が高いほどバランス能力が高いことを示します(満点56点)。
- TUG (Timed Up and Go test): 椅子から立ち上がり、3m先の目印を回って再び椅子に座るまでの時間を測定するテスト。移動能力や転倒リスクの評価に用いられ、時間が短いほど能力が高いことを示します。
- IL-6 (インターロイキン6), CRP (C反応性タンパク質): 体内で炎症が起きているときに増加する物質。これらの値が高いと、慢性的な炎症状態にある可能性を示唆します。
【少し課題も見えた点】 一方で、全てが改善したわけではありませんでした。
- 握力や持久力(VO2Max)については、12週時点では改善が見られたものの、24週間の研究期間全体で見ると、通常ケアグループとの間に明確な差は認められませんでした。
- また、プログラム後半の自宅での運動については、参加者の継続率(アドヒアランス)がやや低め(約58%)だったことも報告されています。これが、握力や持久力の効果が持続しなかった一因かもしれません。
しかし、最も重要なことは、この運動プログラムが安全に行われ、参加者に大きな怪我や転倒を引き起こさなかったという点です。
この研究結果は、地域で行われる多成分運動プログラムが、フレイル高齢者の身体機能、特に転倒に繋がりやすいバランス能力を改善し、フレイル状態そのものを軽減する上で有効かつ安全であることを強く示唆しています。さらに、体内の炎症状態にも良い影響を与える可能性があることも分かりました。
研究で行われた「多成分運動プログラム」の中身を大公開!
では、実際にどのような運動プログラムが行われたのでしょうか? フレイル改善に繋がったプログラムの中身を見てみましょう。
この研究のプログラムは、「多成分」という名前の通り、様々な要素を組み合わせていました。
- 期間: 合計24週間
- 前半12週間:地域のヘルスセンターに週3回集まり、専門家の指導のもとでグループ運動(センターベース)
- 後半12週間:自宅で各自運動を継続(ホームベース)。運動記録をつけ、週に1回スタッフからのフォローアップあり。
- 1回の時間: 約60分(ウォームアップ、メイントレーニング、クールダウン含む)
- 運動の種類(メイントレーニング部分):
- 椅子に座って行う有酸素運動 (約15分): 心肺機能を高める目的。足踏み、腕振り、簡単な体操などを音楽に合わせて行いました。体力に合わせて徐々に運動時間を長くしていきました。
- セラバンド(ゴムバンド)を使った筋力トレーニング (約30分): 筋力・パワー向上が目的。腕、脚、体幹など全身10種類の運動を、座ったまま行いました。バンドの色で抵抗(負荷)を調整し、「ややきつい」と感じる強度で、最初は8回×2セット程度から始め、徐々に回数・セット数・強度を上げていきました(漸進性)。
- バランス訓練 (約15分): 転倒予防が目的。椅子からの立ち座り、横歩き、かかと・つま先歩き、片足立ちなどを、最初は手すりなどを使って安全に行い、慣れてきたら支えなしで行うように進めました。
このように、有酸素運動、筋力トレーニング、バランス訓練という3つの要素を組み合わせ、専門家の指導のもとで安全に開始し、それを自宅で継続するという流れでした。強度も個人の状態に合わせて調整し、徐々にレベルアップしていく工夫がされていました。
このプログラムから学べるのは、フレイル対策には様々な運動を組み合わせること、そして専門家のアドバイスを受けながら安全に始め、それを継続していくことが重要だということです。後半の自宅での運動継続率がやや低かった点は、今後の課題ですが、地域でのサポート体制を整えることで改善できるかもしれませんね。
運動を安全に、そして楽しく続けるために
この研究でも示されたように、運動は安全に行うことが大前提です。
- 運動前後のウォーミングアップとクールダウン(ストレッチなど)を忘れずに行いましょう。
- 「ややきつい」と感じる程度を目安にし、決して無理はしないでください。痛みを感じたらすぐに中止しましょう。
- バランス運動などは、転倒しないように必ず安定した壁や手すりの近くで行いましょう。
- 水分補給もこまめに行いましょう。
- 特に持病(心臓病、高血圧、糖尿病、関節の痛みなど)がある方や、体力に自信のない方は、運動を始める前に必ず医師や理学療法士などの専門家に相談し、自分に合った運動の種類や強度についてアドバイスを受けてください。
そして、何より楽しむことが継続の秘訣です! 好きな音楽をかけたり、家族や友人と一緒に取り組んだり、小さな目標を立てて達成感を味わったりするのも良いでしょう。
まとめ
今回のタイでの研究は、私たちに希望を与えてくれるものでした。
- 地域で行う「多成分運動プログラム」は、フレイル高齢者の状態を改善するのに有効です。 特に、転倒リスクに直結するバランス能力の向上が顕著でした。
- 運動は、体の外側の機能だけでなく、体内の炎症状態にも良い影響を与える可能性があります。
- プログラムは安全に実施可能でしたが、自宅での運動を継続するには工夫やサポートが必要なことも分かりました。
フレイルは「年のせい」と片付けられがちですが、適切な運動によって立ち向かうことができる状態です。もしご自身やご家族のフレイルが気になる場合は、お住まいの地域で提供されている運動教室や介護予防プログラムなどを調べてみるのも良いかもしれません。また、かかりつけ医や理学療法士に相談して、安全に始められる運動のアドバイスをもらうのも有効です。
今日からできる小さな一歩が、未来の元気と笑顔につながります。ぜひ、運動を始めるきっかけにしてくださいね。
参考文献
Sajapong U, Yodkeeree S, Sungkarat S, Siviroj P. Multicomponent Exercise Program Reduces Frailty and Inflammatory Biomarkers and Improves Physical Performance in Community-Dwelling Older Adults: A Randomized Controlled Trial. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(11): 1 3828. Published 2020 May 28. doi:10.3390/ijerph17113828
健康・医学関連情報の注意喚起:
本記事は、フレイルと運動に関する一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の医学的アドバイスを提供するものではありません。 フレイルやその他の疾患の診断や治療については、必ず医療従事者にご相談ください。