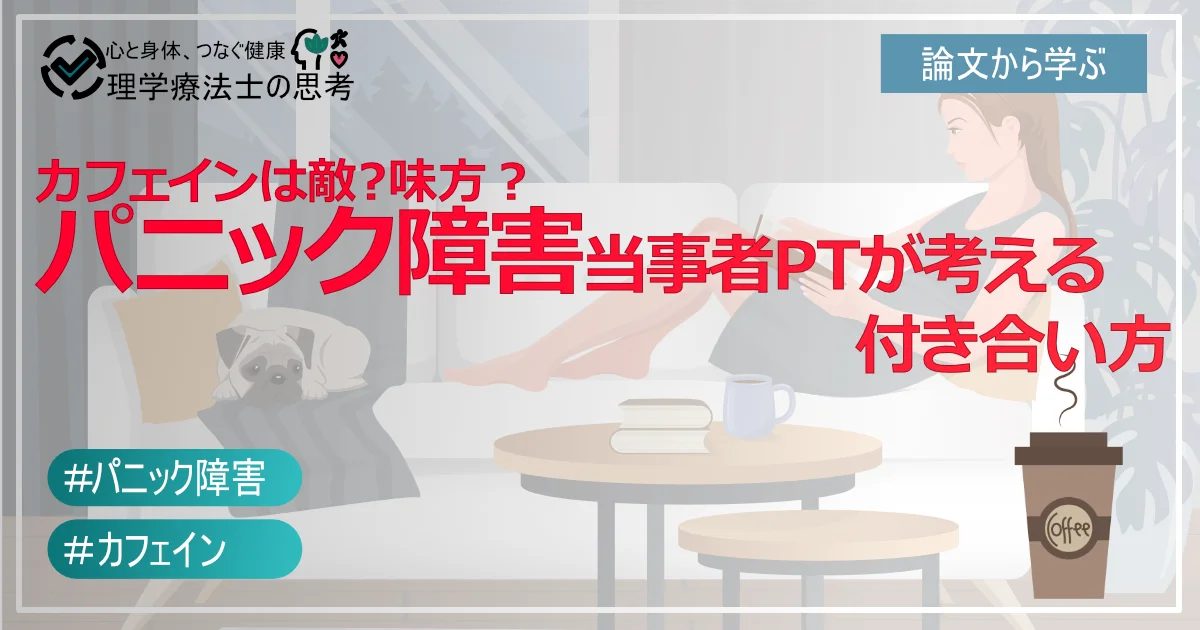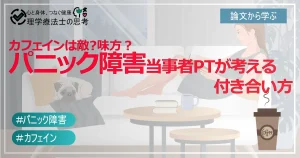コーヒーや紅茶、エナジードリンク…。私たちの日常には、カフェインを含む飲み物や食べ物が溢れています。集中力を高めたい時や、眠気を覚ましたい時に、カフェインの力を借りている方も多いのではないでしょうか?
しかし、もしあなたがパニック障害や強い不安を感じやすい場合、そのカフェイン摂取、少し立ち止まって考えてみる必要があるかもしれません。
こんにちは!あなたの心と体の健康をサポートする理学療法士であり、実は私自身もパニック障害と共に生きるPTケイです。
私自身の経験からお話しすると、パニック障害を発症してからというもの、以前は何ともなかったコーヒー1杯程度のカフェインでも、急に手が震えたり、心臓がドキドキしたり、そして何とも言えない不安感が強まったりすることがあります。そのため、今はできるだけカフェインを避ける生活を送っています。
これは私個人の体験ですが、「カフェインを摂ると不安になる」「動悸がする」と感じているパニック障害当事者の方は、意外と少なくないのではないでしょうか?
今回は、そんなパニック障害とカフェインの関係について、最新の信頼できる研究報告(系統的レビューとメタアナリシス)を基に、科学的な視点から分かってきたこと、そして私自身の体験も交えながら、カフェインとの上手な付き合い方について考えていきたいと思います。
研究紹介:カフェインはパニック障害にどう影響する?
まずは、今回参考にする研究の概要です。
2022年にスウェーデンの研究者リサ・クレベブラントらは、パニック障害(PD)患者の不安およびパニック発作に対するカフェインの影響に関する系統的レビューとメタアナリシス(複数の信頼できる研究結果を統合・分析する手法)を行いました。その結果、高用量のカフェインは、PD患者において健常者よりも有意に高い確率でパニック発作を誘発し、また両群の不安を増強させる(PD患者でより顕著な傾向)と報告しました。
この研究は、これまでに行われた複数の「カフェインチャレンジ」と呼ばれる実験(カフェインを飲んでもらい反応を見る実験)の結果をまとめたもので、パニック障害とカフェインの関係を科学的に検証した重要な報告です。
研究でわかった衝撃の事実:高用量カフェインとパニック発作
この研究で最も注目すべき結果は、比較的高用量のカフェインが、パニック障害(PD)を持つ人のパニック発作を誘発するリスクが非常に高いということです。
研究チームが分析した複数の実験結果を統合すると、
- PD患者さんの約半数(51.1%)が、カフェイン摂取後にパニック発作を起こしていた
- 一方、プラセボ(カフェインの入っていない偽薬)を摂取した場合には、発作は起きていなかった
- 健康な人(HC)と比較すると、PD患者さんはカフェインによってパニック発作を起こすリスクが、健康な人に比べて格段に高い(リスク比で約3.5倍と報告されています)
という衝撃的な事実が明らかになりました。
では、ここでいう「高用量のカフェイン」とは、どのくらいの量なのでしょうか? レビューされた研究の多くで使われていたのは480mgという量でした。これは、一般的なドリップコーヒーに換算すると、およそ4~5杯分に相当します(コーヒーの種類や淹れ方によってカフェイン量は異なります)。他の研究では400mg~750mg(コーヒー約4~7.5杯分)の範囲が用いられていました。
もちろん、これは実験的な状況での結果であり、日常生活で一度にこれほどの量のカフェインを摂取する方は少ないかもしれません。
しかし、パニック障害を持つ人は、カフェインによるパニック発作誘発に対して、特に敏感である可能性が強く示唆されたと言えます。
不安も増強?カフェインのもう一つの影響
パニック発作だけでなく、カフェインは不安感を強める可能性も示されました。
メタアナリシスの結果、
- カフェインを摂取した後、PD患者さんと健康な人の両方で、主観的な不安感が増加した
- 不安の増加度合いは、健康な人と比べてPD患者さんの方が大きい傾向があった
ということが分かりました。
ただし、不安への影響については、研究ごとの結果にばらつき(異質性)が大きく、パニック発作誘発効果ほど一貫した結果ではありませんでした。また、プラセボ(偽薬)を飲んだ時の不安の変化に関するデータが不足していたため、「カフェインが純粋にどれだけ不安を増やすか」を正確に評価するのは難しい、という限界も指摘されています。
それでも、カフェインが不安感を増強させる可能性があること、そしてパニック障害を持つ人はその影響をより受けやすいかもしれないということは、心に留めておくべき情報でしょう。
注意点:用量と反応の関係は?
ここで重要な注意点があります。このレビュー研究で分析された実験の多くは、480mg(コーヒー約5杯分)という比較的高用量のカフェインを使用していました。
そのため、
- もっと少ない量(例えばコーヒー1杯程度)のカフェインで、どの程度の影響があるのか?
- どれくらいの量からパニック発作や不安のリスクが高まるのか? といった「用量と反応の関係」については、今回の研究からは明らかになっていません。
つまり、「高用量のカフェインはリスクが高い」とは言えますが、「少ない量なら絶対に安全」あるいは「どの量から危険」とは、この研究だけでは断定できないのです。ここが、カフェインとの付き合い方を考える上で難しい点でもあります。
身近なカフェイン:どこに含まれている?メリット・デメリットも
カフェインは私たちの身近な多くの飲食物に含まれています。「これにも入っていたの?」と驚くこともあるかもしれません。主なものと、一般的な含有量の目安を見てみましょう。ただし、これから示す含有量はあくまで目安であり、製品の種類、抽出方法(コーヒーや紅茶の淹れ方)、カカオの含有率などで大きく変動しますのでご注意ください。
- コーヒー:
- ドリップコーヒー:1杯(約150ml)あたり 約60mg~100mg程度
- インスタントコーヒー:1杯(約150ml)あたり 約65mg程度
- 紅茶: 1杯(約150ml)あたり 約30mg程度
- 緑茶(煎茶):1杯(約150ml)あたり 約30mg程度
- (参考)玉露はより多く(約160mg/100ml抽出液)、ほうじ茶や玄米茶はやや少なめ(約20mg/150ml)の傾向があります。
- エナジードリンク: 1本(250mlなど)あたり 約80mg~150mg以上含まれるものも。製品による差が非常に大きいです。缶やボトルに記載されている総量を確認しましょう。
- コーラなどの一部の炭酸飲料: 350mlあたり 約30mg~40mg程度
- チョコレート、ココア:
- ミルクチョコレート:1枚(50g)あたり 約10mg程度
- ハイカカオチョコレート:カカオ含有率が高いほどカフェイン量も多くなる傾向があります(例:70%カカオ 50gあたり 約40mg程度)。
- ココア:1杯あたり 約10mg~20mg程度
- 一部の医薬品: 風邪薬、鎮痛剤、眠気防止薬などには、眠気覚ましの目的などで1錠あたり50mg~100mg程度のカフェインが含まれている場合があります。使用前に必ず添付文書を確認しましょう。
| 飲食物の種類 | 単位(目安) | カフェイン含有量(目安) | 備考 |
| コーヒー | |||
| ドリップコーヒー | 1杯 (約150ml) | 約 60mg ~ 100mg | 豆の種類や淹れ方で変動 |
| インスタントコーヒー | 1杯 (約150ml) | 約 65mg | |
| お茶類 | |||
| 紅茶 | 1杯 (約150ml) | 約 30mg | |
| 緑茶(煎茶) | 1杯 (約150ml) | 約 30mg | 玉露は非常に多く(約160mg/100ml)、 ほうじ茶・玄米茶は少ない(約20mg/150ml)傾向があります。 |
| 飲料 | |||
| エナジードリンク | 1本 (250ml等) | 約 80mg ~ 150mg以上 | 製品差が大きい。必ず表示を確認してください。 |
| コーラ類 | 1缶 (約350ml) | 約 30mg ~ 40mg | |
| 菓子類 | |||
| ミルクチョコレート | 1枚 (50g) | 約 10mg | |
| ハイカカオチョコレート | 1枚 (50g) | 約 40mg (70%カカオの場合) | カカオ含有率が高いほど多くなる傾向。 |
| ココア | 1杯 | 約 10mg ~ 20mg | |
| その他 | |||
| 医薬品 | 1錠/1回分など | 約 50mg ~ 100mg (製品による) | 風邪薬、鎮痛剤、眠気防止薬など。 必ず添付文書を確認してください。 |
このように、特にコーヒーやエナジードリンクはカフェイン含有量が多いことが分かりますね。意外なものに含まれていることもあるので、気になる方は成分表示を確認する習慣をつけると良いかもしれません。
そして、カフェインには良い面と悪い面の両方があります。
【カフェインのメリット】
- 眠気を覚ます(覚醒作用)
- 集中力や注意力を高める
- 疲労感を軽減する
- 気分を高揚させる
- 運動能力を向上させる可能性
- (一部の研究では)抑うつ気分の改善や予防効果の可能性
【カフェインのデメリット】
- 不安感を増強させる
- 不眠を引き起こす
- 動悸、手の震え、めまいなどを引き起こす(交感神経の刺激)
- 胃腸の不調(胃痛、吐き気など)
- 頭痛(特に摂取をやめた時の離脱症状として)
- 頻脈、血圧上昇
- 依存性
このように、カフェインは「諸刃の剣」とも言える物質です。メリットを享受できる人もいれば、デメリットの影響を強く受けてしまう人もいるのです。
PTケイの体験談とカフェインとの付き合い方
ここで、少しだけ私自身の話をさせてください。先ほども触れましたが、私はパニック障害と診断されています。診断される前は、コーヒーが好きで毎日何杯も飲んでいましたし、特にそれで体調が悪くなることはありませんでした。
しかし、パニック障害を発症してからは、カフェインに対する体の反応が明らかに変わりました。今では、ドリップコーヒーをマグカップに1杯飲むだけでも、私にとっては摂りすぎになるようで、数時間後に動悸や手の震えが出たり、理由のない不安感が強まったりするのを感じます。まるで、体の「警戒スイッチ」が過剰に入ってしまうような感覚です。エナジードリンクなどは、さらに顕著に症状が出ます。
そのため、今はコーヒーや紅茶、緑茶などを飲む際は、カフェインレス(デカフェ)のものを選ぶようにしています。特に大好きなコーヒーは1杯でも症状が出やすいと感じるので、飲むならカフェインレスと決めています。 ただ、高カカオチョコレートも好きなので、こちらは全く食べないわけではありませんが、食べる量や頻度には気をつけるようにしています。このように、できる範囲でカフェイン摂取をコントロールしています。正直、コーヒーの香りや味が好きなのでカフェインレスは少し寂しい気持ちもありますが、症状の引き金になるかもしれないものを避けることで、安心して過ごせる時間が増えたと感じています。
ただし、これはあくまで私個人の体験です。パニック障害を持つ方全員が、私と同じようにカフェインに敏感に反応するわけではありません。中には、適量のカフェイン摂取なら問題ない、むしろ気分転換になるという方もいらっしゃるでしょう。
大切なのは、「パニック障害だからカフェインは絶対ダメ!」と決めつけるのではなく、ご自身の体調や症状と相談しながら、自分にとっての適切な付き合い方を見つけることだと思います。
研究結果が示すように、高用量のカフェインは明らかにリスクを高める可能性があります。しかし、低~中用量の影響は個人差が大きいため、
- 自分がどれくらいのカフェイン量で、どのような反応が出るのかを観察してみる
- 不安やパニック発作の前にカフェインを摂取していなかったか、記録をつけてみる
- もしカフェインとの関連が疑われる場合は、摂取量を減らしてみる、または一時的にやめてみる
- 判断に迷う場合や、症状が辛い場合は、必ず医師や専門家に相談する
といったステップを踏むことが有効ではないでしょうか。過度に恐れる必要はありませんが、「もしかしたら関係あるかも?」という視点を持っておくことは大切だと思います。
まとめ
今回は、パニック障害とカフェインの関係について、最新の系統的レビュー・メタアナリシスの結果と、私自身の体験談を交えながらお話ししました。
- 高用量(コーヒー約4~5杯以上)のカフェインは、パニック障害(PD)を持つ人のパニック発作を誘発するリスクを、健康な人より著しく高めることが科学的に示されました。
- カフェインは、PD患者さんと健康な人の両方で不安感を増強させる可能性がありますが、特にPD患者さんの方が影響を受けやすい傾向があります。
- ただし、レビューされた研究の多くが高用量であり、一般的な摂取量(コーヒー1杯程度)での影響や、どの量からリスクが高まるかは、個人差も大きく、まだよく分かっていません。
- カフェインにはメリット(覚醒、集中力UPなど)とデメリット(不安、不眠、動悸など)があり、その影響は人それぞれです。
- カフェインとの付き合い方は、ご自身の体調や症状をよく観察し、必要であれば専門家と相談しながら、個別に判断することが大切です。
カフェインは私たちの生活に深く根付いています。だからこそ、その特性を正しく理解し、自分の体と心に耳を傾けながら、上手に付き合っていくことが、穏やかな毎日を送るための一助となるのではないでしょうか。
参考文献
Kleeberg L, Frick A. The effects of caffeine on anxiety and panic attacks in patients with panic disorder: A systematic review and meta-analysis. Gen Hosp Psychiatry. 2022;74:22-31. doi:10.1016/j.genhosppsych.2021.11.005
健康・医学関連情報の注意喚起:
本記事は、パニック障害とカフェインに関する一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の医学的アドバイスを提供するものではありません。 パニック障害やその他の疾患の診断や治療、カフェイン摂取に関する判断については、必ず医療従事者にご相談ください。