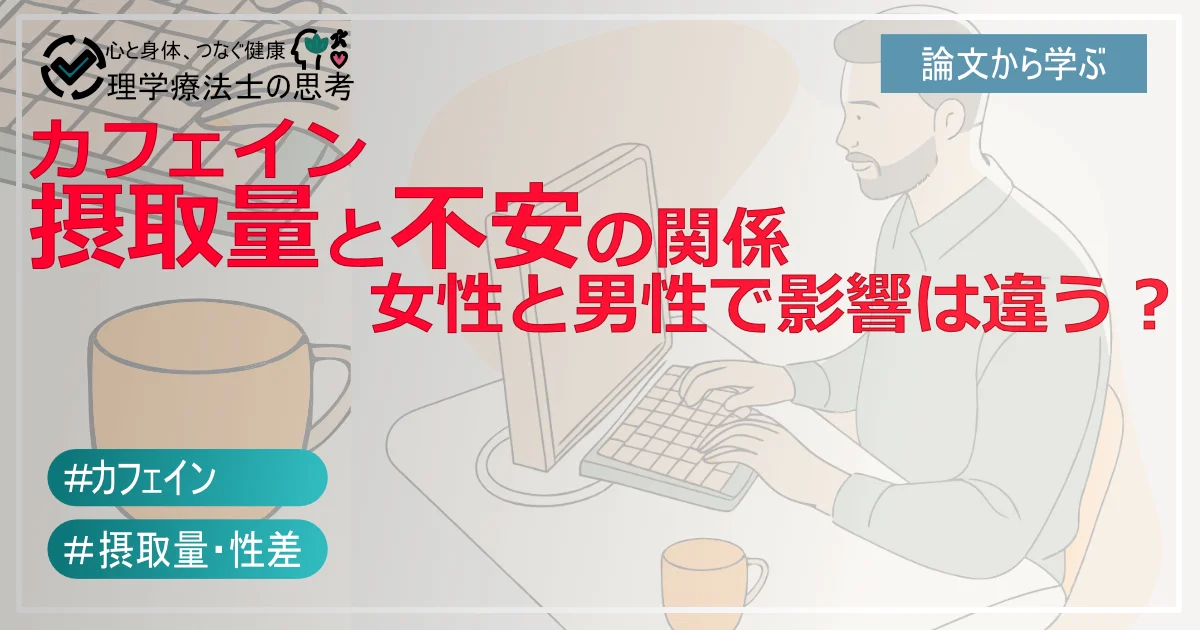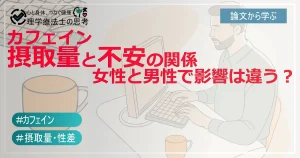「コーヒーを飲まないと一日が始まらない!」
「仕事中にエナジードリンクで気合を入れる」
カフェインは、私たちの生活にとって非常に身近で、時には頼りになる存在ですよね。でも、その一方で、「カフェインを摂りすぎると体に良くない」「不安になる」といった話も耳にします。
「いったい、どれくらいの量から気を付けるべきなの?」
「不安やパニック障害がある場合、カフェインは避けた方がいいの?」
そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
こんにちは!理学療法士であり、パニック障害当事者でもあるPTケイです。
今回は、カフェインの「量」に注目して、不安やパニック発作のリスクとどう関係しているのか、最近発表された2つの重要な研究(複数の研究をまとめたメタアナリシスと、大規模な一般集団調査である横断研究)の結果を読み解きながら、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。この研究からは、興味深い「性差」も見えてきました。
研究紹介:日常的なカフェイン摂取と不安の関連を探る
まずは、今回メインでご紹介する研究の概要です。
2022年にフランスなどの研究グループ(筆頭著者:インディラ・パス・グラニエル)は、一般成人集団におけるカフェイン摂取量とその性特異的な一般的な不安との関連についての横断分析を行いました。
この研究は、フランスの大規模ウェブコホート「NutriNet-Santé」に参加している約2万4千人(平均年齢約54歳、約74%が女性)のデータを用いて、普段の食事からのカフェイン摂取量と、質問票(STAI-T)で評価された不安を感じやすい傾向(特性不安)との関連性を調べたものです。(Paz-Graniel I, et al. Nutrients. 2022)
この研究は「横断研究」というデザインで、ある一時点でのカフェイン摂取量と不安の関係を見たものです。そのため、「カフェインが原因で不安になった」という因果関係を証明するものではない点に注意が必要ですが、日常的な摂取習慣と不安傾向の関連を探る上で重要な手がかりを与えてくれます。
研究結果①:女性ではカフェイン摂取量と不安に関連が?
この大規模調査の結果、まず女性において興味深い関連が見られました。
参加女性を日常的なカフェイン摂取量によって3つのグループ(少ない・中間・多い)に分けて分析したところ、
- カフェイン摂取量が最も多いグループ(平均約389mg/日、コーヒー約4杯弱に相当)は、最も少ないグループ(平均約62mg/日)に比べて、不安傾向が高い人の割合が約1.13倍、統計的にも有意に高かった
- 摂取量が中間のグループ(平均約186mg/日)でも、最も少ないグループに比べて不安傾向が高い人の割合が約1.10倍と、こちらも有意に高かった
という結果でした。
これは、女性の場合、日常的に摂取するカフェインの量が多いほど、不安を感じやすい傾向も高い可能性があることを示唆しています。特に、摂取量が中間(コーヒー2杯弱程度)のグループでも関連が見られた点は注目に値するかもしれません。
研究結果②:男性では関連が見られず… なぜ性差が?
一方で、男性においては、カフェイン摂取量と不安傾向の間に統計的に有意な関連は見られませんでした。
なぜこのような性差が見られたのでしょうか? 研究者たちは、いくつかの可能性を考察しています。
- ホルモンの違い: 女性ホルモン(エストロゲンなど)が不安やストレス反応に関与している可能性。
- ストレスへの対処法の違い: 女性は不安な時に反芻思考(ぐるぐる考え込む)に陥りやすい傾向がある一方、男性は問題解決や気晴らしで対処しようとする傾向があり、その違いが影響している可能性。
- カフェイン摂取の動機や種類の違い: 男性の方がコーヒー消費が多く、女性の方がお茶の消費が多い傾向がこの研究でも見られましたが、コーヒーに含まれる他の成分(ポリフェノールなど)がカフェインの不安作用を和らげる可能性なども考えられます。(ただし、カフェイン源による影響の違いはまだ不明な点が多いです)
この性差については、さらなる研究が必要ですが、カフェインの影響が男女で異なる可能性がある点は非常に興味深いですね。
結果の解釈と限界:因果関係は不明
ここで改めて強調したいのは、この研究は横断研究であるということです。つまり、「カフェインを多く摂っている女性は、不安傾向も高い」という関連性は示されましたが、
- カフェイン摂取が原因で不安が高くなったのか?
- もともと不安傾向が高い女性が、気分転換や覚醒効果を求めてカフェインを多く摂取しているのか?
- あるいは、全く別の要因(例:睡眠不足、ストレスレベルなど)が両方に関係しているのか?
といった因果関係の方向性までは、この研究だけでは分かりません。
また、不安の評価は質問票によるもので、臨床的な不安障害の診断とは異なります。カフェイン摂取量も自己申告の食事記録に基づいているため、サプリメントなどが考慮されていない、などの限界もあります。
量による違いを考える:高用量リスクと日常量の関連性
さて、今回のテーマである「カフェインの量による違い」について、前回のメタアナリシスの結果と合わせて考えてみましょう。
- 高用量(400mg~750mg、コーヒー約4~7.5杯分):
- 前回のメタアナリシスで示されたように、特にパニック障害を持つ人にとっては、パニック発作を誘発する明確かつ高いリスクがあります。
- また、パニック障害の有無に関わらず、不安感を増強させる可能性が高いと考えられます(特にPD患者)。
- 日常的な量(今回の研究では平均60mg~390mg/日程度):
- 今回の横断研究では、女性において、この範囲でも摂取量が多いほど不安傾向が高いという関連性が見られましたが、これはあくまで関連性であり、因果関係は不明です。男性では関連が見られませんでした。
- パニック発作に関しては、この程度の量で誘発されるかどうかは、前回のメタアナリシスではデータ不足で不明でした。
つまり、「高用量は明らかにリスクが高い」と言えますが、「日常的な量が不安やパニックにどう影響するか」は、まだハッキリとは分かっておらず、特に性別や個人の体質による差が大きいのかもしれません。
身近なカフェイン:含有量を知っておこう
自分にとってのカフェインとの付き合い方を考える上で、普段どれくらい摂取しているかを知ることは第一歩です。改めて、主な飲食物のカフェイン含有量の目安(変動あり)を確認しましょう。
ただし、これから示す含有量はあくまで目安であり、製品の種類、抽出方法(コーヒーやお茶の淹れ方)、カカオの含有率などで大きく変動します。ご自身の摂取量を正確に知りたい場合は、製品の表示を確認することが最も確実です。
| カテゴリ | 飲食物の種類 | 単位(目安) | カフェイン含有量(目安) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| コーヒー類 | ドリップコーヒー | 1杯 (約150ml) | 約 60mg ~ 100mg | 豆、淹れ方で変動大 |
| インスタントコーヒー | 1杯 (約150ml) | 約 65mg | ||
| カフェインレス/デカフェ | 1杯 (約150ml) | 数mg以下 | 完全にゼロではない場合が多い | |
| お茶類(茶葉由来) | 玉露 | 1杯 (約60ml想定) | 約 100mg | 高濃度注意! 抽出方法で大きく変動 (抽出液100mlあたり約160mg) |
| 抹茶(薄茶) | 1杯 (抹茶 約2g) | 約 64mg | 茶葉ごと摂取するため比較的高め | |
| 紅茶 | 1杯 (約150ml) | 約 30mg | ||
| 緑茶(煎茶) | 1杯 (約150ml) | 約 30mg | ||
| ウーロン茶 | 1杯 (約150ml) | 約 30mg | 発酵度合いにより差あり | |
| ほうじ茶 | 1杯 (約150ml) | 約 20mg | 焙煎によりカフェイン減少 | |
| 玄米茶 | 1杯 (約150ml) | 約 10mg | 茶葉量が少ないため | |
| マテ茶 | 1杯 (約150ml) | 約 20mg ~ 50mg | 製品・淹れ方による | |
| その他の飲料 | エナジードリンク | 1本 (250ml等) | 約 80mg ~ 150mg以上 | 製品差大。要表示確認。 糖分量にも注意。 |
| 栄養ドリンク/滋養強壮剤 | 1本 | 数十mg程度 | 製品による。医薬部外品など。要表示確認。 | |
| コーラ類 | 350mlあたり | 約 30mg ~ 40mg | ||
| 菓子・食品類 | ハイカカオチョコレート | 1枚 (50g) | 約 40mg (70%カカオの場合) | カカオ%が高いほど多い。 |
| ミルクチョコレート | 1枚 (50g) | 約 10mg | ||
| ココア | 1杯 | 約 10mg ~ 20mg | ピュアココアか調整ココアかで差あり | |
| コーヒーゼリー/菓子 | 1個/1食分 | 微量~数十mg程度 | 製品による。 | |
| 機能性食品・医薬品 | カフェイン入りガム/タブレット | 1粒/1錠 | 数十mg ~ 100mg以上 | 製品差大。要表示確認。 眠気覚まし目的など。 |
| 医薬品 | 1錠/1回分など | 約 50mg ~ 100mg (製品による) | 風邪薬、鎮痛剤、眠気防止薬など。必ず添付文書を確認。 |
カフェインの光と影:メリット・デメリット
カフェインとの付き合い方を考える上で、良い面と悪い面の両方を知っておくことも大切です。
【カフェインのメリット】
- 眠気覚まし、集中力UP、疲労感軽減
- 気分を高揚させる
- 運動能力向上(可能性)
- 抑うつ気分改善・予防(可能性)
【カフェインのデメリット】
- 不安増強
- 不眠
- 動悸、手の震え、めまい
- 胃腸障害
- 頭痛(離脱症状)
- 依存性
PTケイの視点:カフェインとの距離感を測る
今回の研究結果(女性で不安との関連が見られた)と、前回の研究結果(高用量でパニックリスク)を合わせて考えると、やはりパニック障害や不安を感じやすい方は、カフェイン摂取に対して少し慎重になった方が良いのかもしれない、と改めて感じます。
私自身、コーヒー1杯(カフェイン量としては今回の研究の中~低用量群程度)でも動悸や不安を感じやすいため、カフェインレスを選んでいます。高カカオチョコレートは好きで少し食べますが、量や時間帯には気をつけています。
これは、私が自分の体と向き合った結果、見つけた現時点での「私にとっての適切な距離感」です。
皆さんにお伝えしたいのは、「絶対ダメ」ではなく、自分の体の声を聞くことの重要性です。
- 普段どれくらいカフェインを摂っているか?(上記の表も参考に)
- カフェインを摂った後、体調(特に不安、動悸、睡眠)に変化はないか?
- もし関連を感じるなら、少し量を減らしたり、カフェインレスを試したりしてみる。
- 不安なら、医師や専門家に相談する。
このように、研究結果は参考にしつつも、最終的にはご自身の感覚と専門家のアドバイスに基づいて、カフェインとの付き合い方を探っていくのが良いのではないでしょうか。
まとめ
今回は、日常的なカフェイン摂取と不安の関係を調べた大規模な横断研究を中心に、カフェインの「量」による影響について考えてきました。
- 女性では、日常的なカフェイン摂取量が多いほど不安傾向が高いという関連が見られましたが、男性では見られませんでした(ただし、因果関係は不明)。
- 前回の研究結果と合わせると、高用量のカフェインはパニック障害のリスクを高める可能性が高い一方、低~中程度の日常的な量の影響は、個人差や性差が大きく、まだはっきりとは分かっていません。
- カフェインにはメリットもデメリットもあります。自分にとっての適切な摂取量や付き合い方を、体調を観察しながら見つけることが大切です。
- 不安症状が強い場合や、カフェインとの関連について判断に迷う場合は、必ず専門家に相談しましょう。
カフェインと上手に付き合っていくためのヒントとして、今回の情報が少しでもお役に立てば嬉しいです。
参考文献:
- Paz-Graniel I, Babio N, Hercberg S, Galan P, Touvier M, Salas-Salvadó J, Andreeva VA. Caffeine Intake and Its Sex-Specific Association with General Anxiety: A Cross-Sectional Analysis in the Adults from the General Population. Nutrients. 2022;14(6):1304. Published 2022 Mar 19. doi:10.3390/nu14061304
- Kleeberg L, Frick A. The effects of caffeine on anxiety and panic attacks in patients with panic disorder: A systematic review and meta-analysis. Gen Hosp Psychiatry. 2022;74:22-31. doi:10.1016/j.genhosppsych.2021.11.005 (前回の記事で参照)
健康・医学関連情報の注意喚起:
本記事は、カフェインと不安に関する一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の医学的アドバイスを提供するものではありません。 パニック障害やその他の疾患の診断や治療、カフェイン摂取に関する判断については、必ず医療従事者にご相談ください。