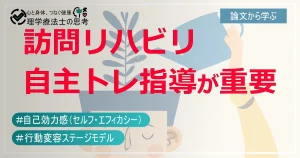こんにちは!PTケイです。
実は私2025年6月から訪問看護ステーションで働くことになりまして、今はその準備のために日々勉強に励んでいます。在宅でのリハビリテーションについて学ぶ中で、特に「自主練習のサポート」の重要性を改めて感じているところなんです。
ご利用者さんやご家族から、 「訪問リハビリ、週に1回だけじゃ物足りない…」 「家での自主練習、何をどれだけやればいいの?」 「やる気はあるけど、なかなか続かないんだよね…」 といったお悩みをよく伺いますよね。これは、これから私が働く訪問の現場でも、きっと多くの方が直面する課題だと感じています。
特に骨折や変形性関節症などの骨関節疾患をお持ちの場合、ご自宅での自主練習は、回復を促し、できることを維持・向上させていくために非常に重要です。しかし、その大切さは分かっていても、継続するのは難しいもの…。
そこで今回の記事では、まさに私が今勉強しているテーマでもある、在宅での自主練習を「やらなきゃ」から「やりたい!」に変えるためのヒントを、最新の研究論文を基に分かりやすく解説していきます。この記事を読めば、あなたに合った自主練習の進め方や、モチベーションを保つコツが見つかるはずです。私自身の学びも深めながら、皆さんと一緒に考えていきたいと思います!
最新研究が示す!自主練習継続のための「カギ」
まずは、今回参考にした研究をご紹介します。
2024年に日本で発表された大沼剛氏らの総説「在宅で訪問リハビリテーションを利用する骨関節疾患に対する自主練習の考え方」では、訪問リハビリテーションを利用する骨関節疾患の方が、どのようにすれば自主練習を効果的に続けられるかについて、様々な角度から分析・考察されています。
この研究では、単に運動メニューをこなすだけでなく、利用者さん一人ひとりの状態や心理的な側面(「自分にもできそう!」という自信や、行動を変えるための心の準備段階)を考慮したサポートが不可欠であると強調されています。 また、分かりやすいパンフレットなどのツールを活用したり、適切な目標設定とリスク管理を行うことの重要性も示されています。
つまり、根性論ではなく、科学的なアプローチに基づいた「続けられる仕組みづくり」が大切、ということですね。
なぜ自主練習が続かない?3つの壁と乗り越えるヒント
「自主練習が大切と分かっていても、三日坊主になってしまう…」そんな経験はありませんか?この論文では、自主練習がなかなか定着しない理由とその対策について、いくつかの重要な視点が示されています。
1. 「何をすれば良いか分からない」の壁:目的と効果の明確化
「どんな運動をすればいいの?」「この運動、本当に効果があるの?」といった疑問は、自主練習の大きな障壁となります。 ただ漠然と「これをやってください」と言われるだけでは、なかなかやる気には繋がりませんよね。
乗り越えるヒント: 理学療法士などの専門家は、利用者の方に自主練習を提案する際、その運動が「何のために行うのか」「どのような効果が期待できるのか」を具体的に説明することが重要です。 例えば、「この運動は、立ち上がりをスムーズにするための太ももの筋肉を鍛えますよ」「このストレッチで、膝の痛みが和らぎ、歩きやすくなります」といった具体的な言葉で伝えることで、利用者さんは目的意識を持って取り組むことができます。
2. 「やる気が出ない・続かない」の壁:自己効力感と行動変容ステージ
「どうせやっても変わらない…」「面倒くさいな…」と感じてしまうのは、心理的な要因が影響しているかもしれません。カナダの心理学者アルバート・バンデューラが提唱した「自己効力感(セルフエフィカシー)」、つまり「自分ならできる!」という自信が低いと、行動に移しにくくなります。
また、人は行動を変える際に、いくつかの心理的な段階を経ると言われています。これを「行動変容ステージモデル」と呼びます。 例えば、「まだ自主練習なんて考えてもいない(無関心期)」という方と、「そろそろ始めようかな(関心期・準備期)」という方では、アプローチの仕方が異なります。
乗り越えるヒント:
- 自己効力感を高める工夫:
- 達成体験: 簡単な運動から始め、少しずつ「できた!」という成功体験を積み重ねる。
- 代理体験: 他の人が自主練習で良くなった事例を聞いたり見たりする。 例えば、「同じような膝の痛みがあった〇〇さんも、この体操を続けて楽になったそうですよ」といった情報提供も有効です。
- 言語的説得: 専門家から「あなたならこの運動は安全にできますよ」「続ければきっと良くなりますよ」といった励ましや具体的なアドバイスを受ける。
- 情緒的高揚: 好きな音楽を聴きながら運動するなど、リラックスしてポジティブな気分で行う。
- 行動変容ステージに合わせた働きかけ:
- 無関心期の方へ: まずは自主練習のメリットを知ってもらう、現状のままだと困るかもしれないという気づきを促す。
- 関心期の方へ: 自主練習をしている自分をポジティブにイメージしてもらう。
- 準備期の方へ: 具体的な目標を立て、周囲に「自主練習を始める!」と宣言してもらうことも有効です。
3. 「やり方が合っているか不安」の壁:具体的なツールの活用とフィードバック
「このやり方で合っているのかな?」「一人だとつい甘えちゃう…」といった不安や、日々の記録がないことによるマンネリ化も、継続を妨げる要因です。
乗り越えるヒント:
- パンフレットの活用: 写真やイラスト付きで、運動の目的やポイントが分かりやすく書かれたパンフレットは、自主練習の正確性を高め、習慣化を助けます。 論文では、変形性膝関節症や腰痛症の方向けの具体的なパンフレット例(図3、図4)や、臥位・座位・立位で行える基本的な運動メニュー「Basic5」(図5、図6、図7)が紹介されています。 これらのパンフレットには、各種運動の目的(例:「太ももの内側の筋肉をストレッチ」など)や、実施する上でのポイント(例:「できるだけ力を抜いてリラックス」など)が具体的に記載されています。
- 自主練習記録表の活用: 実施した日や回数を記録することで、利用者さんと理学療法士が共に進捗を確認できます。 これにより、できていることを褒めたり、できていない場合はその理由を一緒に考えたりするきっかけになります。
- 定期的なフォローアップとフィードバック: 理学療法士が定期的に訪問し、自主練習の状況を確認し、適切なアドバイスや励ましを行うことが重要です。 目標の達成度を具体的に伝え(例:「歩く速さがこれだけ速くなりましたね!」など)、頑張りを認めることで、モチベーション向上に繋がります。
安全に続けるために:高齢者・併存疾患のある方の注意点
特に85歳以上の超高齢の方や、複数のご病気をお持ちの利用者の場合、自主練習の負荷量やリスク管理には細心の注意が必要です。
- 無理のない負荷設定: 最初は物足りないと感じるくらいの軽い運動から始め、体調を見ながら徐々に回数や種類を増やしていくことが大切です。
- バイタルサインの確認: 運動前後に血圧や脈拍を測ったり、疲労感を確認したりする習慣をつけましょう。
- 安全な環境で行う: 転倒のリスクを避けるため、不安定な場所での立位運動は避け、必要であれば椅子や壁に手をついて行う、あるいは座位や臥位の運動を選択するなど、安全性を最優先に考えましょう。
- 痛みへの対応: 頑張りすぎて痛みを誘発しないよう、「痛いときは無理しない」「痛みのない範囲で行う」ことを心がけ、痛みが出た場合は専門家に相談しましょう。
今日からできる!自主練習を習慣にするための小さな一歩
では、具体的に今日から何ができるでしょうか?
- まずは目標設定の「準備」から:
- 小さな「できそう」を見つける: 今のあなたにとって、無理なく「これならできそう」と思える簡単な運動を一つ選んでみましょう。それは、論文で紹介されているパンフレットの運動の一つでも良いですし(図3〜7参照) 、深呼吸や足首を動かすといった本当に簡単なことでも構いません。
- 「いつやるか」を決める: 例えば、「朝起きたらベッドの上で足首を10回動かす」「テレビを見ながらCMの間に膝を伸ばす」など、日常生活の中に組み込むと忘れにくいです。
- 「できた!」を記録する:
- 簡単なカレンダーやノートに、実施できたら〇をつけるなど、目で見て達成感が得られるように工夫してみましょう。
- 訪問リハビリの専門家に相談する:
- 「どんな運動がいい?」「このやり方で合ってる?」など、遠慮なく相談してみてください。あなたに合った自主練習メニューや、やる気を引き出すためのアドバイスをくれるはずです。
- 論文でも、理学療法士が関わることで運動プログラムが習慣化しやすくなる可能性が示唆されています。
自主練習は、単なる「宿題」ではありません。ご自身の体と向き合い、より良い生活を送るための「投資」です。焦らず、ご自身のペースで、楽しみながら取り組んでいきましょう。
まとめ
今回は、訪問リハビリテーションを利用されている骨関節疾患の方が、自主練習を効果的に続けるための考え方や具体的な工夫について、大沼剛氏らの論文を基に解説しました。
- 自主練習の鍵は「やらされ感」からの脱却と「自分にもできる!」という自信(自己効力感)。
- 行動変容ステージに合わせたアプローチと、具体的な目標設定が大切。
- 分かりやすいパンフレットや記録表を活用し、専門家からの適切なフィードバックを受けることが継続を後押し。
- 特に高齢の方や複数の疾患をお持ちの方は、安全第一で無理のない範囲で行うことが重要。
自主練習を通じて、昨日より今日、今日より明日と、少しでも体の変化を実感し、笑顔で過ごせる日が増えることを心から応援しています!
参考文献
- 大沼 剛. 在宅で訪問リハビリテーションを利用する骨関節疾患に対する自主練習の考え方. 理学療法学. 2024;51(6):195-200. (本記事内で引用した図版や具体的な自主練習メニューの内容は、この論文に基づいています。)
健康・医学関連情報の注意喚起
本記事は、骨関節疾患における自主練習に関する一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の医学的アドバイスを提供するものではありません。 変形性膝関節症や腰痛症などの診断や治療については、必ず医療従事者にご相談ください。