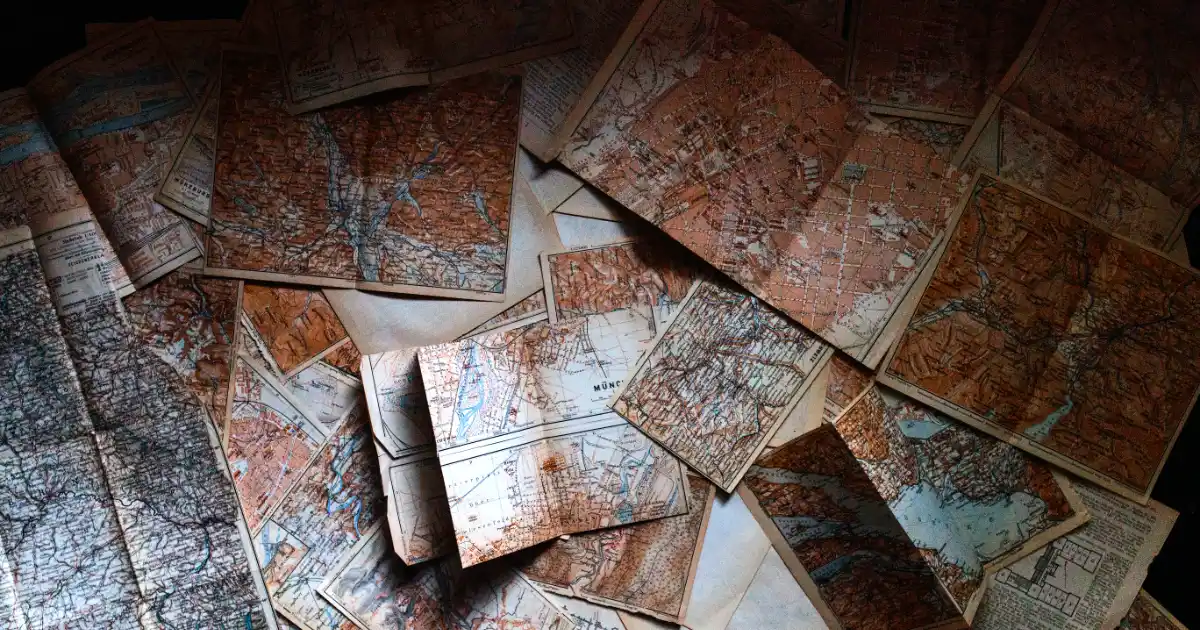はじめに:「休み明けの新患ラッシュ…」情報収集とゴール設定、どう乗り切る?
連休明けや担当患者の入れ替えが重なると、あっという間に複数の新規患者さんを担当することになり、情報収集や書類業務に追われる――。
理学療法士なら誰しも経験する、忙しくも重要な時期ではないでしょうか。
2019年当時、私も連休明けに増える業務に追われながら、「限られた時間で、どうすれば質の高い初期評価とゴール設定ができるのか?」と日々模索していました。
特に、多くの病院で目標とされる「入院後約1週間でのカンファレンスでのゴール提示」は、時に大きなプレッシャーとなります。
この記事では、当時の私の試行錯誤を元に、入院初期という限られた時間の中で、効率的かつ網羅的に情報を収集し、根拠に基づいた初期ゴール(仮説)を立てるための具体的なプロセスと思考法について、2025年の視点から情報をアップデートし、深掘りしていきます。
1. なぜ「最初の1週間」が勝負なのか?初期評価の重要性
入院初期の評価とゴール設定は、その後のリハビリテーション全体の方向性を決定づける、非常に重要なプロセスです。
- 治療の羅針盤となる: 適切なゴール設定は、リハビリテーションの明確な目標となり、介入の選択や優先順位付けの基準となります。
- チームでの情報共有の基盤: 医師、看護師、ソーシャルワーカーなど、多職種チームで患者さんの情報を共有し、一貫したアプローチを行うための共通言語となります。
- 患者・家族の信頼獲得: 専門家として患者さんの全体像を把握し、納得感のあるゴールを提示することは、患者さんやご家族との信頼関係を築く上で不可欠です。
- 早期退院支援への第一歩: 入院初期から退院後の生活を見据えた評価と計画を行うことで、スムーズな在宅復帰や社会復帰を支援できます。
しかし、現実には患者さんの状態が不安定であったり、十分な関わりが持てなかったりと、1週間で全ての情報を集め、完璧なゴールを立てるのは困難な場合も多いです。
だからこそ、効率的で体系的な情報収集の「型」を持つことが重要になります。
2. 1週間で成果を出す!情報収集からゴール設定までの4ステップ・フレームワーク
私が実践していた情報収集とゴール設定の流れを、より具体的なフレームワークとして整理しました。
ステップ1:【情報収集】カルテから「医学的情報(Bio)」と「過去(Before)」を読み解く
リハビリテーションを開始する前に、まずカルテから客観的な情報を収集し、患者さんの医学的背景と病前の状態を把握します。
- 基本情報・現病歴: 年齢、性別、診断名、発症日、現症、治療経過など。
- 既往歴: 過去の病気や手術歴、特に今回の疾患に関連するものや、リハビリテーションのリスクとなりうるもの(心疾患、呼吸器疾患、糖尿病、骨粗鬆症など)。
- 各種検査データ: 血液検査、画像所見(X線、CT、MRIなど)、心電図などから、リスク管理に必要な情報を抽出。
- 病前のADL・IADL:
- 歩行能力: 屋内自立、屋外杖使用、歩行器レベルなど。
- 日常生活動作: 食事、更衣、入浴、トイレ動作などの自立度。
- 生活範囲: 主に自宅内での生活だったか、外出や社会参加はどの程度だったか。
- 社会的背景(初回情報): 職業歴、同居家族の有無、キーパーソンなど。
ポイント: この段階で、現在の状態と病前の能力とのギャップを大まかに把握します。これが、リハビリテーションで目指すべき目標の基礎となります。
ステップ2:【情報収集】他職種から「社会的・環境的情報(Social)」を補完する
次に、他職種、特にソーシャルワーカーや看護師からの情報を活用し、患者さんを取り巻く環境を理解します。
- ソーシャルワーカーのフェイスシート(初期情報記録)の確認:
- 住環境: 家屋形態(一軒家、マンション)、間取り、段差の有無、手すりの設置状況など。
- 介護力・サポート体制: 同居家族の構成、主な介護者、家族の協力度、利用可能な社会資源(介護保険サービスなど)。
- 経済状況や本人の価値観(情報があれば): 退院後の生活設計に関わる情報。
- 看護師からの情報収集:
- 入院後の病棟でのADLの様子、認知機能、精神状態、睡眠・食事・排泄の状況、家族とのやり取りなど、24時間の生活の様子を把握します。
ポイント: 医学的情報だけでは見えてこない、患者さんの生活そのものを具体的にイメージします。これにより、より現実的なゴール設定が可能になります。
ステップ3:【情報収集】患者・家族から「心理・意向(Psycho)」を聴き出す
集めた情報を元に、患者さん本人やご家族から直接お話を伺います。
- 本人の主訴と希望: 今一番困っていることは何か、今後どうなりたいか、何を大切にしているか。
- 退院先に関する意向: 自宅復帰を希望しているか、施設入所も検討しているかなど。
- 自宅環境の詳細: フェイスシートの情報を補完する形で、具体的な間取りや段差、よく使う部屋などを聴取します。
- 心理面の評価: 疾患や将来に対する不安、リハビリテーションへの意欲、痛みに対する捉え方など。
ポイント: ここでは、一方的に質問するのではなく、患者さんやご家族の思いに寄り添い、傾聴する姿勢が重要です。信頼関係を築き、共にゴールを目指すパートナーとしての関係性を構築する第一歩です。
ステップ4:【評価と統合】理学療法評価と「ゴール(仮説)」の立案
ここまでの情報を統合し、理学療法士として専門的な身体機能評価を実施し、初期のゴール(仮説)を立てます。
- 身体機能評価の実施: 関節可動域、筋力、感覚、バランス能力、歩行能力、ADL遂行能力などを具体的に評価します。
- 問題点の抽出と統合:
- ステップ1~3で得た情報と、身体機能評価の結果を統合します。
- ICF(国際生活機能分類)のフレームワークを用いて、「心身機能・身体構造」「活動」「参加」の各レベルにおける問題点を整理すると、全体像が把握しやすくなります。
- 予後予測とゴール(仮説)の立案:
- 疾患の特性、年齢、合併症、病前の能力、本人の意欲などを考慮し、予後を予測します。
- 「〇週間後には、〇〇という条件下で、△△まで可能になるだろう」といった、具体的で測定可能なゴール(仮説)を立てます。
- 退院先の方向性(自宅、施設など)も、この段階で仮説として提示できるように準備します。
なぜ「仮説」なのか? 入院初期は、情報が不十分であったり、患者さんの状態が変動しやすかったりするため、完璧なゴールを立てることは困難です。ここで立てるゴールは、あくまで「現時点で得られる情報に基づく最善の予測(作業仮説:Working Hypothesis)」です。この仮説を元にリハビリを進め、その反応を見ながら随時修正していくという柔軟な姿勢が重要です。2019年の記事で「不確定要素については整理しておく必要がある」と書きましたが、まさにこの「仮説思考」が不確実性に対応するための鍵となります。
3. なぜ情報収集と計画に時間をかけるべきなのか?
「とにかく早くリハビリを始めたい」と思うかもしれませんが、初期の情報収集と計画立案に時間をかけることには、大きなメリットがあります。
- 判断の精度向上: 十分な情報が、より的確な臨床判断と根拠のあるゴール設定を可能にします。
- 手戻りの防止: 方向性のズレたリハビリを進めてしまい、後から大幅な計画修正を迫られるリスクを減らします。
- チーム内での連携強化: 整理された情報を他職種に提供することで、信頼を得やすく、円滑な連携に繋がります。
- 業務の効率化と標準化: 一度患者情報をしっかりと整理しておくことで、カンファレンス資料の作成がスムーズになったり、急な休みでも他のスタッフに情報共有しやすくなったりします。
2019年当時、「一度患者情報をしっかり整理しておくことで他人に整理した情報を渡すことで代理で業務を行ってもらうことも可能」と考えていましたが、これはチーム医療におけるリスク管理の観点からも非常に重要です。
まとめ:体系的な情報収集で、質の高いリハビリテーションをデザインする
変形性股関節症に限らず、あらゆる患者さんを担当する際、入院初期の体系的な情報収集と、それに基づく仮説思考によるゴール設定は、理学療法士にとって不可欠なスキルです。
- Bio-Psycho-Socialの視点で情報を網羅的に収集する。
- Before-Afterの比較で目標の方向性を定める。
- 評価結果を統合し、根拠のある「ゴール仮説」を立てる。
- 常に仮説と検証のサイクル(PDCA)を回し、計画を柔軟に修正する。
私自身、これらのプロセスを自分なりにフォーマット化し、臨床で活用することで、思考の整理がつきやすくなり、カンファレンスでのプレゼンテーションにも自信が持てるようになりました。
将来的には、このようなフレームワークを組織レベルで共有し、新人教育やチーム全体の質の向上に繋げていくことも、私たち中堅以上の理学療法士の役割なのかもしれません。
この記事が、日々の臨床で多忙な中でも、質の高いリハビリテーションを目指す理学療法士の皆さんの一助となれば幸いです。