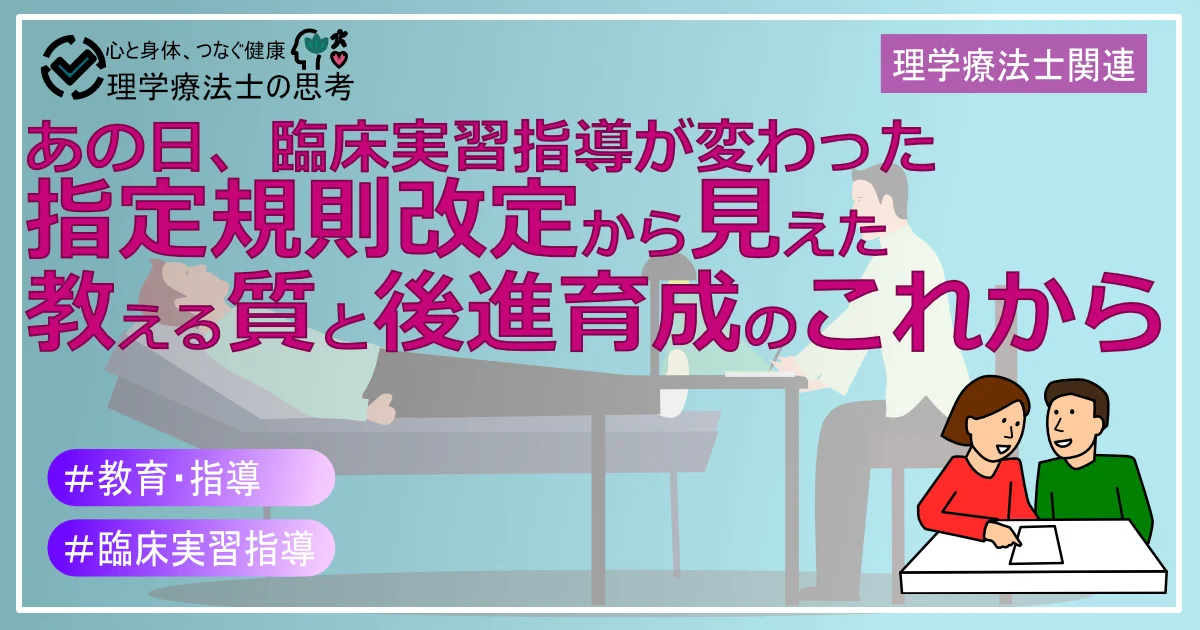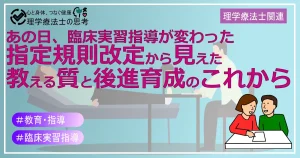理学療法士にとって、未来の仲間となる学生たちを育てる「臨床実習指導」は、非常に重要でやりがいのある役割の一つです。
その指導者のあり方について、数年前(2020年度)に大きな転換点があったことを皆さんは覚えていらっしゃるでしょうか?
今から約6年前の2019年夏、私が所属する日本理学療法士協会(JPTA)から発行されたニュース(JPTA NEWS 2019.vol320 8月号)に目を通した時の衝撃は、今でも少し覚えています。
「臨床実習指導者の要件が、来年度(2020年度)から大きく変わる」という内容でした。「これは知らないとまずいぞ…」と感じた方も多かったのではないでしょうか。
あれから数年が経ち、制度も現場に浸透してきた今、改めて当時の変更内容を振り返り、それが私たちの「教える質」や「後進育成」にどのような意味を持っていたのか、そしてこれから私たちは何を目指すべきなのかを考えてみたいと思います。
この記事は、こんな方におすすめです:
- 現在、臨床実習指導に関わっている理学療法士の方
- これから臨床実習指導者を目指したいと考えている若手・中堅の理学療法士の方
- 理学療法士の教育や育成に関心のある方
あの時、何が変わったのか? 臨床実習指導者 要件変更の振り返り
2020年度、実に約19年ぶりに理学療法士養成施設の基準を定める「指定規則」が改定され、施行されました。
様々な変更点がありましたが、現場で働く私たち理学療法士にとって特にインパクトが大きかったのが、臨床実習指導者の要件変更でした。
具体的に何が変わったのか、当時の情報を元に整理してみましょう。
【改正前の状況】
- 臨床実習を行う施設には、「実務経験3年以上の理学療法士が1人以上いる」ことが主な要件でした。
- 学生を直接指導する担当者(いわゆるバイザー)については、必ずしも3年以上の実務経験が求められていたわけではありませんでした。
- (当時の感覚としては、多くの施設がこの基準を満たしていたのではないでしょうか。)
【改正後の要件(2020年度~)】
- 学生を直接指導するすべての臨床実習指導者は、以下の両方を満たす必要が出てきました。
- 実務経験5年以上であること
- 厚生労働省が指定した「臨床実習指導者講習会」(2日間・合計16時間)を受講していること (※または同等の指定講習会の修了)
- この要件を満たさない理学療法士は、原則として学生を直接指導することができなくなりました。(※ただし、見学実習については、実務経験5年以上の理学療法士であれば、講習会未受講でも指導可能とされました。)
- また、一人の実習指導者が同時に指導できる学生数は、原則として2人まで、という規定も設けられました。
- 学生を直接指導するすべての臨床実習指導者は、以下の両方を満たす必要が出てきました。
当時、この変更を知り、「来年度から指導に携わるには、今年度中に16時間もの講習会を受けなければならないのか!」と、少し焦りを感じた方もいたかもしれません。
実際、多くの理学療法士が講習会に申し込み、指導体制の見直しを迫られた施設もあったことでしょう。
なぜ要件は厳格化されたのか? 制度変更の意図と意義を再考する
では、なぜこのような要件の厳格化が行われたのでしょうか? 当時の私の考察も交えながら、その意図と意義を改めて考えてみます。
意図①:指導者の「質」の担保と向上
最も大きな目的は、やはり臨床実習指導の質を一定レベル以上に保ち、向上させることにあったと考えられます。「実務経験5年以上」という経験値に加え、「指定講習会」で指導に必要な知識やスキル(指導計画の立て方、評価方法、学生とのコミュニケーションなど)を標準化された形で学ぶ機会を設けることで、学生がどの施設で実習を受けても、一定水準以上の指導を受けられる体制を目指したのでしょう。
意図②:指導者の「意識」と「意欲」の可視化
当時の私が記事で考察していたように、この制度変更には、単に知識や経験だけでなく、「指導に対する意欲」や「最新情報を学び続ける姿勢」を持つ理学療法士が指導にあたることを促す側面もあったのではないでしょうか。講習会に参加するという行動自体が、後進育成へのコミットメントを示す一つの指標となりうる、と考えたのかもしれません。変化のスピードが速い医療分野において、指導者自身が学び続ける存在であることの重要性は、今も昔も変わりません。
意図③:社会からの要請と専門職としての責任
質の高い医療専門職を育成することは、安全・安心な医療を求める社会全体の要請でもあります。臨床実習という、学生が専門職としての実践力を身につける極めて重要なプロセスにおいて、その教育の質を高めることは、理学療法士という専門職全体の信頼性を高め、社会的責任を果たしていく上でも不可欠な取り組みと言えます。
質の高い臨床実習指導のために、今、私たちにできること
制度によって指導者の最低限の要件は定められましたが、それはあくまでスタートラインです。質の高い臨床実習指導を提供し続けるためには、私たち一人ひとりが、そして組織全体が、継続的に努力していく必要があります。
- 指導者自身の「学び続ける姿勢」: 指定講習会で学んだ内容は基礎です。指導技術、コミュニケーションスキル、教育学の知見、そしてもちろん最新の臨床知識など、指導者として常に自己研鑽に励むことが求められます。
- 「教える技術」の探求: 知識や経験が豊富であることと、それを効果的に「伝え」「学びに繋げる」ことができるかは別の問題です。学生一人ひとりの個性やレベル、理解度に合わせて、伝え方、質問の仕方、フィードバックの方法などを工夫し、最適な関わり方を探求していく必要があります。
- 組織的な「サポート体制」の構築: 指導者の育成は、個人の努力だけに委ねるべきではありません。施設内で指導者同士が経験や悩みを共有する場を設けたり、外部研修への参加を奨励したりするなど、組織として指導者をサポートし、育てていく文化や体制づくりが重要です。
- 学生との「対話」と「個別性」の尊重: 指導は一方的な知識伝達ではありません。学生の考えや疑問に耳を傾け、対話を通じて共に考え、学びを深めていくプロセスを大切にしたいものです。マニュアル通りの指導ではなく、目の前の学生の特性や課題に合わせた、個別性の高い関わりが求められます。
まとめ:未来の理学療法士を育てる責任とやりがい
2020年度の臨床実習指導者の要件変更は、私たち理学療法士にとって、「後進育成の質」とは何か、そしてそのために何をすべきかを改めて深く考えるきっかけとなりました。
制度が変わったから、というだけでなく、未来の理学療法を担う大切な仲間である学生たちに、質の高い学びの機会を提供し、専門職として成長していくことの厳しさも、そして素晴らしさも伝えていくことは、私たちに課せられた重要な責務であり、他に変えがたい大きなやりがいでもあります。
私自身も、当時の記事で「よく講習会の内容を理解し、しっかり指導できる理学療法士になっていければ」と書いていた初心を忘れず、指導者として、そして一人の理学療法士として、学び続け、成長していきたいと改めて思います。
私たち一人ひとりがより良い指導を目指し続けることが、学生たちの未来を、ひいては理学療法界全体の未来を、より明るく照らしていくことに繋がると信じています。