 Aさん
Aさん「最近、母の口数がめっきり減ってしまって…。年のせいかと思ってたけど、なんだか元気がないのが心配で。」



「わかるなぁ。僕も退職してから、なんとなく気分が晴れない日が多くて。『これが老いか』と諦めてたけど、やっぱり不安だよ。」



「お二人とも、ご家族やご自身の変化に気づかれていること、それ自体がとても大切な第一歩です。
実はその『心の元気』、毎日の食事で少しずつ支えられるかもしれません。
今日は、最新の研究が明かす『魚と心』の意外な関係について、お話ししましょう。」
1分でわかる要約 (1-Minute Summary)
🌱 この記事の結論:魚は「心の栄養」になる
- ✅ 【量】「1日1切れ」が分かれ道
魚をよく食べる(1日約110g)高齢者は、あまり食べない人に比べてうつ病リスクが低いことがわかりました。毎日の習慣が未来を変えます。 - ✅ 【サプリ】効くのは「1.5g」から
サプリメントで効果を得たいなら、中途半端な量では意味がないかもしれません。研究では「1日1.5g以上」の高用量で効果が示唆されています。 - ✅ 【成分】DHAだけじゃない「DPA」
これまで脇役だと思われていた「DPA(ドコサペンタエン酸)」という成分が、実はうつ予防のキープレイヤーである可能性が出てきました。 - 🕊 PTケイのひとこと:
「毎日魚なんて無理!」という方も安心してください。缶詰やサプリの賢い使い方も紹介します。まずは今の自分がどれくらい摂れているか、ツールで計算してみましょう。
研究紹介 (Research Introduction)
2022年、日本の群馬大学大学院医学系研究科の浜崎 景(はまざき けい)氏らが発表した研究によると、高齢者のうつ病とω3系多価不飽和脂肪酸(以下、ω3)の間には、興味深い関連があることが示唆されています。
今回は、この論文を紐解きながら、私たちの生活にどう活かせるかを考えていきましょう。
1. 魚をよく食べる高齢者は「うつ」になりにくい?
まず最も希望が持てるデータとして、「普段から魚をよく食べている人」を約25年間追いかけた研究(観察研究)の結果をご紹介します。
1日「1切れ」のリスク低減効果
長野県佐久地域の住民を対象とした大規模な調査で、以下のことが分かりました。
- 魚をよく食べるグループ(1日約111.1g):うつ病リスクが有意に低い。
- あまり食べないグループ(1日約57.2g):比較対象。
「111g」というのは、スーパーで売っている魚の切り身(鮭やサバ)の「ちょっと大きめ1切れ」くらいです。
つまり、「毎日食卓に魚が並ぶ」人と、「2日に1回程度」の人では、将来の心の健康に差が出る可能性があるのです。



正直に言いますね。私も仕事や家事で疲れ切っている時、「魚を焼く」という行為のハードルの高さに絶望することがあります(笑)。
グリルの掃除も面倒ですしね。でも、「この1切れが20年後の笑顔を作る」と思うと、スーパーで自然と鮮魚コーナーに足が向くようになりました。無理な時は缶詰でOK、という逃げ道を作っておくのが続けるコツです。
新発見!重要成分は「DPA」かもしれない
魚の油といえば「EPA」や「DHA」が有名ですが、この研究で最も強くうつ病リスク低下と関連していたのは、実は「DPA(ドコサペンタエン酸)」という成分でした。
DPAは、体内でEPAからDHAが作られる途中の成分。これまではあまり注目されていませんでしたが、うつ病で亡くなった方の脳内ではこのDPAが減少していたというデータもあり、「心の健康を守る隠れた主役」として注目されています。
2. サプリメントは効くの? カギは「量」にあり
「毎日魚を食べるのはしんどい。サプリで済ませたい」
そう思うのは当然です。しかし、サプリメントの研究結果は「効果あり」「なし」で意見が割れていました。なぜでしょうか?
「1.5gの壁」を超えられるか
複数の研究をまとめて分析(メタ解析)した結果、ある重要な条件が見えてきました。
- ω3摂取量が1日1.5g未満の研究:効果がはっきりしない。
- ω3摂取量が1日1.5g以上の研究:抑うつ症状の改善効果が見られた。
つまり、「なんとなく飲む」のではなく、「しっかりと量を確保して飲む」ことが、効果を実感するための分かれ道になるようです。
【判定ツール】あなたの食事、ω3は足りてる?
「じゃあ、私は普段どれくらい摂れているの?」
気になりますよね。そこで、普段よく食べる魚の頻度から、おおよそのω3摂取量を計算できるツールを用意しました。
以下のツールで、あなたの食生活をチェックしてみてください。
あなたのω3摂取量チェックツール (3種まで)
普段よく食べる魚を最大3種類まで選んで、それぞれの頻度を選択してください。
計算結果はどうでしたか?
「1500mg(1.5g)」というハードルは、意外と高いと感じたのではないでしょうか。 日本人の食事摂取基準(2020年版)では、65〜74歳の目標量は男性2.2g、女性2.0g(α-リノレン酸含む)です。国の基準を満たすような健康的な食生活をしていれば、自然とうつ予防ラインもクリアできる設定になっています。



私も計算してみましたが、忙しい週は余裕で「不足気味」が出ます…。
そんな時は、サプリメントに頼るのも賢い選択です。
ただ、選ぶ時は必ずパッケージの裏を見てください。「EPA・DHA含有量」の合計が少ないものだと、気休めにしかならない可能性があります。「1.5g」という数字を、頭の片隅に置いておいてくださいね。
PTケイのQ&A (Q&A Section)
まとめ (Conclusion)
- 🔍 「週3回」から始める 毎日が無理でも、週に3回食卓に魚が出れば合格点。サバ缶や惣菜を賢く使って、無理なく続けましょう。
- 🎯 サプリは「量」を見る もしサプリを使うなら、成分表示をチェック。「1.5g」に近い高用量のものが、研究で効果を示しています。
- 🕊 食事は「未来への投資」 今日食べた魚が、数年後のあなたの、そしてご家族の笑顔を守る盾になります。焦らず、じっくり積み重ねていきましょう。
親御さんの元気がないと、ご自身まで不安になってしまいますよね。 でも、食事という「毎日できること」で対策ができるというのは、一つの希望でもあります。 今夜は久しぶりに、食卓に魚を並べてみませんか? その香りと温かさが、きっと心も体もほぐしてくれるはずです。
参考文献 (References)&注意喚起 (Disclaimer)
参考文献 (References)
Hamazaki, K. (2022). The Role of ω3 Polyunsaturated Fatty Acids on Geriatric Depression. Oleoscience, 22(7), 337–341.
注意喚起 (Disclaimer)
本記事は、理学療法士の国家資格を持つ筆者の知識と経験、および執筆時点での信頼できる文献に基づいて作成されていますが、医学的な診断や治療を提供するものではありません。
記事内で紹介しているセルフケアや運動は、万人に効果を保証するものではなく、お体の状態によっては適さない場合もあります。
・現在、医師の治療を受けている方は、主治医の指示を優先してください。
・痛み、しびれ、強い疲労感などがある場合は無理を行わず、速やかに専門の医療機関を受診してください。
本記事の情報を利用して生じた損害等について、当サイトは一切の責任を負いかねます。ご自身の体調に合わせて、無理のない範囲で活用してください。

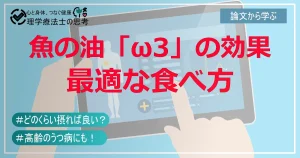
コメント