目次
はじめに
 新人A
新人Aエビデンスって言いますけど、講習会で技術を学んできましたし、結果を出すことの方が大事だと思うんですよね。
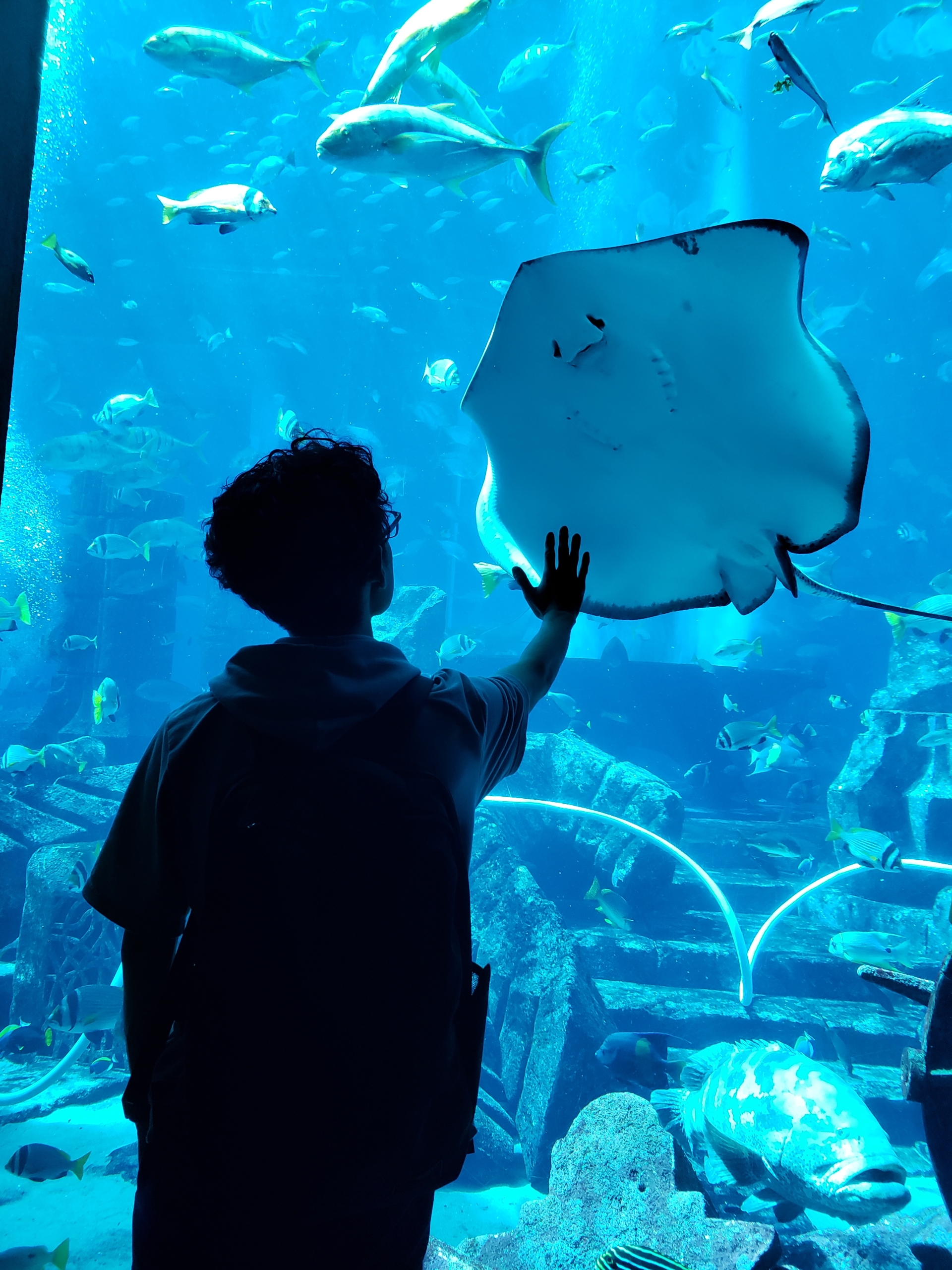
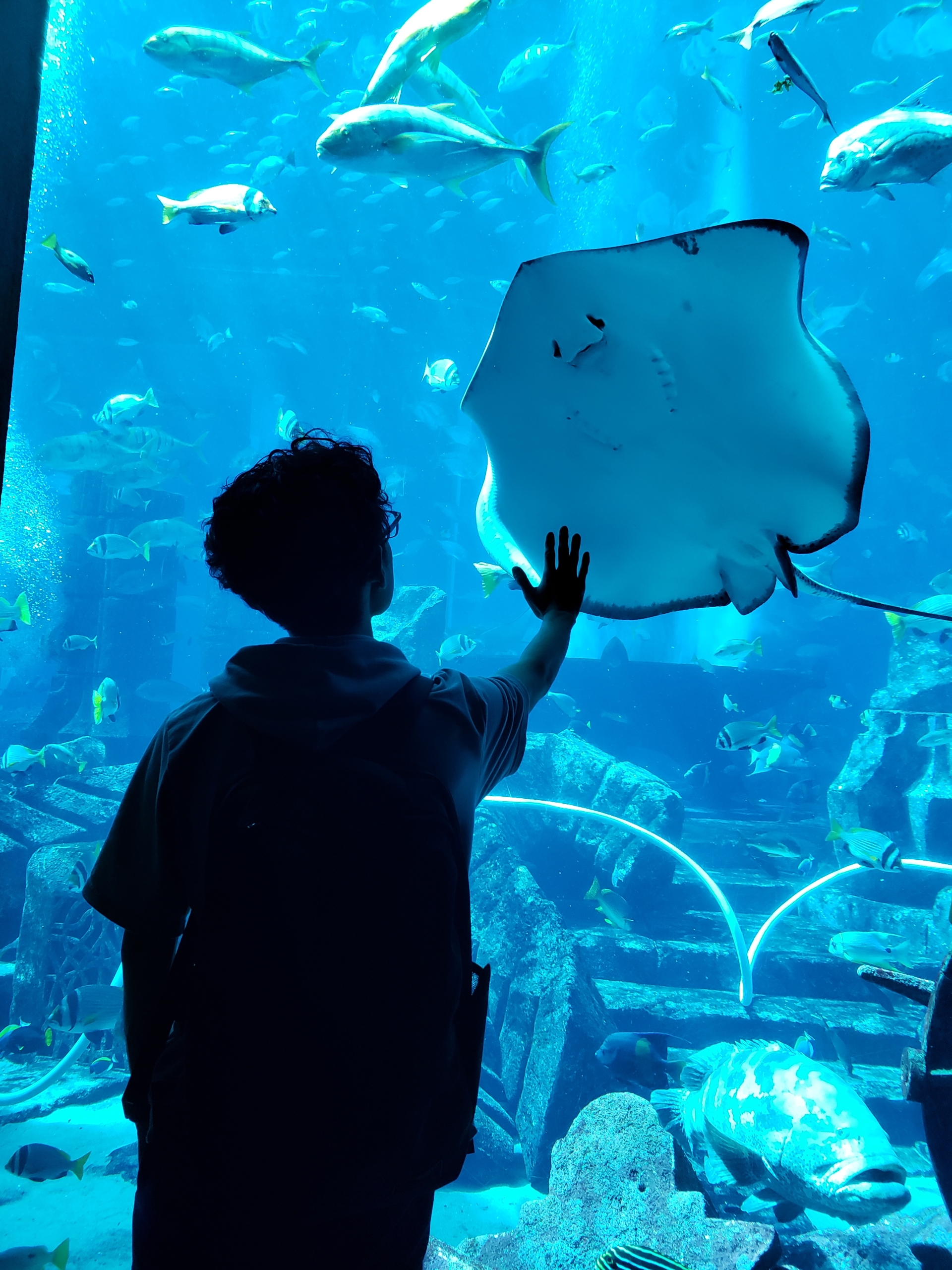
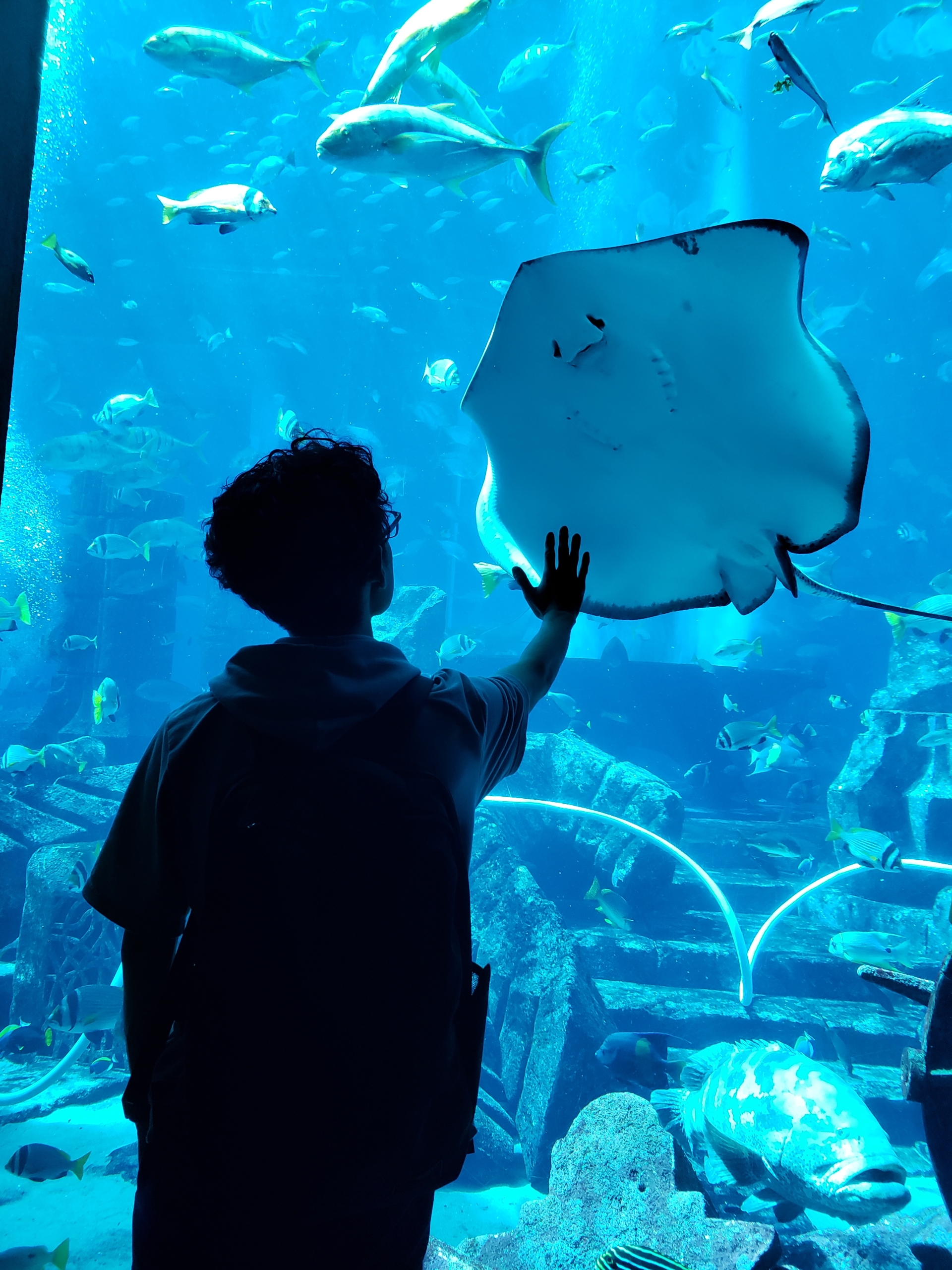
講習会で学んだ技術は確かに重要で結果にも繋がります。理学療法にはアートの部分とサイエンスの部分がありますので、技術は前者になります。後者はエビデンス。ガイドラインを活用することも大切ですよ!



文献を読むとかですかね。ガイドラインってなんですか?
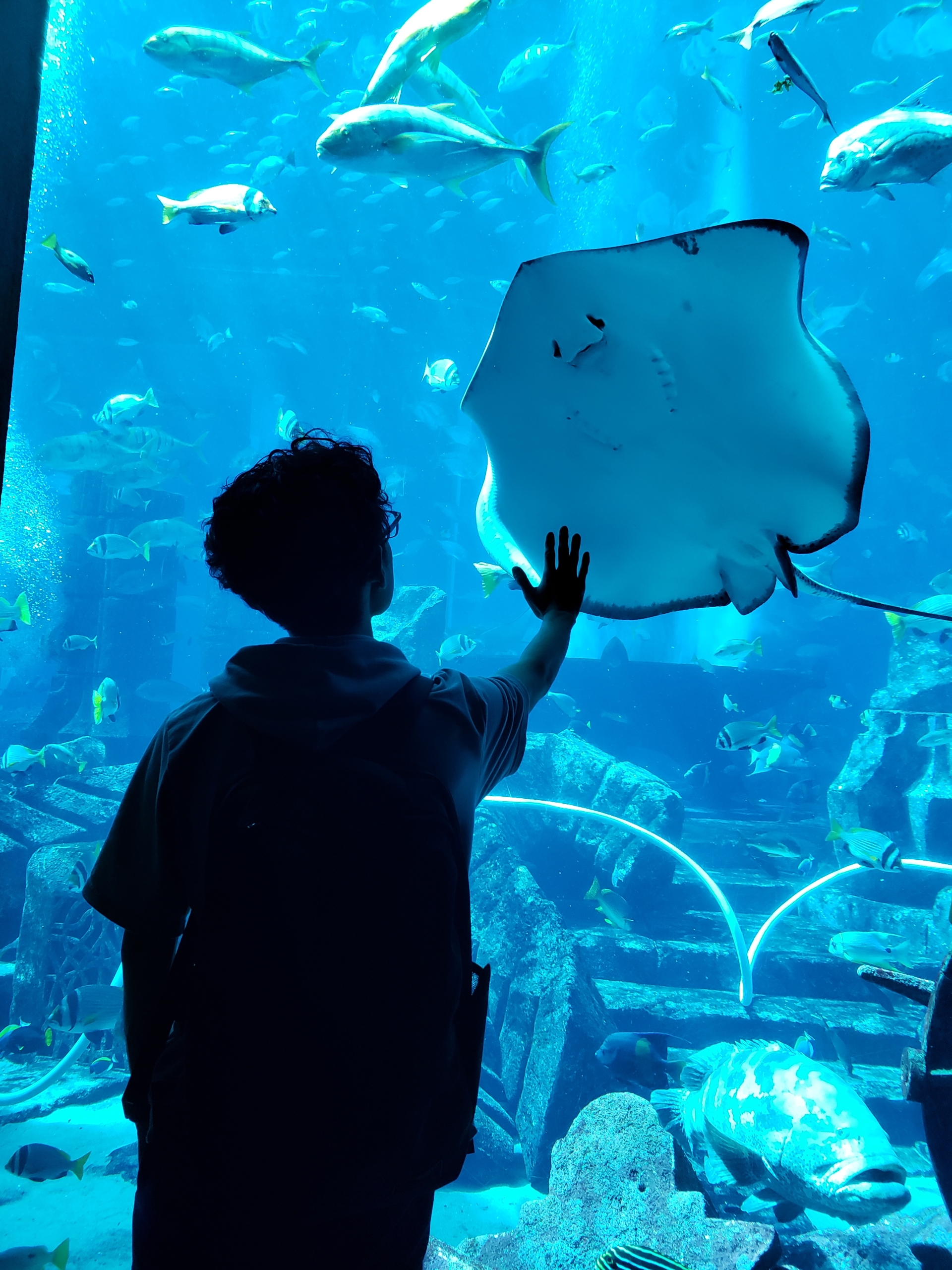
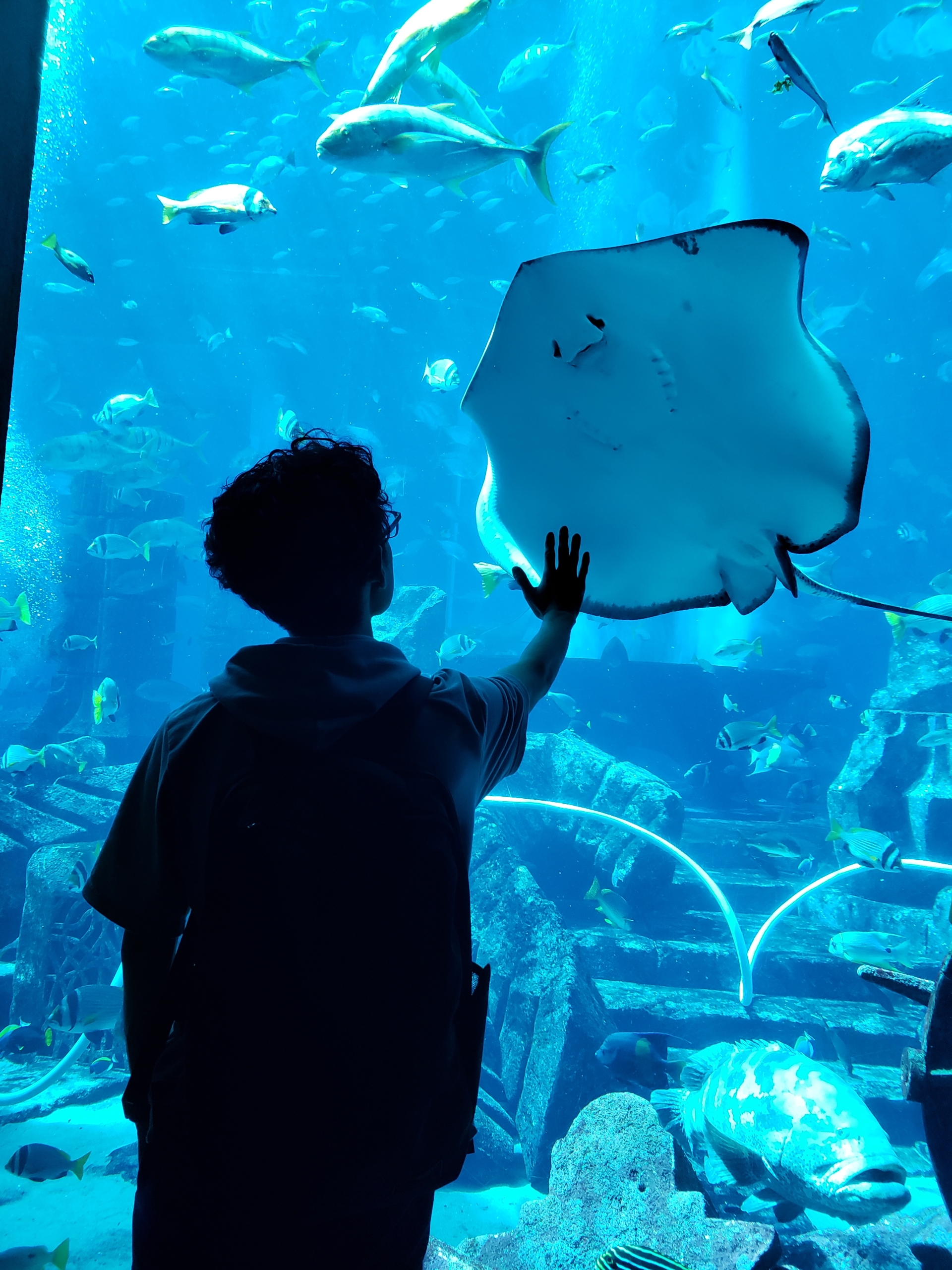
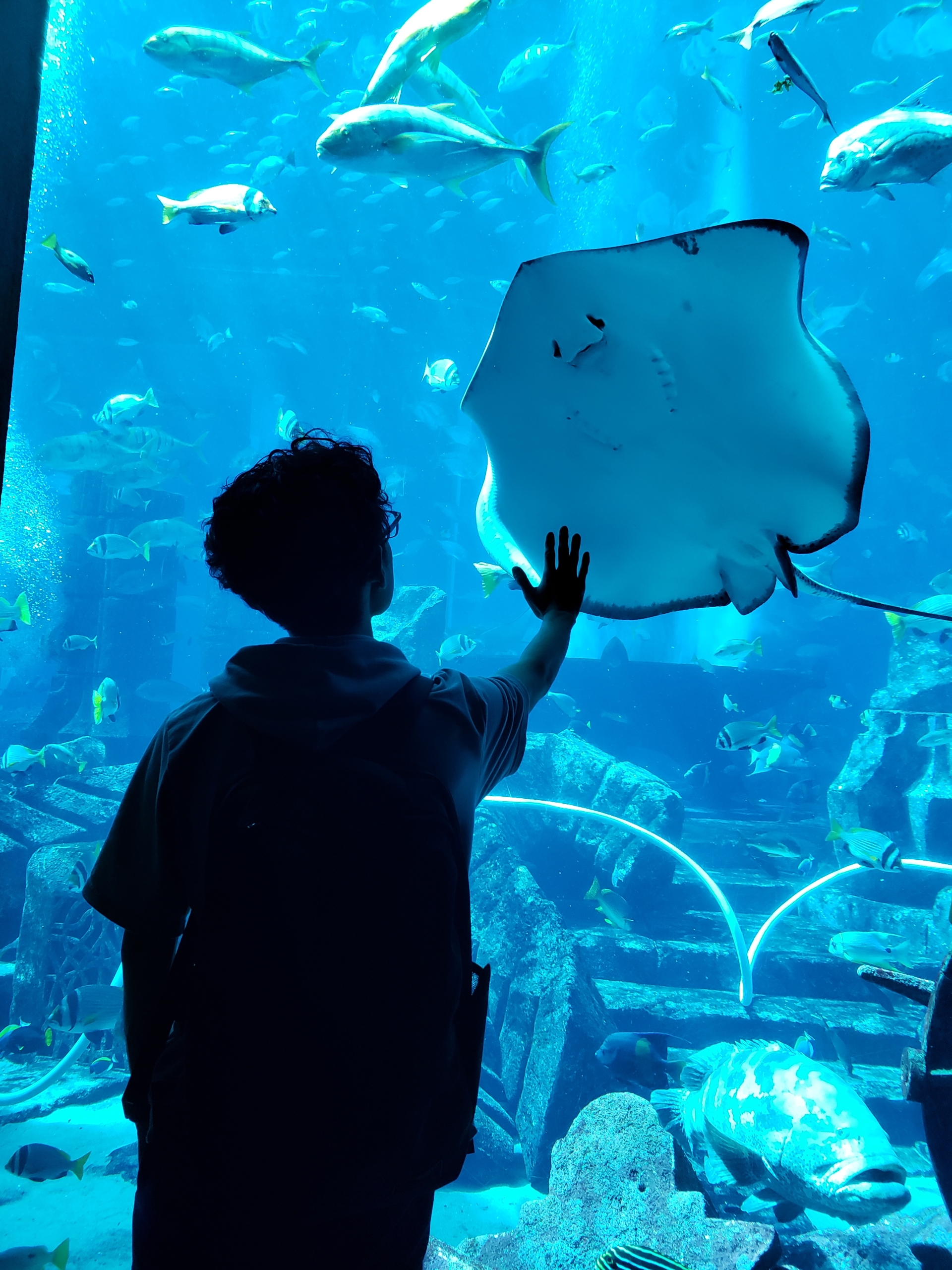
理学療法士協会の会員コンテンツから理学療法の診療ガイドラインが確認できます。認定理学療法士試験でもガイドラインは重視されており、積極的に使うことが推奨されています。今回は、肩関節周囲炎のガイドラインを一緒に見ていきましょう!
理学療法評価(指標)の推奨グレード
以下、推奨グレードA
MRI造影(MRI arthrography)
関節鏡(arthroscopy)
病理所見(pathological examination)
以下、推奨グレードB
理学所見(筋電図)
理学所見(触診)
理学所見(特殊テスト)
評価表(上肢障害評価表:disability of the arm, shoulder and hand: DASH)
評価表(shoulder pain and disability index:SPADI)
磁気共鳴画像(MRI)
骨スキャン(bone scanning)
超音波所見(ultrasonography)
リスクファクター(リスクファクター全般)
リスクファクター(糖尿病)
リスクファクター(肩関節手術後)
リスクファクター(甲状腺疾患)
リスクファクター(血中脂質)
リスクファクター(職業)
合併症(デュピュイトラン拘縮)
以下、推奨グレードC
疫学(発症率)
疫学(予後)
理学所見(可動域)
理学所見(交感神経)
理学所見(動作解析)
単純X線(plain x-ray)
リスクファクター(心臓手術、心臓カテーテル)
リスクファクター(パーキンソン病)
リスクファクター(クモ膜下出血)
合併症(心理的影響)
デルファイ法
理学療法介入の推奨グレードとエビデンスレベル
以下、推奨グレードA
なし
以下、推奨グレードB
一般理学療法 エビデンスレベル2
運動療法(一般運動療法) エビデンスレベル3
運動療法(徒手療法) エビデンスレベル2
物理療法(温熱療法) エビデンスレベル2
物理療法(光線療法:レーザー療法) エビデンスレベル2
理学療法・薬物療法(理学療法・非ステロイド系抗炎症薬)エビデンスレベル2
理学療法・薬物療法(理学療法・ハイドロプラスティー) エビデンスレベル3
理学療法・薬物療法(理学療法・麻酔下マニュピュレーション〈MUA〉)エビデンスレベル3
理学療法・手術療法 エビデンスレベル3
以下、推奨グレードC
物理療法(超音波療法)(C2)エビデンスレベル2
理学療法・注射(理学療法・ステロイド注射)(C1)エビデンスレベル3
現状と展望
- DASHとSPADIの妥当性が示された。
- 関節鏡所見、病理所見、画像所見より肩関節周囲炎では
- 関節滑膜の炎症(一次性拘縮ではないとされる)と肥厚があること
- 関節包、腱板疎部、烏口上腕靭帯が線維化して肥厚していること
- 関節包の容量が少ないこと
- 肩甲下筋下滑液包の閉塞が認められるが、関節内癒着は観察されないこと
- 肩峰下滑液包の血流が増加していること
などが明らかになった。
筋の短縮以外の理学療法のターゲットとして
- 関節包
- 腱板疎部
- 烏口上腕靭帯の伸張性低下と短縮
- 肩甲下筋滑液包の閉塞
- 肩峰下滑液包の閉塞
- 肩峰下滑液包の滑動障害
があげられる。
- 今回の作業で運動療法単独あるいは他の治療との併用は概ね効果があることが分かった。
- しかし、中には肩を含めた全身運動やセルフエクササイズに比べ,運動療法の積極的な介入、特に発症初期での介入が好ましくない影響を及ぼしていることを指摘する文献も見られた。
- 早期の炎症収束と運動強度の選択の重要性を示していると思われる
- 初期の痛みに対する局所注射の併用
- 痛み閾値を超えないストレッチ
- 徒手療法では痛みを出さない強さでの最終域でのモビライゼーションが勧められる。
- 補助的治療としては深部温熱、超音波照射が勧められるが,悪影響を及ぼすことを指摘したものから効果を認めるものまで判定には大きなばらつきがある。
- どの病期に何を狙って照射するか,深達度の選択や温熱効果の排除による差など更なる検討が必要である。
- 理学療法を中心とした保存療法のみでは治療効果が得られない場合には,ハイドロセラピー,麻酔下マニピュレーション,手術などの外科的治療が選択されることがあり,その後に継続的な理学療法を併用することで大きな効果を示す。
- 長期的には外科的に対応した群とそうでない群には大差がないということも明らかになったが、早期の回復を望む場合には外科的治療は大きな意味がある。
- 日常生活の活動性に重点を置いた各種のアンケート形式の評価指標から得られた、年単位の長期的経過では、運動療法や外科的治療の積極的な介入による差がないが、それは即時的あるいは短期間の内に効果を出すために積極的に介入することが無意味であるということでは決してないし、代償動作を排した肩甲上腕関節の可動域を追求した場合には違った結論が得られるかも知れない。
- 今後は,「積極的介入が好ましくない影響を及ぼす」ことがないように,病期を追った組織学的変化と,臨床症状はどの変化を反映しているのかを明らかにし,その起きている変化に合わせた適切な介入が何かを発見しなければならない。
考察
MRI造影(MRI arthrography)
関節鏡(arthroscopy)
病理所見(pathological examination)
のみである。

